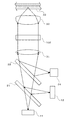JP5056059B2 - 広帯域波長板 - Google Patents
広帯域波長板 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5056059B2 JP5056059B2 JP2007040830A JP2007040830A JP5056059B2 JP 5056059 B2 JP5056059 B2 JP 5056059B2 JP 2007040830 A JP2007040830 A JP 2007040830A JP 2007040830 A JP2007040830 A JP 2007040830A JP 5056059 B2 JP5056059 B2 JP 5056059B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- phase plate
- wavelength
- plate
- polarization
- polarized light
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 147
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 51
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 22
- 239000005264 High molar mass liquid crystal Substances 0.000 claims description 15
- 239000010409 thin film Substances 0.000 claims description 11
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 147
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 26
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 21
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 20
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 17
- 239000010408 film Substances 0.000 description 11
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 9
- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 9
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 8
- 239000004642 Polyimide Substances 0.000 description 7
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 5
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 5
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 4
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 2
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYSA-N 1,2-diphenyl-2-propan-2-yloxyethanone Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(OC(C)C)C(=O)C1=CC=CC=C1 MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 210000002858 crystal cell Anatomy 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- 239000008385 outer phase Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Polarising Elements (AREA)
- Optical Head (AREA)
Description
図1は、本発明の広帯域波長板の概略の構成を示す模式図であり、広帯域波長板101は、入射側位相板1および出射側位相板2によって構成されている。
また、透明基板にAR(Anti Reflection)処理が施される場合は、入射光の透過率が向上するため好ましい。
80°≦Rd1(λ)≦100° (1)
の関係を有すると、好ましい。また、分散の大きい材料を用いることも好ましいが、λ1<λ<λ2を満たすλのうち、いずれか1波長のλに対して第1の位相板103が4分の1波長板として機能するようにしてもよい。
30°≦β≦60° (3)
の関係を有すると、好ましい。通常は、βの値が45°付近になるよう構成することが好ましいが、2つの位相板のリタデーションやその分散等で最も好ましい角度が変化するので、上記範囲で適宜調整することが好ましい。
|{Rd2(λ1)−Rd2(λ2)}/2−α|≦10° (2)
の関係式を有するようにすることが好ましい。また、分散の大きい材料を用いてもよい。ここで、式(2)の右辺の値が0付近となるように構成してもよい。
本発明に係る広帯域波長板を4分の1波長板に適用する場合の実施例を、図2および図3を用いて説明する。
2枚のガラス基板間のギャップは3.0μmとなるようにする。
実施例1においては、広帯域波長板102に入射される2波長の直線偏光の偏光方向のなす角をα=10°としたが、本実施例においては、0°≦α≦90°とした場合における、収束計算の結果求めた、好ましい広帯域波長板の特性を示す。
つまり、Rd2及びαが、上記の式(2)の関係を満たしている。
実施例2においては、本発明に係る広帯域波長板102を4分の1波長板に適用する場合についての特性の計算例を示したが、本実施例においては、広帯域波長板102を2分の1波長板に適用する場合についての特性の計算例を示す。
実施例3においては、広帯域波長板102に入射される2波長の直線偏光の偏光方向のなす角をα=45°としたが、本実施例においては、0°≦α≦90°とした場合において、収束計算の結果求めた、好ましい広帯域波長板の特性を示す。
つまり、Rd2及びαが、上記の式(2)の関係を満たしている。
2 出射側位相板
3、4 高分子液晶
5、6 ガラス基板
7、8 ポリイミド配向膜
9 UV接着剤
11 第1の半導体レーザ(光源)
12 第2の半導体レーザ(光源)
21 第1のハーフミラー
22 第2のハーフミラー
31 コリメータレンズ
32 対物レンズ
33 光ディスク(光記録媒体)
34 光検出器
101 広帯域波長板
102 広帯域波長板
103 第1の位相板
104 第2の位相板
201 第1の位相板の遅相軸
202 第2の位相板の遅相軸
203 偏光方向(偏光面)
204 偏光方向(偏光面)
205 第1の位相板の遅相軸
206 第2の位相板の遅相軸
207 偏光方向(偏光面)
208 偏光方向(偏光面)
Claims (6)
- 複屈折材料によって形成される第1および第2の位相板が互いに積層されるよう構成され、
少なくとも、波長λ1を有する第1の偏光と前記λ1より長い波長λ2を有する第2の偏光とが、互いに異なる方向の直線偏光として前記第1の位相板に入射され、所定の偏光状態に変化して前記第2の位相板から出射されるように用いられる広帯域波長板であって、
前記第1の位相板の光学軸と前記第1の偏光の偏光方向とが交差する角度をθとし、
前記第1の偏光の偏光方向と前記第2の偏光の偏光方向とのなす角度をαとし、
前記第1の位相板の光学軸と前記第2の位相板の光学軸とのなす角度をβとし、
前記第1の位相板の任意の波長λにおけるリタデーション値をRd1(λ)とし、
前記第2の位相板の任意の波長λにおけるリタデーション値をRd2(λ)とすると、
λ 1 ≦λ≦λ 2 の関係式を満たす波長λに対して、前記Rd 1 (λ)が80°≦Rd 1 (λ)≦100°の関係式を満たし、
前記βが30°≦β≦60°の関係式を満たし、
前記Rd 2 (λ 1 )、Rd 2 (λ 2 )及び前記αが、|{Rd 2 (λ 1 )−Rd 2 (λ 2 )}/2−α|≦10°の関係式を満たし、
前記θは、前記第2の位相板を通過することにより前記2つの偏光に与えられる位相差の差Rd2(λ1)−Rd2(λ2)によって、前記第1の位相板を出射した後の2つの偏光のポアンカレ球上での緯度の差を相殺し、前記第2の位相板通過後に2つの偏光の偏光状態が共に楕円率90%以上の楕円偏光となるように設定されていることを特徴とする広帯域波長板。 - 複屈折材料によって形成される第1および第2の位相板が互いに積層されるよう構成され、
少なくとも、波長λ 1 を有する第1の偏光と前記λ 1 より長い波長λ 2 を有する第2の偏光とが、互いに異なる方向の直線偏光として前記第1の位相板に入射され、所定の偏光状態に変化して前記第2の位相板から出射されるように用いられる広帯域波長板であって、
前記第1の位相板の光学軸と前記第1の偏光の偏光方向とが交差する角度をθとし、
前記第1の偏光の偏光方向と前記第2の偏光の偏光方向とのなす角度をαとし、
前記第1の位相板の光学軸と前記第2の位相板の光学軸とのなす角度をβとし、
前記第1の位相板の任意の波長λにおけるリタデーション値をRd 1 (λ)とし、
前記第2の位相板の任意の波長λにおけるリタデーション値をRd 2 (λ)とすると、
λ 1 ≦λ≦λ 2 の関係式を満たす波長λに対して、前記Rd 1 (λ)が80°≦Rd 1 (λ)≦100°の関係式を満たし、
前記βが30°≦β≦60°の関係式を満たし、
前記Rd 2 (λ 1 )、Rd 2 (λ 2 )及び前記αが、|{Rd 2 (λ 1 )−Rd 2 (λ 2 )}/2−α|≦10°の関係式を満たし、
前記θは、前記第2の位相板を通過することにより前記2つの偏光に与えられる位相差の差Rd 2 (λ 1 )−Rd 2 (λ 2 )によって、前記第1の位相板を出射した後の2つの偏光のポアンカレ球上での緯度の差を相殺し、前記第2の位相板通過後に2つの偏光の偏光状態が共に楕円率10%以下の楕円偏光となるように設定されていることを特徴とする広帯域波長板。 - 前記αの増加に応じて、前記第1の位相板のリタデーション値Rd 1 に対する前記第2の位相板のリタデーション値Rd 2 の比Rd 2 /Rd 1 が実質的に増加する請求項1または2に記載の広帯域波長板。
- 前記複屈折材料が高分子液晶の薄膜層により構成されている請求項1から3のいずれか1項に記載の広帯域波長板。
- 前記θが、前記αの増加に応じて実質的に増加するように設定されている請求項1から4のいずれか1項に記載の広帯域波長板。
- 複数の波長の光を出射する光源と、
前記光源から出射された光を光記録媒体上に集光させる対物レンズと、
前記光記録媒体により反射された光を検出する光検出器とを備える光ヘッド装置において、
前記光源と前記対物レンズとの間の光路中に請求項1から5のいずれか1項に記載の広帯域波長板が配置されていることを特徴とする光ヘッド装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007040830A JP5056059B2 (ja) | 2006-02-21 | 2007-02-21 | 広帯域波長板 |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2006043990 | 2006-02-21 | ||
| JP2006043990 | 2006-02-21 | ||
| JP2007040830A JP5056059B2 (ja) | 2006-02-21 | 2007-02-21 | 広帯域波長板 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2007256937A JP2007256937A (ja) | 2007-10-04 |
| JP5056059B2 true JP5056059B2 (ja) | 2012-10-24 |
Family
ID=38631184
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007040830A Active JP5056059B2 (ja) | 2006-02-21 | 2007-02-21 | 広帯域波長板 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5056059B2 (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5171214B2 (ja) * | 2007-11-07 | 2013-03-27 | リコー光学株式会社 | フォトニック結晶を用いた波長板の製造方法 |
| JP2017044797A (ja) | 2015-08-25 | 2017-03-02 | 株式会社ルケオ | 波長可変フィルター |
| JP2017090585A (ja) * | 2015-11-06 | 2017-05-25 | 日本電信電話株式会社 | 広帯域波長板およびその作製方法 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3174367B2 (ja) * | 1991-10-07 | 2001-06-11 | 日東電工株式会社 | 積層波長板及び円偏光板 |
| JPH1068816A (ja) * | 1996-08-29 | 1998-03-10 | Sharp Corp | 位相差板及び円偏光板 |
| CN1161642C (zh) * | 1997-05-09 | 2004-08-11 | 夏普公司 | 叠层相位差板以及由该板构成的液晶显示装置 |
| JPH11149015A (ja) * | 1997-11-14 | 1999-06-02 | Nitto Denko Corp | 積層波長板、円偏光板及び液晶表示装置 |
| JP3671768B2 (ja) * | 1999-09-30 | 2005-07-13 | 旭硝子株式会社 | 光ヘッド装置 |
| WO2003091768A1 (en) * | 2002-04-26 | 2003-11-06 | Toyo Communication Equipment Co., Ltd. | Laminate wavelength plate and optical pickup using it |
| JP4218393B2 (ja) * | 2003-03-28 | 2009-02-04 | 旭硝子株式会社 | 光ヘッド装置 |
| JP2004354936A (ja) * | 2003-05-30 | 2004-12-16 | Toyo Commun Equip Co Ltd | 積層波長板及びそれを用いた光ピックアップ |
-
2007
- 2007-02-21 JP JP2007040830A patent/JP5056059B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2007256937A (ja) | 2007-10-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| TWI406018B (zh) | 利用光校準液晶的笛卡兒偏光板 | |
| JP3671768B2 (ja) | 光ヘッド装置 | |
| JP5056059B2 (ja) | 広帯域波長板 | |
| JP4300784B2 (ja) | 光ヘッド装置 | |
| JP4930084B2 (ja) | 広帯域波長板 | |
| JP5316409B2 (ja) | 位相差素子および光ヘッド装置 | |
| JP5228805B2 (ja) | 積層1/4波長板 | |
| JP5071316B2 (ja) | 広帯域波長板および光ヘッド装置 | |
| JP5347911B2 (ja) | 1/2波長板、光ピックアップ装置、偏光変換素子及び投写型表示装置 | |
| JP4349335B2 (ja) | 光ヘッド装置 | |
| JP2007280460A (ja) | 光ヘッド装置 | |
| JP5131244B2 (ja) | 積層位相板及び光ヘッド装置 | |
| JP4626026B2 (ja) | 光ヘッド装置 | |
| JP3968593B2 (ja) | 光ヘッド装置 | |
| US8040781B2 (en) | Wavelength selecting wavelength plate and optical head device using it | |
| JP2005339595A (ja) | 光ヘッド装置 | |
| JP4876826B2 (ja) | 位相差素子および光ヘッド装置 | |
| JP4427877B2 (ja) | 開口制限素子および光ヘッド装置 | |
| JP2010146605A (ja) | 広帯域波長板および光ヘッド装置 | |
| JP2002250815A (ja) | 2波長用位相板および光ヘッド装置 | |
| JP2010238350A (ja) | 光ヘッド装置 | |
| JP2001311821A (ja) | 位相子および光ヘッド装置 | |
| JP2008004146A (ja) | 光学素子および光学素子を備えた光ヘッド装置 | |
| JP2009176417A (ja) | 光ヘッド装置 | |
| JP4222042B2 (ja) | 光ヘッド装置と光ヘッド装置に用いられる位相板の製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20090904 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20110114 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110802 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110922 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120703 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120716 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150810 Year of fee payment: 3 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 5056059 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150810 Year of fee payment: 3 |
|
| S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |