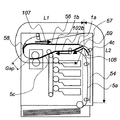JP4482297B2 - 電子写真装置 - Google Patents
電子写真装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP4482297B2 JP4482297B2 JP2003204997A JP2003204997A JP4482297B2 JP 4482297 B2 JP4482297 B2 JP 4482297B2 JP 2003204997 A JP2003204997 A JP 2003204997A JP 2003204997 A JP2003204997 A JP 2003204997A JP 4482297 B2 JP4482297 B2 JP 4482297B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- conveyance path
- recording medium
- electrophotographic apparatus
- paper
- unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 105
- 238000007639 printing Methods 0.000 claims description 84
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 16
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 3
- 238000000151 deposition Methods 0.000 claims 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims 1
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 138
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 41
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 30
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 description 18
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 13
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 9
- 238000011161 development Methods 0.000 description 7
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 6
- 108091008695 photoreceptors Proteins 0.000 description 6
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 6
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 4
- 230000003252 repetitive effect Effects 0.000 description 4
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 3
- 238000003491 array Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000010408 film Substances 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004642 Polyimide Substances 0.000 description 1
- BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N Selenium Chemical compound [Se] BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920006311 Urethane elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229910001120 nichrome Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 1
- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000007790 scraping Methods 0.000 description 1
- 229910052711 selenium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011669 selenium Substances 0.000 description 1
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 description 1
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
- G03G15/22—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern involving the combination of more than one step according to groups G03G13/02 - G03G13/20
- G03G15/23—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern involving the combination of more than one step according to groups G03G13/02 - G03G13/20 specially adapted for copying both sides of an original or for copying on both sides of a recording or image-receiving material
- G03G15/231—Arrangements for copying on both sides of a recording or image-receiving material
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G2215/00—Apparatus for electrophotographic processes
- G03G2215/01—Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies
- G03G2215/0103—Plural electrographic recording members
- G03G2215/0119—Linear arrangement adjacent plural transfer points
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Color Electrophotography (AREA)
- Separation, Sorting, Adjustment, Or Bending Of Sheets To Be Conveyed (AREA)
- Conveyance By Endless Belt Conveyors (AREA)
- Counters In Electrophotography And Two-Sided Copying (AREA)
- Paper Feeding For Electrophotography (AREA)
- Electrophotography Configuration And Component (AREA)
Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子写真技術を用いてカラー画像を形成する複写機,プリンタ,ファクシミリなどの電子写真装置に係り、特に複数色の着色されたトナーを用いてカラー画像を生成する電子写真装置の両面印刷手段に関する。
【0002】
【従来の技術】
電子写真方式では、一様に帯電させた感光体上に露光手段からの光を照射して画像データに対応した静電潜像を形成し、感光体上の静電潜像にトナーを付着させて静電潜像を現像し、このトナー画像を記録媒体に転写し定着させる。
【0003】
この「発明の詳細な説明」では、記録媒体を用紙として説明するが、記録媒体は、紙に限らず、プラスチックなどの種々の素材で形成されたシート状の記録媒体をすべて含む。
【0004】
カラー画像を形成する場合は、例えば、イエローY,マゼンタM,シアンC,ブラックKなどの複数のカラートナーを重ね合わせて画像を形成する。
【0005】
カラー画像形成方式には、1つの感光体に各カラートナーを繰り返し現像してカラー画像を形成する繰り返し現像方式と、複数個の感光体で各カラートナーを同時に現像してカラー画像を形成する同時現像方式とがある。
【0006】
繰り返し現像方式は、1つの感光体を用いてカラー画像を形成する方式であり、その一例として、中間転写体方式がある。
【0007】
中間転写体方式とは、感光体の周囲に各々異なるカラートナーを現像する複数個の現像器と中間転写体とを配置し、感光体上に形成したトナー画像を中間転写体上に順次1色ずつ転写する方式である(例えば、特許文献1参照)。
【0008】
この転写を各色ごとに繰り返して複数のカラートナー画像を中間転写体上で重ね合わせた後、中間転写体上のカラートナー画像を媒体に転写し、カラー画像を定着させる。
【0009】
中間転写体方式では、例えば、イエローY,マゼンタM,シアンC,ブラックKのカラートナー画像を1色ずつ感光体上に順次形成し、中間転写体上に重ね合わせて転写するので、モノクロ画像を形成する場合と比較すると、画像形成におよそ4倍の時間を要する。
【0010】
同時現像方式とは、各色に対応した複数の感光体でほぼ同時にトナー画像を形成し、用紙の搬送に対応させてトナー画像を転写し、カラー画像を形成する方式であり、タンデム方式とも呼ばれる(例えば、特許文献2参照)。
【0011】
タンデム方式では、感光体,帯電手段,露光手段,現像手段,クリーナ手段を含む画像形成手段を各色ごとに独立して備えるので、イエローY,マゼンタM,シアンC,ブラックKのカラートナーによってカラー画像を形成する場合には、画像形成手段を4セット備えなくてはならない。
【0012】
タンデム方式では、独立した4セットの画像形成手段でほぼ同時並行にトナー画像を形成し、トナー画像を中間転写体または用紙に転写する。タンデム方式は、カラー画像を同時に重ねるので、モノクロ画像を形成する場合と比較すると、ほぼ同じ時間でカラー画像を形成でき、カラー画像の高速印刷に向いた方式である。
【0013】
近年、オフィスでは文書のカラー化の要求が高まり、カラープリンタが急速に普及しつつある。また、印刷の高速化が望まれ、タンデム方式のカラープリンタが注目されている。
【0014】
ところが、タンデム方式のカラープリンタは、画像形成手段を4セット備えるため、装置の小型化が困難であり、繰り返し現像方式のカラープリンタと比べて大型であった。
【0015】
装置の小型化のためには、高さを低くして偏平な形状とする方法と、面積を削減して高さを増した縦形の形状とする方法とがある。プリンタがオフィスや家庭に設置される場合には、高さ方向の制約が比較的少ないので、体積が同一ならば設置面積を削減して高さを増した形態の方が望ましい。
【0016】
さらに、近年では、紙資源の節約のために両面に印刷する両面印刷機能が求められているので、両面印刷機能を装備しながら装置を小型化することが要望されている。
【0017】
繰り返し現像方式のカラープリンタの場合には、裏側に印刷するイエロー,マゼンタ,シアン,ブラックの4色のトナー画像を1色ずつ感光体上に順次形成し、中間転写体に重ね合わせるので、その間に用紙の裏側に画像を転写する準備として用紙を反転する時間があり、片面印刷でも両面印刷においても、印刷速度は変わらない。
【0018】
これに対して、タンデム式プリンタの場合には、片面に連続して印刷する場合には例えば用紙は50mm程度の間隔を開けて連続的に印刷される。
【0019】
しかし、両面印刷の場合には、片面の印刷が完了した用紙を反転し、用紙の後端を先端とするように搬送方向を反転し、転写手段よりも上流側の搬送路に進行方向を反転した用紙を挿入して、中間転写体上に形成されたフルカラー画像を裏側に転写してから定着するので、用紙を反転する間は用紙上にトナー画像を転写できないから、両面印刷時には、片面印刷時と比べて、毎分当たりの印刷速度は低下する。
【0020】
そこで、両面印刷時の印刷速度を片面印刷時にできるだけ近づけ、同じ印刷速度に高速化することが望まれている。
【0021】
両面印刷時に、ほぼ垂直に用紙を搬送しながら画像を形成する電子写真装置が知られている(例えば、特許文献3参照)。
【0022】
この電子写真装置においては、複数の画像形成手段に沿ってトナー画像を用紙上に転写しながらほぼ垂直に下方から上方に用紙を搬送するシート搬送手段と、両面印刷しようとする用紙の先端を後端とするように反転させる反転手段のシート反転搬送部と、反転搬送部から上向きに送出されるシートの進行方向をほぼ180°反転させて下方に向ける曲面ガイド部と、曲面ガイド部からレジストローラ対よりも用紙カセット側まで搬送する再給紙手段とを、開放可能な開閉扉に設けている。
【0023】
この電子写真装置では、定着手段が画像形成部よりも上部に配置されており、装置のほぼ最上部にある。
【0024】
一方、用紙に画像を転写する画像形成部の開始点に当たるレジストローラは、用紙カセットに近く、搬送路の最下部にある。
【0025】
裏面を印刷するには、表側画像の転写および定着が完了した用紙を反転搬送部に上方から挿入し、それまでの後端を先端とするように進行方向を反転し、搬送路のレジストローラの上流側で搬送路に合流させてから裏面に画像を転写する。
【0026】
また、主搬送路とバイパス搬送路とを備え、バイパス搬送路により記録媒体を反転させて主搬送路に戻し、裏を向けて再度主搬送路を搬送する電子写真装置が知られている(例えば、特許文献4参照)。
【0027】
【特許文献1】
特開平08−137179号公報(第3〜4頁,図1)
【特許文献2】
特開2001−356548号公報(第4〜6頁,図1)
【特許文献3】
特開2001−002330号公報(第3〜4頁,図1)
【特許文献4】
特開平06−208266号公報(第4〜5頁,図1)
【0028】
【発明が解決しようとする課題】
特許文献3の電子写真装置において、反転搬送路から送出された用紙をレジストローラまで搬送する戻り搬送路は、反転搬送路から上向きに送出されてからほぼ180°向きを変えて下向きに装置の下端近傍まで搬送し、再度ほぼ180°向きを変えて搬送方向を上向きにしてからレジストローラの上流側において搬送路と合流させる必要があるので、ほぼ半円形状の曲面ガイドを上下に設ける構成となる。
【0029】
この曲面ガイド部分を小さな半径にしようとすると、搬送される用紙ジャムが発生しやすくなるので、あまり小さくできず、例えば直径で50mm程度が最小となる。
【0030】
したがって、開閉扉の厚さは、曲面ガイドの直径に、更に搬送ローラを反転搬送部と再給紙手段とに実装するスペースが必要となるので、その厚さは最低でも70mm程度は必要となり、電子写真装置の小型化には限界がある。
【0031】
また、この従来技術においては、開閉扉部にはシート搬送手段,再給紙手段,シート反転搬送部の3層のシート搬送手段を備えているので、開閉扉は更に厚くなる。
【0032】
特許文献4の電子写真装置において、裏側を印刷する場合、用紙を一時的に収納する反転搬送路に相当する余計なスペースをとらないので、小型化に適した構成ではある。
【0033】
しかし、裏側を印刷する際には、用紙が主搬送路を逆方向に搬送されるので、反転が完了するまで次ページの印刷用紙を給紙できないことになり、両面印刷の高速化には限界がある。
【0034】
本発明の目的は、両面印刷機能を備え両面印刷時にも高速に印刷できる小型の電子写真装置を提供することである。
【0035】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、感光体ドラムと前記感光体ドラムの感光層に静電潜像を形成する露光手段と前記感光体ドラムの静電潜像にトナーを付着させてトナー像を形成する現像手段とを含む複数の画像形成手段と、駆動ローラと従動ローラとに張り渡されて回転する無端の中間転写ベルトと、前記感光体ドラムの列の上方に配置され前記中間転写ベルトから記録媒体にトナー像を転写する第2転写手段とを有し、前記複数の感光体ドラムに形成されたトナー像を前記中間転写ベルトを介して記録媒体に転写しカラー画像を形成する電子写真装置において、電子写真装置本体前面に、前記現像手段を着脱するための開閉扉を有し、該開閉扉内に設けられ且つ記録媒体を収納する用紙カセットから供給された前記記録媒体を上方に搬送する縦搬送路と、屈曲搬送路と、前記第2転写手段までほぼ水平に前記記録媒体を搬送する横搬送路とからなる記録媒体供給経路と、前記転写手段よりも下流の前記横搬送路に配置されて転写されたトナー像を前記記録媒体上に定着させる定着手段と、印刷が完了した記録媒体を排出して堆積する排紙トレイと、既に片面が印刷され両面印刷する記録媒体を搬送するバイパス搬送路と、前記両面印刷する記録媒体を前記排紙トレイへの搬送路から前記バイパス搬送路に導く第1分岐手段と、両面印刷時に前記バイパス搬送路で搬送された前記記録媒体を反転させるスリット形状の反転搬送路と、両面印刷時に前記反転搬送路で反転された前記記録媒体を前記バイパス搬送路から前記横搬送路に導く第2分岐手段と、前記第2分岐手段を通過した前記記録媒体を前記横搬送路に搬送する戻り搬送路とを備え、前記反転搬送路を前記開閉扉内の前記縦搬送路にほぼ並行させて設置し、前記反転搬送路内に挿入されまたはそこから送り出される前記記録媒体を駆動する搬送ローラを開閉扉上方の装置本体側に設けたことを特徴とする。
【0038】
開閉扉は、記録媒体ジャムの処理などのメンテナンスのために、縦搬送路に沿って開放する機構を有することができる。
【0039】
部品交換や記録媒体ジャムの処理などのメンテナンスのために、屈曲搬送路および横搬送路に沿って開放されるケース上部を備えると便利である。
【0040】
さらに、ケース上部が、バイパス搬送路に沿って開放する機構を備えると、ケース上部内のメンテナンス作業をしやすくなる。
【0041】
戻り搬送路のほぼ延長線上に手差し給紙トレイを設けると、厚紙などの特殊紙にも情報を記録できる。
【0042】
バイパス搬送路上の第2分岐手段から横搬送路の第2転写手段,定着手段,第1分岐手段,バイパス搬送路を経由して再び第2分岐手段に至るまでの長さをL1とし、第2分岐手段から用紙カセットの近傍に至るまでの反転搬送路の長さをL2とし、記録媒体の最大長さをPmaxとし、搬送される記録媒体同士の間隔をGapとして、
L1>(2×Pmax+Gap)
L2>Pmax
の関係を満たすことが望ましい。
【0043】
その場合は、第2分岐手段からの戻り搬送路をS字形状として、戻り搬送路の必要な長さを確保してもよい。
【0044】
バイパス搬送路上の第2分岐手段から横搬送路の第2転写手段,定着手段,第1分岐手段,バイパス搬送路を経由して再び第2分岐手段に至るまでの長さをL1とし、第2分岐手段から用紙カセットの近傍に至るまでの反転搬送路の長さをL2とし、記録媒体の最大長さをPmaxとし、搬送される記録媒体同士の間隔をGapとして、
L1<(2×Pmax+Gap)
L2>Pmax
の関係を満たすようにすることもできる。この場合は、両面印刷時に前後の記録媒体の一部が重なってすれ違うことになる。
【0045】
第2分岐手段は、反転搬送路から送り出される記録媒体の先端を戻り搬送路に導く段差を備えることができる。
【0046】
第2分岐手段は、また、記録媒体がバイパス搬送路から反転搬送路に送り込まれる時は、記録媒体により持ち上げられ、記録媒体が反転搬送路から戻り搬送路に送り込まれる時は、自重により自然落下し、反転搬送路から送り出される記録媒体の先端を戻り搬送路に導く分岐補助部材を備えることも可能である。
【0047】
第2分岐手段から反転搬送路への搬送路における記録媒体の有無を検出し反転搬送路に関連する記録媒体駆動機構の動作タイミングを規定する記録媒体検出手段を設ける。
【0048】
【発明の実施の形態】
次に、図1〜図18を参照して、本発明による電子写真装置の実施形態を説明する。
【0049】
【実施形態1】
図1は、本発明による両面印刷機能を備えた電子写真装置の実施形態1の全体構成を示す断面図である。
【0050】
実施形態1の電子写真装置は、ケース100と、用紙カセット2と、用紙分離手段3と、搬送手段4と、用紙搬送路5と、開閉扉6と、用紙位置検出手段8と、レジストローラ9と、イエローY,マゼンタM,シアンC,ブラックKの4セットの画像形成手段70と、中間転写ベルト44と、駆動ローラ45と、従動ローラ45aと、張力調整ローラ46と、転写クリーニング手段48と、第2転写手段50と、定着手段51と、一対の排紙ローラ52と、排紙トレイ53とからなる。
【0051】
用紙カセット2は、ケース100の底部に前面側に引き出し可能に配置され、用紙1を収容する。用紙分離手段3は、用紙カセット2の開閉扉6に近い側の端部に設置され、用紙カセット2にセットされた複数の印刷用紙1を1枚ずつ分離する。
【0052】
搬送手段4は、ゴムローラなどからなり、用紙搬送ガイドを備える用紙搬送路5に沿って1枚ずつに分離された用紙1を矢印102方向に所定速度で搬送する。用紙搬送路5は、用紙分離手段3と用紙カセット2との接点から始まり、駆動ローラ45および第2転写手段50を経て、排紙ローラ52まで延びている。すなわち、用紙搬送路5は、用紙1を上方に搬送する縦搬送路5aと、ゆるやかにカーブして用紙1を第2転写手段50方向に向かわせる屈曲搬送路5bと、方向を変えた用紙1を横方向に搬送する横搬送路5cとからなる。
【0053】
開閉扉6は、ケース100の前面に配置され、回動支点7を中心にして矢印101方向に開く。
【0054】
用紙位置検出手段8は、レジストローラ9の上流側の横搬送路5cに配置され、用紙位置を検出する。用紙位置検出手段8は、用紙1表面からの光反射量の変化を検出する反射光検出方式、用紙1が発光体と受光体との間を通過する際の受光量変化を検出する透過光検出方式、用紙1先端のレバーへの接触を検出するレバー検出方式などのいずれかを採用し、用紙1の先端が用紙位置検出手段8に到達したことを検出し、用紙位置信号を出力する。一対のレジストローラ9は、第2転写手段50の屈曲搬送路5bに近い側の横搬送路5cに、第2転写手段50に隣接して配置されている。
【0055】
イエローY,マゼンタM,シアンC,ブラックKの画像形成手段70は、中間転写ベルト44の開閉扉6に近い側に沿って上から順に積み重ね配置されている。
【0056】
無端の中間転写ベルト44は、駆動ローラ45と従動ローラ45aとに環状に掛け渡されている。駆動ローラ45は、軸線を回動支点7の軸線に平行させてケース100の中央上部に設置されている。従動ローラ45aは、軸線を駆動ローラ45の軸線に平行させて駆動ローラ45の下方に配置されている。張力調整ローラ46は、中間転写ベルト44の開閉扉6から遠い側の内側に接触している。
【0057】
転写クリーニング手段48は、中間転写ベルト44を挟んで、従動ローラ45a対向している。転写クリーニング手段48は、一端を中間転写ベルト44の外周面に所定圧力で接触させて配置され、外周面に残留しているトナーを掻き落とすクリーニングブレード49を備えている。掻き落とされたトナーは、転写クリーニング手段48の容器に集積される。
【0058】
なお、実施形態1では、中間転写ベルト44の外周面に残留しているトナーを掻き落とすために、クリーニングブレード49を用いているが、クリーニングローラを用いてもよい。
【0059】
第2転写手段50は、駆動ローラ45に軸線を平行させ、外周面を駆動ローラ45の外周面に接触して配置されている。搬送路5cを矢印102b方向に搬送されてきた用紙1を中間転写ベルト44に接触させ、中間転写ベルト44上に形成されたトナー画像を用紙1の表面に転写する。
【0060】
定着手段51は、第2転写手段50の排紙トレイ53に近い側の搬送路5cに設置されている。定着手段51は、内部にニクロム線やハロゲンランプなどの加熱手段を備え、用紙1上のトナーが溶融する温度まで温度上昇させるとともに、所定圧力を加えて溶融したトナー画像を用紙1上に定着する。定着手段51の用紙排出側には、用紙1を搬送路5に沿って移動させるために、用紙を両面から挟む曲面ガイドが設けられている。
【0061】
一対の排紙ローラ52は、排紙トレイ53の開閉扉6から遠い側に軸線を回動支点7の軸線に平行させ、外周面を互いに接触させて配置されている。排紙ローラ52は、搬送されてきた用紙1を外部に排出する。
【0062】
ケース100の上部の排紙トレイ53は、排紙ローラ52から装置外部に排出された用紙1を保持する。
【0063】
図2は、実施形態1の主要部において1つの現像手段を抜き出した状態を示す断面図である。
【0064】
カラー画像を得るためには4セットの画像形成手段70が必要であるが、図2では、イエローYのみを示してある。イエローY,マゼンタM,シアンC,ブラックKに対応している4セットの画像形成手段70は、いずれも同じ構成であるので、イエローの画像形成手段70Yについてその構成を説明する。
【0065】
イエローの画像形成手段70Yは、感光体ドラム40Yと、帯電手段41Yと、露光手段42Yと、現像手段60Yと、クリーナ手段43Yと、第1転写ローラ47Yとを含んでいる。
【0066】
感光体ドラム40Yは、表面に例えばセレンや感光性の有機薄膜を塗布された円筒であり、静電潜像とトナー像とを形成する。感光体ドラム40Yは、軸線を駆動ローラ45の軸線に平行させ、中間転写ベルト44の開閉扉6に近い側の外周面にその外周面を接触させて回転する。
【0067】
帯電手段41Yは、例えば導電性のゴムローラからなり、例えば2kV程度の電圧を加えて感光体ドラム40Yの表面を所定電圧に帯電させる。
【0068】
露光手段42Yは、感光体の幅方向に1列に配置された例えばLEDアレイを含み、クリーナ手段43Yよりも感光体ドラム40Yの回転方向下流側で、照射方向を感光体ドラム40Yの外周面に向け、感光体ドラム40Yの表面に対して所定焦点距離Fだけ離して配置されている。LEDアレイは、例えば、1インチ(25.4mm)あたり600個ないし1200個配置され、感光体ドラム40Yの外周面に静電潜像を形成する。
【0069】
クリーナ手段43Yは、第1転写ローラ47Yよりも感光体ドラム40Y回転方向下流側で、軸線を感光体ドラム40Yの軸線に平行させ、かつ外周面を互いに接触させて配置されている。
【0070】
現像手段60Yは、露光手段42Yよりも感光体ドラム40Yの回転方向下流側で、感光体ドラム40Yの外周面に所定間隔をおいて感光体ドラム40Yと平行に内装した現像ローラ61Yの外周面を接触させ、黄トナー66Yを収容する。
【0071】
現像手段60Yは、図1の開閉扉6が開かれた状態で、矢印104方向に直線状に、容易に引き抜き、再装着できる。
【0072】
現像ローラ61Yは、ステンレスなどの金属を芯体とし、例えば、カーボンを加え103〜109Ω・cm程度の導電性を備えたウレタンゴムやシリコンゴムなどの導電性の弾性体膜を表面に備えている。現像ローラ61Yの表面は、感光体ドラム40と同一の矢印108方向に回転する。
【0073】
現像手段60Yは、現像ローラ61Yと平行に供給ローラ62Yを内装し、供給ローラ62Yの外周面を現像ローラ61Yの外周面に接触させてある。
【0074】
供給ローラ62Yは、その表面が例えば多孔質のスポンジゴムからなり、現像ローラ61Yに接触して同じ方向に回転し、現像ローラ61Yにトナーを供給する。
【0075】
トナー規制ブレード63Yは、固定端を現像手段60Yに固定され、自由端を現像ローラ61Yの母線に沿って現像ローラ61Yに線状に接触させた板ばねからなる。トナー規制ブレード63Yの自由端は、現像ローラ61Yの外周面に所定圧力で接触し、現像ローラ61Yの回転に伴ってその表面を摺動し、トナーを帯電させるとともに現像ローラ61Y表面に所定厚さのトナー薄層を形成する。
【0076】
トナー規制ブレード63Yは、現像ローラ61Yの軸線に直交する平面で切った断面において、固定端と現像ローラ61Yへの接触点を結ぶ直線が、中間転写ベルト44の表面に立てた法線に沿う方向に配置されている。
【0077】
前記直線は、中間転写ベルト44の表面に直交するのが理想的であり、直線と中間転写ベルト44の表面に立てた法線とのなす角は、10度以下であることが望ましい。この角が小さいほど、トナー規制ブレード63Yが占有する画像形成手段70Yの積み重ね方向の寸法が少なくて済み、画像形成手段70Yの積み重ねピッチを小さくできる。
【0078】
現像手段60Yは、黄トナー66Yを収容するトナー収容部65Yと、トナー収容部65Yの感光体ドラム40Y側に形成されて現像ローラ61Y,供給ローラ62Yを内装し、トナー規制ブレード63Yを備えた現像器先端部68Yとからなる。
【0079】
第1転写ローラ47Yは、感光体ドラム40Yと平行に設置され、中間転写ベルト44を挟んで感光体ドラム40Yと接触している。
【0080】
実施形態1のクリーナ手段43Yは、ステンレスなど金属を芯体として、表面には例えば導電性の繊維を植毛したブラシローラであり、感光体ドラム40外周面に接触し、中間転写ベルト44に転写されずに感光体ドラム40Y上に残留したトナーを除去する。
【0081】
実施形態1においては、ブラックK,マゼンタM,シアンC,イエローYのカラートナーを用いてフルカラー印刷をする4セットの画像形成手段70が、中間転写ベルト44に沿って上下に積み重ね配置されている。
【0082】
無端の中間転写ベルト44は、例えば、ポリイミドやポリカーボネートなどの導電性の材料からなり、上下方向に細長く配置されている。中間転写ベルト44は、駆動ローラ45と駆動ローラ45の下方に配置された従動ローラ45aと両者の中間に配置された張力調整ローラ46とに架け渡されており、たるまないように張力調整ローラ46によって適切な張力が加えられている。
【0083】
中間転写ベルト44は、駆動ローラ45の回転に伴って感光体ドラム40に接触する側が、矢印105の方向に所定速度で移動する。中間転写ベルト44の一面は、ブラックK,マゼンタM,シアンC,イエローYのカラートナー画像を形成する4セットの感光体ドラム40と接触している。
【0084】
各感光体ドラム40に対向する中間転写ベルト44の反対側には、各カラー感光体ドラム40K,40C,40M,40Yにそれぞれ対向して、所定電圧を加えられた第1転写ローラ47が配置されており、中間転写ベルト44を介して、各感光体ドラム40に所定圧力で接触している。
【0085】
次に、実施形態1の電子写真装置において、カラー画像を用紙上に形成する手順を説明する。4セットの画像形成手段70が、ブラックK,マゼンタM,シアンC,イエローYのカラー画像が形成する。ここでは、イエローYの画像が形成される場合を説明する。ブラックK,マゼンタM,シアンCについても、同様の手順で画像が形成される。
【0086】
帯電ローラ41Yに所定電圧を印加すると、感光体ドラム40Y表面の感光層が一様に帯電される。
【0087】
イエローの画像に対応したLED光が露光手段42Yから感光体ドラム40Yに照射され、感光層が露光される。感光体ドラム40Y表面の感光層の露光された部分は、帯電電位が接地レベルに近づくので、感光層上に見えない静電潜像が形成される。
【0088】
感光体ドラム40Y上の静電潜像に、現像ローラ61Yの表面に薄く形成されたイエロー層のトナーを付着させて現像する。
【0089】
このようにして形成されたイエロートナー像は、中間転写ベルト44の表面に転写される。
【0090】
中間転写ベルト44に転写されず感光体ドラム40Y上に残留したトナーは、クリーナ手段43Yによって除去される。
【0091】
ブラック,マゼンタ,シアンの各色についても、対応する画像形成手段70により、そのカラートナー画像が形成され、中間転写ベルト44に転写される。
【0092】
各カラー感光体ドラム40K,40M,40C,40Y上のトナー像は、中間転写ベルト44の移動速度と各感光体ドラム40の中間転写ベルト44移動方向間隔とに応じて、適切な時間差をもって形成される。これらのトナー像は、中間転写ベルト44上に転写される際に重ね合わされ、中間転写ベルト44上には、フルカラーのトナー画像が形成される。
【0093】
続いて、中間転写ベルト44上に形成されたフルカラーのトナー画像は、用紙1上に転写される。
【0094】
用紙カセット2にセットされた用紙1は、用紙分離手段3によって1枚ずつに分離され、縦搬送路5aに送出される。用紙1は、互いに向き合った一対の回転自在な搬送手段4により挟まれている。搬送手段4の少なくとも一方は、駆動ローラとなっており、用紙1を所定速度で所望の方向に移動させる。
【0095】
用紙1は、縦搬送路5a,屈曲搬送路5b,横搬送路5c内を矢印102a,102bに沿って移動する。用紙位置検出手段8が用紙1の先端を検出すると、用紙を位置決めするレジストローラ9を一旦停止させる。この状態で搬送手段4の回転を継続すると、用紙1の先端がレジストローラ9のニップ部すなわち対向したローラ同士の接触部に押し付けられ、用紙1の先端がレジストローラ9の軸と平行になる。
【0096】
レジストローラ9は、用紙1の先端と中間転写ベルト44上に形成されたトナー画像の先端位置とが所定の位置関係になるようなタイミングで、再度駆動される。第2転写手段50は、用紙1の表面を中間転写ベルト44に接触させ、中間転写ベルト44のトナー画像を用紙1上に転写させる。
【0097】
用紙1は定着手段51に送られ、転写されたトナー画像を表面に定着される。
【0098】
トナーが表面に付着した用紙1は、定着手段51によってトナーが溶融する温度まで加熱される。定着手段51の表面が温度が160℃程度であり、用紙1上のトナーは溶融温度が100℃程度なので、トナーは定着手段51を通過する際に短時間で溶融する。
【0099】
定着手段51においては、定着手段51のローラ同士またはローラとベルトとの対などの圧力により、溶融したトナーを用紙1に押し付けて密着させ、自然冷却し、定着させる。
【0100】
定着が完了した用紙1は、搬送路5を矢印106a,106b方向に搬送され、排出ローラ52により排紙トレイ53上に排出される。
【0101】
上記一連の動作を繰り返すと、カラー画像を定着した用紙が連続的に得られる。
【0102】
トナー規制ブレード63は、トナー収容部65Yのトナー規制ブレード取り付け手段64にねじなどで固定された金属製の板ばねであり、上下に張り渡された中間転写ベルト44に対してほぼ直交する方向すなわちほぼ水平方向に延びている。
【0103】
トナー規制ブレード63の先端は、現像ローラ61の上面頂点付近に所定圧力で接触しており、現像ローラ61の表面上に付着したトナーの厚さを規制し、所定電荷を帯電した所定量のトナー薄層を形成する。
【0104】
現像ローラ61の上面頂点近くで現像ローラ61の外周面に接触するトナー規制ブレード63の部分は、トナー規制ブレード63の実際の端部とは限定されない。すなわち、接触する部分は、トナー規制ブレード63の折り曲げて形成された角部または曲部であってもよい。
【0105】
トナー規制ブレード63は、現像ローラ61外周面と接触する際に、所定たわみをもつような位置関係と構造で配置されており、現像ローラ61に回転上流側からfollowing方向にすなわち現像ローラの表面移動方向と同方向から接触するように配置されている。
【0106】
トナー収容部65は、トナー66を攪拌し供給ローラ62から現像ローラ61にトナーを供給するトナー攪拌手段67を備えている。
【0107】
トナー66が消耗した現像手段60は、全体を矢印104方向にほぼ直線的に引き抜いて、新しい現像手段60を再装着できるようになっている。
【0108】
装置全体の寸法を小さくするためには、感光体ドラム40,帯電手段41,露光手段42,現像手段60,クリーナ手段43を備えた画像形成手段70を高密度に実装する必要がある。すなわち、複数の感光体ドラム40相互間の感光体ピッチをできるだけ小さくしするとともに、画像形成手段70を構成する感光体ドラム40,帯電手段41,露光手段42,現像手段60,クリーナ手段43同士が互いに干渉しないよう配置しなければならない。
【0109】
一方、装置が小型であったとしても、トナー収納部65に充填されたトナー66の量はできるだけ多い方が望ましい。
【0110】
画像形成装置を小型化するには、各カラートナーに対応した画像形成手段70を重ね合わせる際のピッチすなわち間隔をできるだけ狭くする必要がある。
【0111】
現像手段60における現像ローラ61近傍の現像器先端部68と露光手段42とは、高さ方向に重なる。
【0112】
露光手段42のLEDアレイなどの先端にトナーが付着すると露光不良となって画像に白すじが生じ、画像が劣化する。したがって、露光手段42内のLEDアレイは光軸を水平か、水平より下向きに配置することが望ましい。
【0113】
図2の実施形態1では、LEDアレイは、光軸が水平より約3°から5°下向きになるように配置されている。なお、この光軸の角度は、図2の実施形態に限定されず、例えば現像器と干渉しない範囲で、更に傾斜させてもよい。
【0114】
次に、媒体両面に印刷する機構について説明する。
【0115】
バイパス搬送路56は、定着手段の下流側の第1分岐手段58において、排紙搬送路55の途中に設けられた切り替え手段11により、主搬送路5から分岐し、反転搬送路54まで用紙を搬送する。切り替え手段11は、図示しないアクチュエータにより、用紙1の搬送路を排紙搬送路55とバイパス搬送路56とのいずれかに切り替える。
【0116】
定着手段51で表側のカラー画像を定着された用紙1は、裏側を印刷するためにバイパス搬送路56を通り、戻り搬送ローラ4cにより挟まれて、矢印107方向に搬送される。
【0117】
バイパス搬送路56を搬送された用紙は、反転搬送路54に挿入され、後端が先端となるように搬送方向を転換される。
【0118】
バイパス搬送路56を搬送された用紙は、第2分岐手段59により戻り搬送路57を矢印108方向に搬送され、横搬送路5cを通り、第2転写手段50を通過する際に裏側にフルカラー画像を転写され、定着手段51によりトナーを定着され、排紙搬送路55から排紙トレイ53上に排紙される。
【0119】
開閉扉6は、用紙カセット2から1枚ずつ分離された用紙1を搬送する主搬送路5の一部である縦搬送路5aと、用紙1をスイッチバックする反転搬送路54とだけを2層に内蔵している。
【0120】
反転搬送路54が、上下すなわち重力方向に配置されているので、反転される用紙1は、その上端のみを搬送ローラ4cにより挟まれていればよい。
【0121】
本発明においては、反転搬送路54に送出されまたは反転搬送路54から取り出される用紙1を搬送する搬送ローラ4cを開閉扉6内部には設けずに、装置本体だけに設けた。 したがって、搬送ローラ4cを駆動する動力を伝達する動力伝達手段を開閉扉6内部に形成した搬送ローラのために別途設ける必要がないので、反転搬送路54は用紙を1枚収納できるだけの単なるスリット形状でよく、構成が簡素になるとともに、開閉扉6を薄くできる。
【0122】
このように、開閉扉6の内側には、用紙カセット2から給紙手段3によって1枚ずつに分離された用紙1を下方から上方に搬送する縦搬送路5aと反転搬送路54だけを2層に設けており、さらに、反転搬送路54を反転搬送される用紙1を搬送する搬送ローラを開閉扉6の内側には設けていないので、開閉扉6の厚さThを薄くできる。
【0123】
その結果、電子写真装置の図1における左右方向の寸法Wを短縮し、電子写真装置の設置面積を削減し、小型化を実現できる。
【0124】
図3は、実施形態1において開閉扉を開放し、現像手段を交換する状況を示す図である。 実施形態1において、回転支点7を中心に開閉扉6を矢印101方向に開放すると、現像手段60を矢印104方向に取り出し、容易にメンテナンスまたは交換できる。
【0125】
図4は、実施形態1において主搬送路5内で用紙ジャムが生じた場合に用紙ジャムを解消する状況を示す図である。
【0126】
図3の機構に開閉扉内の縦搬送路部5aを開放する構造を追加すると、主搬送路5内で用紙ジャム1jが生じた場合でも、ジャムを容易に解除できる。
【0127】
次に、両面印刷時に用いるバイパス搬送路の構成について説明する。
【0128】
図5は、実施形態1においてケース上部を開いた状態を示す図である。
【0129】
ケース上部200は、屈曲搬送路5b,横搬送路5cの少なくとも上面と、バイパス搬送路56および戻り搬送路57とを含んでおり、矢印122方向に回動させると、ケース100の上面を開放できる。
【0130】
ケース上部200を開放すれば、屈曲搬送路5b,横搬送路5cが露出するので、屈曲搬送路5b,横搬送路5c内部で用紙ジャムなどが発生した場合にも、容易に取り除くことができる。
【0131】
CYMK各色の画像を形成する感光体ドラム40K,40C,40M,40Yと、帯電ローラ41K,41C,41M,41Yと、クリーナ手段43K,43C,43M,43Yとが、中間転写ベルト44に沿って上下方向に所定の間隔で配置されている。それらは、ケース100とは別の感光体ユニット121として、一体構造とすることもできる。
【0132】
このような構造にすれば、感光体ユニット121を矢印123方向に一体として引き抜くことができるので、感光体40が劣化したり傷が付いたりして交換する場合の操作が容易となり、保守しやすくなる。
【0133】
図6は、実施形態1においてバイパス搬送路内を開放している状況を示す図である。
【0134】
バイパス搬送路56において用紙ジャムなどが発生した場合には、バイパス搬送路56より下部を矢印124方向に回動させてバイパス搬送路56を開放できるので、用紙ジャムなどを容易に取り除くことができる。
【0135】
図7は、実施形態1において手差し給紙する状況を示す図である。
【0136】
用紙カセット2にセットしてある印刷用紙1とは異なる例えば厚紙やOHPフィルムなどの特殊紙を手差しの用紙トレイ73から挿入する状況を示している。
【0137】
厚紙などの特殊紙は、剛性が高いために曲率の高い搬送路を通すことができない場合がある。その場合は、搬送路ができるだけ直線に近い形態が望ましい。
【0138】
本発明においては、手差しトレイ73をほぼ戻り搬送路57の延長線上に設けてある。
【0139】
また、給紙手段3aを設けると、手差し用紙1aを1枚ずつに分離して印刷できる。
【0140】
さらに、定着手段51から排出される用紙1をガイドする定着手段後ガイド125を支点126の周りに回動可能にし、定着手段51から排出される厚紙などの特殊紙を矢印106c方向に排出できるようにした。厚紙などの特殊紙は、搬送ローラ4eによってケース100外部の矢印106d方向に排出され、排紙トレイ74上に集積される。
【0141】
図7の構成によれば、手差しトレイ73に供給された用紙1aは、給紙手段3aにより1枚ずつに分離され、戻り搬送路57,横搬送路5cを矢印102bに沿って搬送され、レジストローラ9を経由し、第2転写手段50においてトナー画像を転写され、定着手段51でトナー画像を定着してから排出される。
【0142】
実施形態1の構成によれば、手差しトレイ73から排紙トレイ74に至るまでの搬送経路で曲率の大きな部分や屈曲部を少なくできる。
【0143】
このように直線的な搬送経路を実現できるので、厚紙などの剛性の高い用紙1も使用可能である。
【0144】
次に、再び図1を参照して、両面印刷動作について説明する。
【0145】
両面印刷する場合は、表側のトナー画像の転写,定着が完了した用紙1を、主搬送路5の第1分岐手段58に備えられた切り替え手段11により切り換える。用紙1は、バイパス搬送路56を矢印107の方向に搬送され、反転搬送路54に一旦収納される。
【0146】
用紙1の後端がバイパス搬送路56に備えられた第2分岐手段を通り過ぎて用紙の全体が反転搬送路に収納されると、搬送ローラ4cを逆転させて、用紙を矢印108方向に、逆方向に搬送する。
【0147】
用紙1の先端が、第2分岐手段において戻り搬送路57に進入し、矢印108方向に進行して横搬送路5に導かれ、更に矢印102b方向に進行し、第2転写手段50において予め中間転写手段に形成されたフルカラーのトナー画像を裏面側に転写され、定着手段51でトナー画像を定着され、裏側の画像が形成され、両面印刷が完了する。
【0148】
図8は、従来の両面印刷の際の印刷順序および用紙間ギャップの一例を示す図である。
【0149】
上記手順を1枚ごとに繰り返すと、印刷順序は1枚目の表,1枚目の裏,2枚目の表,2枚目の裏,……となる。
【0150】
このような印刷順序の場合は、1枚目の表が印刷完了してから1枚目の裏側を印刷開始するまでに待ち時間が生じて毎分当たりの印刷速度が片面印刷の場合よりも遅くなる。
【0151】
すなわち、図1において、表側の印刷が完了し、用紙の後端が定着手段51から離脱した後、バイパス搬送路56を搬送されて用紙の後端が第2分岐手段59を通過し、用紙1全体が反転搬送路54に収納され、逆に矢印102a方向に搬送され、用紙先端が第2転写手段50に到達するまでの間は、現像手段60,感光体40,中間転写ベルト44とを備えた画像形成手段は、いわば「待ち」の状態になって裏側を印刷するまでの時間間隔が開くので、毎分当たりの印刷速度は低下する。
【0152】
1枚目の裏側の印刷が完了してから2枚目の表側の印刷を開始するまでは、1枚目裏側の後端が戻り搬送路57から横搬送路5に搬送されるタイミングに合わせて、所定の用紙間隔Gapを確保できるように、2枚目の用紙を供給手段3によってピックアップできるので、1枚目と2枚目との用紙間隔Gapは、片面印刷の場合と同等にすることができ、印刷速度は低下しない。
【0153】
1枚目の用紙1の後端が定着手段51を通過してバイパス搬送路56を経由し、更に反転搬送路54に一旦収納され、搬送方向を反転して戻り搬送路57を通り、第2転写手段50に到達するまでは、用紙1を第2転写手段50による転写搬送速度よりも高速で搬送できるので、待ち時間となる反転時間を短縮できる。
【0154】
しかし、印刷速度を片面印刷の場合と全く同等にすることはできない。すなわち、1枚目の表側の印刷が完了してから裏側の印刷を開始するまでの用紙間隔は、用紙の反転に要する時間とその間の平均速度Vaveとの積となる。この積は、連続的に用紙1が用紙カセットから給紙された場合の用紙間の間隔Gapより大きくなる。
【0155】
図9は、本発明による両面印刷の際の印刷順序および用紙間ギャップ一例を示す図である。
【0156】
両面印刷の印刷速度を片面印刷の場合と同等にするには、1枚目の表側を印刷してから1枚目の裏側を印刷するために用紙1を反転搬送路54に搬送している間に、2枚目の用紙1をピックアップしておいて、1枚目の表側の印刷が完了したら、2枚目の表側を印刷し、その間に1枚目を反転しておき、1枚目の裏側を印刷して排紙し、その間に2枚目を反転搬送路に待避するという印刷順序を繰り返す手順が望ましい。
【0157】
【実施形態2】
図10は、図9のような印刷順序を実現するための記録媒体搬送経路の実施形態を示す図である。
【0158】
バイパス搬送路56上の第2分岐手段59から横搬送路5cの第2転写手段50,定着手段51,第1分岐手段58,バイパス搬送路56を経由して再び第2分岐手段59に至るまでの長さをL1とし、第2分岐手段59から用紙カセット2の近傍に至るまでの反転搬送路54の長さをL2とする。
【0159】
反転搬送路54には最大長さの用紙1を収納しなければならないので、用紙の最大長さをPmaxとすると、
L2>Pmax
の関係を満たす必要がある。
【0160】
次に、図9に示した印刷順序を実現するには、図10に示すように、用紙同士の間隔をGapとして、
L1>(2×Pmax+Gap)
にすることが望ましい。
【0161】
搬送路長さL1をこのように規定すると、反転搬送路54から戻り搬送路57を経由して横搬送路5cを通り裏側を印刷する1枚目の後端と、表側の印刷が終了してバイパス搬送路56から反転搬送路54に入る2枚目の用紙先端とが衝突しないので、ジャムなどの発生を抑止して、安定な用紙搬送を実現できる。
【0162】
反転搬送路54内で用紙1を挟み搬送する搬送ローラ4cは、待避していた1枚目を送出する際には時計方向に回転し、1枚目を送出し終わったことを用紙検出手段120で検出したら、反時計方向に回転し、バイパス搬送路56から搬送される2枚目の用紙を反転搬送路54内に送り込む。
【0163】
【実施形態3】
図11は、バイパス搬送路56上の第2分岐手段59から横搬送路5の第2転写手段50,定着手段51,第1分岐手段58,バイパス搬送路56を経由して再び第2分岐手段59に至るまでの長さをL1を、図10の実施形態よりも短くした実施形態を示す図である。
【0164】
図12は、図11の用紙1aとその次の用紙1bとが、重なり合ってすれ違う状況を示す図である。
【0165】
実施形態3においては、第2分岐手段59から戻り搬送路57とバイパス搬送路56とを経由する搬送路長さL1は、
L1<(2×Pmax+Gap)
となる。
【0166】
表側の印刷が既に完了していて次に裏側を印刷するために反転搬送路54から送出され戻り搬送路57に搬送される用紙1aと、その次の用紙1bとは、第2分岐手段59から反転搬送路54に至るまでの搬送路の一部において、重なってすれ違う。
【0167】
図11においては、表側を印刷している用紙1bの先端が第2分岐手段59に到達しようとしている時点で、裏面を印刷するために反転搬送路54から送出される用紙1aの後端は、まだ反転搬送路内にある。
【0168】
図12に示す通り、用紙1bの先端が第2分岐手段59を通過してから、用紙1aの後端が第2分岐手段59を通過して戻り搬送路57に進入するまでの間は、用紙1aと用紙1bとは、搬送路内ですれ違う。
【0169】
この用紙すれ違い範囲の長さL3は、第2分岐手段59から
L3=(2×Pmax+Gap−L1)
として表される。
【0170】
この用紙すれ違い範囲においては、2枚の用紙が重なって互いに逆方向に搬送される。この範囲に搬送ローラ4cを設けると、用紙すれ違いができなくなる。そこで、用紙を挟む搬送ローラ4cの挟み込みを開放する構成などが必要となる。 これに対して、本発明では、用紙すれ違い範囲L3には、搬送ローラ4cを設けていないので、搬送ローラの開放機構が不要となり、用紙のすれ違いを簡素な構成で実現できる。
【0171】
【実施形態4】
図13は、第2分岐手段59からの戻り搬送路57aをS字形状とした実施形態を示す図である。
【0172】
実施形態4においては、戻り搬送路57を屈曲させてS字形状として、図10の実施形態と同様に、
L1>(2×Pmax+Gap)
の長さを確保できるので、表側を転写・定着してからバイパス搬送路56を経由し反転搬送路54に進入する用紙1bと、反転搬送路から先端と後端とを反転し送出され戻り搬送路57から横搬送路5cに進入し裏側を転写・定着される用紙1aとが、第2分岐手段59では接することなく、それぞれの搬送方向に進行できる。
【0173】
このような構成を採用すると、
L1>(2×Pmax+Gap)
L2>Pmax
という搬送路長さL1,L2を確保し、しかも、図10の実施形態よりも装置を小型化できる。
【0174】
この場合、戻り搬送路57の上下方向の寸法Hrは大きくなる。しかし、電子写真装置の高さHが高くなるだけで、電子写真装置の設置面積を増やす要因にはならず、幅Wを削減できるので、装置の小型化には有効である。
【0175】
次に、図14〜図18を参照して、第2分岐手段59に関する実施形態を説明する。
【0176】
【実施形態5】
図14は、本発明による両面印刷機能を備えた電子写真装置の第2分岐手段の実施形態を示す図である。
【0177】
バイパス搬送路56を矢印107方向に搬送される用紙1は、第2分岐手段59の上流側から反転搬送路54に進入する。搬送ローラ4cは反時計方向110aに回転して、用紙1を反転搬送路54内で矢印109a方向に送り込む。
【0178】
用紙検出手段120は、例えば投光素子と受光素子との対からなる光透過形の検出手段であり、搬送路の用紙の有無を検出する。光の透過と遮断とを検出すると、搬送路を搬送される用紙1の先端または後端の通過タイミングを検出できる。
【0179】
図15は、図14の第2分岐手段において、用紙検出手段120が遮光から透過への変化を検出した瞬間の状態を示す図である。
【0180】
用紙検出手段120は、用紙1の搬送中は遮光されている。用紙検出手段120が、遮光から透過への変化を検出すると、搬送される用紙1の後端が検出手段の位置を通過したと判定できるので、その時点でまたは所定時間/所定距離だけ用紙を更に搬送してから、搬送ローラ4を停止させる。
【0181】
図16は、図14の第2分岐手段において、反転搬送路54から戻り搬送路57を介して横搬送路5cに用紙1を戻している状態を示す図である。
【0182】
搬送ローラ4cを時計方向110bに回転させると、反転搬送路54に収納された用紙1は、それまでの後端を先端として、矢印109b方向に搬送される。
【0183】
バイパス搬送路56と反転搬送路54との間には段差Dが形成されているので、用紙1の先端は、この段差部Dにより、戻り搬送路57で矢印108方向に導かれて搬送される。
【0184】
戻り搬送路57を搬送された用紙1は横搬送路5cに進入し、図1に示すように、第2転写手段50により裏側にトナー画像を転写され、定着手段51により画像を定着され、排紙搬送路55を矢印106a方向に搬送され、排紙トレイ53上に排紙される。
【0185】
【実施形態6】
図17は、本発明による両面印刷機能を備えた電子写真装置の第2分岐手段の実施形態を示す図である。
【0186】
本実施形態は、回転中心115の周りに回転自在な分岐補助部材116を備えている。
【0187】
バイパス搬送路56を矢印107方向に用紙1が搬送されると、用紙1の先端が、用紙の弾力により、分岐補助部材116を重力による自由落下位置Bから位置Aまで回動させる。用紙1の先端が反転搬送路54に進入すると、搬送ローラ4cは、反時計方向110aに回転し、用紙1を反転搬送路54内部に搬送する。
【0188】
用紙1の後端が反転搬送路54に進入してしまうと、分岐補助部材116は、重力により、自由落下位置Bに復帰する。
【0189】
図18は、図17の第2分岐手段において、反転搬送路54から戻り搬送路57を介して主搬送路5に用紙1を戻している状態を示す図である。
【0190】
搬送ローラ4を時計方向110bに回転させると、反転搬送路54に収納された用紙1は、それまでの後端を先端として、矢印109b方向に搬送され、反転搬送路54から送出される。用紙1の先端が、分岐補助部材116に接触すると、進行方向を戻り搬送路57の方向に変えられ、矢印108方向に搬送される。
【0191】
本実施形態においては、分岐補助部材116により、用紙1の先端が戻り搬送路57に案内されるので、用紙反転の動作がより確実になる。
【0192】
戻り搬送路57を搬送された用紙1は横搬送路5cに進入し、図1に示すように、第2転写手段50により裏側にトナー画像を転写され、定着手段51により画像を定着され、排紙搬送路55を矢印106a方向に搬送され、排紙トレイ53上に排紙される。
【0193】
【発明の効果】
本発明によれば、両面印刷をするために表側の印刷が終了した用紙を反転するためのバイパス搬送路を、ケース底面にある用紙カセットから1枚ずつに分離されて搬送され、転写手段によってトナー画像を転写されてから定着手段によって画像を用紙に定着されるまでの主搬送路にほぼ並列に備えたので、定着手段から排出された直後に方向をほぼ180°転換する曲面ガイドが必要であるが、バイパス搬送路,反転搬送路,戻り搬送路とも屈曲部が少なく、搬送距離が短く小型化に適した記録媒体供給経路を実現できる。
【0194】
また、トナーや現像手段を交換するための開閉扉の内部には、反転搬送路と主搬送路との2層だけを設けたので、開閉扉を薄くして装置を小型化できる。
【0195】
さらに、ケース上部を開閉自在とし、その内部にバイパス搬送路と戻り搬送路とを設けたので、用紙ジャムの解除が容易であり、感光体ドラムユニットの交換に際しても、上方に引き抜くことができるので、メンテナンスが容易になる。
【0196】
したがって、両面印刷機能を備え両面印刷時にも高速に印刷できる小型の電子写真装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による両面印刷機能を備えた電子写真装置の実施形態1の全体構成を示す断面図である。
【図2】実施形態1の主要部において1つの現像手段を抜き出して示す断面図である。
【図3】実施形態1において開閉扉を開放し、現像手段を交換する状況を示す図である。
【図4】実施形態1において主搬送路内で用紙ジャムが生じた場合に用紙ジャムを解消する状況を示す図である。
【図5】実施形態1においてケース上部を開いた状態を示す図である。
【図6】実施形態1においてバイパス搬送路内を開放している状況を示す図である。
【図7】実施形態1において手差し給紙する状況を示す図である。
【図8】従来の両面印刷の際の印刷順序および用紙間ギャップの一例を示す図である。
【図9】本発明による両面印刷の際の印刷順序のおよび用紙間ギャップ一例を示す図である。
【図10】図9のような印刷順序を実現するための記録媒体搬送経路の実施形態を示す図である。
【図11】図9のような印刷順序を実現するための記録媒体搬送経路の実施形態を示す図である。
【図12】図11の用紙1aとその次の用紙1bとが、重なり合ってすれ違う状況を示す図である。
【図13】第2分岐手段59からの戻り搬送路57aをS字形状とした実施形態を示す図である。
【図14】本発明による両面印刷機能を備えた電子写真装置の第2分岐手段の実施形態を示す図である。
【図15】図14の第2分岐手段において、用紙検出手段120が遮光から透過への変化を検出した瞬間の状態を示す図である。
【図16】図14の第2分岐手段において、反転搬送路54から戻り搬送路57を介して主搬送路5に用紙1を戻している状態を示す図である。
【図17】本発明による両面印刷機能を備えた電子写真装置の第2分岐手段の実施形態を示す図である。
【図18】図17の第2分岐手段において、反転搬送路54から戻り搬送路57を介して主搬送路5に用紙1を戻している状態を示す図である。
【符号の説明】
1 用紙(記録媒体)
2 用紙カセット
3 用紙分離手段
4 搬送手段
5 用紙搬送路
5a 縦搬送路
5b 屈曲搬送路
5c 横搬送路
6 開閉扉
7 回動支点
8 用紙位置検出手段
9 レジストローラ
11 切り替え手段
40 感光体ドラム
41 帯電手段
42 露光手段
43 クリーナ手段
44 中間転写ベルト
45 駆動ローラ
46 張力調整ローラ
47 第1転写ローラ
48 転写クリーニング手段
49 クリーニングブレード
50 第2転写手段
51 定着手段
52 排紙ローラ
53 排紙トレイ
54 反転搬送路
55 排紙搬送路
56 バイパス搬送路
57 戻り搬送路
58 第1分岐手段
59 第2分岐手段
60 現像手段
61 現像ローラ
62 供給ローラ
63 トナー規制ブレード
64 トナー規制ブレード取り付け手段
65 トナー収容部
66 トナー
67 攪拌手段
68 現像器先端部
70 画像形成手段
73 手差しトレイ
74 排紙トレイ
100 ケース
115 回転中心
116 分岐補助部材
120 用紙検出手段
121 感光体ユニット
200
Claims (11)
- 感光体ドラムと前記感光体ドラムの感光層に静電潜像を形成する露光手段と前記感光体ドラムの静電潜像にトナーを付着させてトナー像を形成する現像手段とを含む複数の画像形成手段と、駆動ローラと従動ローラとに張り渡されて回転する無端の中間転写ベルトと、前記感光体ドラムの列の上方に配置され前記中間転写ベルトから記録媒体にトナー像を転写する第2転写手段とを有し、前記複数の感光体ドラムに形成されたトナー像を前記中間転写ベルトを介して記録媒体に転写しカラー画像を形成する電子写真装置において、
電子写真装置本体前面に、前記現像手段を着脱するための開閉扉を有し、
該開閉扉内に設けられ且つ記録媒体を収納する用紙カセットから供給された前記記録媒体を上方に搬送する縦搬送路と、屈曲搬送路と、前記第2転写手段までほぼ水平に前記記録媒体を搬送する横搬送路とからなる記録媒体供給経路と、
前記転写手段よりも下流の前記横搬送路に配置されて転写されたトナー像を前記記録媒体上に定着させる定着手段と、
印刷が完了した記録媒体を排出して堆積する排紙トレイと、
既に片面が印刷され両面印刷する記録媒体を搬送するバイパス搬送路と、
前記両面印刷する記録媒体を前記排紙トレイへの搬送路から前記バイパス搬送路に導く第1分岐手段と、
両面印刷時に前記バイパス搬送路で搬送された前記記録媒体を反転させるスリット形状の反転搬送路と、
両面印刷時に前記反転搬送路で反転された前記記録媒体を前記バイパス搬送路から前記横搬送路に導く第2分岐手段と、
前記第2分岐手段を通過した前記記録媒体を前記横搬送路に搬送する戻り搬送路とを備え、
前記反転搬送路を前記開閉扉内の前記縦搬送路にほぼ並行させて設置し、前記反転搬送路内に挿入されまたはそこから送り出される前記記録媒体を駆動する搬送ローラを開閉扉上方の装置本体側に設けたことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項1に記載の電子写真装置において、
前記開閉扉が、前記縦搬送路に沿って開放する機構を有する
ことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項1又は2に記載の電子写真装置において、
前記屈曲搬送路および前記横搬送路に沿って開放されるケース上部を有する
ことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項3に記載の電子写真装置において、
前記ケース上部が、前記バイパス搬送路に沿って開放する機構を有する
ことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項1ないし4のいずれか一項に記載の電子写真装置において、
前記戻り搬送路のほぼ延長線上に手差し給紙トレイを設けた
ことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項1ないし5のいずれか一項に記載の電子写真装置において、
前記バイパス搬送路上の前記第2分岐手段から前記横搬送路の前記第2転写手段,前記定着手段,前記第1分岐手段,前記バイパス搬送路を経由して再び前記第2分岐手段に至るまでの長さをL1とし、前記第2分岐手段から前記用紙カセットの近傍に至るまでの反転搬送路の長さをL2とし、記録媒体の最大長さをPmaxとし、搬送される記録媒体同士の間隔をGapとして、
L1>(2×Pmax+Gap)
L2>Pmax
の関係を満たすことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項6に記載の電子写真装置において、
前記第2分岐手段からの戻り搬送路をS字形状としたことを特徴とする
ことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項1ないし5のいずれか一項に記載の電子写真装置において、
前記バイパス搬送路上の前記第2分岐手段から前記横搬送路の前記第2転写手段,前記定着手段,前記第1分岐手段,前記バイパス搬送路を経由して再び前記第2分岐手段に至るまでの長さをL1とし、前記第2分岐手段から前記用紙カセットの近傍に至るまでの反転搬送路の長さをL2とし、記録媒体の最大長さをPmaxとし、搬送される記録媒体同士の間隔をGapとして、
L1<(2×Pmax+Gap)
L2>Pmax
の関係を満たすことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項1ないし8のいずれか一項に記載の電子写真装置において、
前記第2分岐手段が、前記反転搬送路から送り出される記録媒体の先端を前記戻り搬送路に導く段差を備えた
ことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項1ないし8のいずれか一項に記載の電子写真装置において、
前記第2分岐手段が、記録媒体が前記バイパス搬送路から前記反転搬送路に送り込まれる時は、前記記録媒体により持ち上げられ、記録媒体が前記反転搬送路から前記戻り搬送路に送り込まれる時は、自重により自然落下し、前記反転搬送路から送り出される記録媒体の先端を前記戻り搬送路に導く分岐補助部材を備えた
ことを特徴とする電子写真装置。 - 請求項9または10に記載の電子写真装置において、
前記第2分岐手段から前記反転搬送路への搬送路における記録媒体の有無を検出し前記反転搬送路に関連する用紙駆動機構の動作タイミングを規定する用紙検出手段を設けた
ことを特徴とする電子写真装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2003204997A JP4482297B2 (ja) | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 電子写真装置 |
| US10/730,112 US6895211B2 (en) | 2003-07-31 | 2003-12-09 | Electrophotographic apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2003204997A JP4482297B2 (ja) | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 電子写真装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2005049543A JP2005049543A (ja) | 2005-02-24 |
| JP4482297B2 true JP4482297B2 (ja) | 2010-06-16 |
Family
ID=34100689
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2003204997A Expired - Fee Related JP4482297B2 (ja) | 2003-07-31 | 2003-07-31 | 電子写真装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6895211B2 (ja) |
| JP (1) | JP4482297B2 (ja) |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4482296B2 (ja) * | 2002-10-31 | 2010-06-16 | 株式会社リコー | 電子写真装置 |
| JP2004206070A (ja) * | 2002-10-31 | 2004-07-22 | Hitachi Ltd | 電子写真装置 |
| JP4417281B2 (ja) * | 2005-03-18 | 2010-02-17 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP4750506B2 (ja) * | 2005-08-11 | 2011-08-17 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP4994768B2 (ja) * | 2005-12-09 | 2012-08-08 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP4479693B2 (ja) | 2006-06-02 | 2010-06-09 | 富士ゼロックス株式会社 | 粉体供給器、粉体供給器の製造方法、及び粉体供給器の再生方法 |
| JP4424330B2 (ja) | 2006-06-02 | 2010-03-03 | 富士ゼロックス株式会社 | 粉体供給器、粉体供給器への粉体充填量の設定方法、及び再生した粉体供給器への粉体充填量の設定方法 |
| KR101273593B1 (ko) * | 2007-02-01 | 2013-06-11 | 삼성전자주식회사 | 화상형성장치와 인쇄매체 이송방법 |
| KR101460537B1 (ko) * | 2007-02-01 | 2014-11-12 | 삼성전자 주식회사 | 화상형성장치 및 그 제어방법 |
| JP5366428B2 (ja) * | 2007-07-23 | 2013-12-11 | 理想科学工業株式会社 | 両面印刷装置 |
| JP4618306B2 (ja) * | 2008-03-05 | 2011-01-26 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP4951562B2 (ja) * | 2008-03-24 | 2012-06-13 | 京セラミタ株式会社 | 原稿搬送装置及びこれを搭載した画像形成装置 |
| JP4951563B2 (ja) * | 2008-03-24 | 2012-06-13 | 京セラミタ株式会社 | 原稿搬送装置及びこれを搭載した画像形成装置 |
| JP2010038990A (ja) * | 2008-07-31 | 2010-02-18 | Ricoh Co Ltd | 現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |
| JP5473393B2 (ja) * | 2009-05-07 | 2014-04-16 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP5429212B2 (ja) * | 2010-04-28 | 2014-02-26 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP6051686B2 (ja) | 2012-08-29 | 2016-12-27 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP6819852B2 (ja) * | 2016-06-30 | 2021-01-27 | セイコーエプソン株式会社 | 媒体排出装置、画像読取装置 |
| JP6624398B2 (ja) * | 2018-06-13 | 2019-12-25 | セイコーエプソン株式会社 | 記録装置 |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06208266A (ja) | 1993-01-11 | 1994-07-26 | Toray Ind Inc | 記録媒体搬送装置、記録媒体搬送方法および電子写真プリンタ |
| JPH08137179A (ja) | 1994-11-04 | 1996-05-31 | Minolta Co Ltd | フルカラー画像形成装置 |
| US6078760A (en) * | 1997-07-14 | 2000-06-20 | Seiko Epson Corporation | Image forming apparatus having an inverse and re-fixing sub-mode |
| US5839016A (en) * | 1997-11-24 | 1998-11-17 | Xerox Corporation | Fused image sensing |
| JP3371781B2 (ja) * | 1997-11-28 | 2003-01-27 | 日本電気株式会社 | 画像形成装置及び画像形成方法 |
| JPH11322138A (ja) * | 1998-05-15 | 1999-11-24 | Mita Ind Co Ltd | 画像形成装置 |
| KR100342983B1 (ko) * | 1999-01-13 | 2002-07-05 | 이토가 미찌야 | 양면 유닛 및 화상 형성 장치 |
| JP3668052B2 (ja) | 1999-06-21 | 2005-07-06 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |
| US6798430B2 (en) * | 2000-06-14 | 2004-09-28 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Tandem type color image forming device having a plurality of process cartridges arrayed in running direction of intermediate image transfer member |
| JP2001356548A (ja) | 2000-06-14 | 2001-12-26 | Brother Ind Ltd | カラー画像形成装置 |
| US6484003B2 (en) * | 2000-06-21 | 2002-11-19 | Konica Corporation | Color image forming apparatus with rack having detachable units |
| EP1826626B1 (en) * | 2000-09-27 | 2012-12-05 | Ricoh Company, Ltd. | Apparatuses for color image formation, tandem color image formation and image formation |
| JP3758029B2 (ja) * | 2001-06-18 | 2006-03-22 | 富士ゼロックス株式会社 | 画像形成装置及びこれに用いられる定着ユニット |
-
2003
- 2003-07-31 JP JP2003204997A patent/JP4482297B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2003-12-09 US US10/730,112 patent/US6895211B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20050025544A1 (en) | 2005-02-03 |
| US6895211B2 (en) | 2005-05-17 |
| JP2005049543A (ja) | 2005-02-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4482297B2 (ja) | 電子写真装置 | |
| US6757516B2 (en) | Carrying apparatus and image forming apparatus | |
| JP4482296B2 (ja) | 電子写真装置 | |
| JP2010039191A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2004206070A (ja) | 電子写真装置 | |
| US7634219B2 (en) | Transfer media transport guide mechanism for image forming device | |
| JP3877367B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2010001156A (ja) | 記録媒体反転装置及び画像形成装置 | |
| JP2009051579A (ja) | 記録媒体搬送経路構造および画像形成装置 | |
| US11964843B2 (en) | Transport device and image forming apparatus | |
| JP4810232B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP3578980B2 (ja) | 転写材分離機構、及びこれを備えた画像形成装置 | |
| US20230312280A1 (en) | Sheet transport device and image forming apparatus | |
| JP3587566B2 (ja) | カラー電子写真装置 | |
| JP3583104B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2004010220A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP4340524B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP4079744B2 (ja) | 同時両面画像形成装置 | |
| JP4545817B2 (ja) | 電子写真装置 | |
| JP6601050B2 (ja) | シート搬送装置及び画像形成装置 | |
| JP2005189607A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP3881820B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2004157448A (ja) | カラー画像形成装置 | |
| JP5762366B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP4496071B2 (ja) | 記録紙搬送装置及び画像形成装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20060705 |
|
| A711 | Notification of change in applicant |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20060728 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20060728 |
|
| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20080826 |
|
| A711 | Notification of change in applicant |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20081028 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090804 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090925 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20091110 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20091119 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100309 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100319 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130326 Year of fee payment: 3 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140326 Year of fee payment: 4 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |