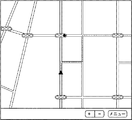以下、本発明による情報通信システムについて、実施の形態を用いて説明する。なお、以下の実施の形態において、同じ符号を付した構成要素及びステップは同一または相当するものであり、再度の説明を省略することがある。
(実施の形態1)
本発明の実施の形態1による情報通信システムについて、図面を参照しながら説明する。本実施の形態による情報通信システムは、第1の車載装置で得られた信号機の点灯色を、第2の車載装置に送信するものである。
図1は、本実施の形態による情報通信システム100の構成を示すブロック図である。本実施の形態による情報通信システム100は、互いに通信可能な、第1の車載装置1と、複数の第2の車載装置2とを備える。第1及び第2の車載装置1,2は、車両に設置される装置であり、例えば、ナビゲーション装置や、PND(Portable Navigation Device)、PDA、PC等であってもよい。その車両は、道路を通行する移動体であって、信号機の点灯色に応じて進行したり、停止したりするものであり、例えば、乗用車やバス、トラック等の自動車であってもよく、オートバイ等であってもよい。本実施の形態では、第1及び第2の車載装置1,2が、カーナビゲーション装置である場合について主に説明する。以下、第1の車載装置1の設置される車両を第1の車両と呼び、第2の車載装置2の設置される車両を第2の車両と呼ぶことがある。また、図1では、第1の車載装置1が1個存在し、第2の車載装置2が2個存在する場合について示しているが、これは一例であって、本実施の形態による情報通信システム100が有する第1及び第2の車載装置1,2の個数は問わない。例えば、第1の車載装置1が2個以上存在してもよく、第2の車載装置2が1個または、3個以上存在してもよい。なお、第1及び第2の車載装置1,2は、多数存在していることが好適である。
図2は、本実施の形態による第1の車載装置1の構成を示すブロック図である。本実施の形態による第1の車載装置1は、地図情報記憶部11と、現在位置取得部12と、点灯色取得部13と、信号機識別子取得部14と、送信部15とを備える。
地図情報記憶部11には、地図に関する情報である地図情報が記憶される。なお、その地図は、信号機の位置を含んでいる。したがって、この地図情報によって、ある位置、例えば、ある交差点等に信号機があるかどうかが分かるようになっているものとする。地図に位置が含まれる信号機を識別する信号機識別子も、この地図情報に含まれていてもよく、あるいは、含まれていなくてもよい。その地図情報は、例えば、地図の画像情報であってもよい。この画像情報は、例えば、ラスタデータ(ビットマップデータ)であってもよく、ベクタデータであってもよい。また、画像情報がラスタデータである場合には、地図情報に、複数の縮尺に対応した画像情報が含まれていてもよい。例えば、同じ地域について、縮尺の大きい画像情報、縮尺の中ぐらいの画像情報、縮尺の小さい画像情報が地図情報に含まれていてもよい。また、地図情報は、タイル状に分割された地図を示すものであり、それらを適宜組み合わせることによって、様々な領域の地図を表示することができるようになっていてもよい。ここで、「地図」は、地形図や、地勢図、地質図、土地利用図、住宅地図、路線図、道路地図、ガイドマップ等であってもよい。第1の車載装置1がカーナビゲーション装置である場合には、この地図情報は道路地図であってもよい。また、その地図情報は、経路探索を行うことができるものであってもよい。すなわち、地図情報は、例えば、道路の位置を示すものであってもよい。また、その地図情報は、道路の属性(例えば、制限速度や、主要な道路であるのか、脇道であるのかなど)を知ることができるようになっているものであってもよい。また、例えば、この地図情報は、カーナビゲーションで用いられるKIWIフォーマットのものであってもよい。また、「地図」は、地形や道路等が把握可能な航空写真や衛星写真、それらに記号や文字等が記入されたものなどであってもよい。地図情報において、地図の各地点と、座標(位置)との対応を知ることができるようになっているものとする。座標とは、ある基準点を原点とした座標(この座標は、例えば、距離でもよい)であってもよく、緯度・経度であってもよく、その他の位置を識別できる情報であってもよい。このことは、後述する他の座標についても同様であるとする。地図情報に、その座標そのものが含まれていてもよい。本実施の形態では、座標が緯度・経度である場合について説明する。また、この地図情報には、地名や、山や川などの地形に関する文字情報が含まれていてもよい。また、この地図情報において、北などの特定の方位がどちらであるのかが設定されていてもよい。なお、地図情報は、2次元のオンライン地図や電子地図等として公知であり、その詳細な説明を省略する。
地図情報記憶部11に地図情報が記憶される過程は問わない。例えば、記録媒体を介して地図情報が地図情報記憶部11で記憶されるようになってもよく、通信回線等を介して送信された地図情報が地図情報記憶部11で記憶されるようになってもよく、あるいは、入力デバイスを介して入力された地図情報が地図情報記憶部11で記憶されるようになってもよい。地図情報記憶部11での記憶は、RAM等における一時的な記憶でもよく、あるいは、長期的な記憶でもよい。地図情報記憶部11は、所定の記録媒体(例えば、半導体メモリや磁気ディスク、光ディスクなど)によって実現されうる。
現在位置取得部12は、第1の車載装置1の現在位置を取得する。その現在位置の取得は、例えば、GPS(Global Positioning System)を用いてなされてもよく、ジャイロなどの自律航法装置を用いてなされてもよく、その両方を用いることによって互いの欠点を補うようにしてもよい。なお、現在位置の取得方法は、これらに限定されないことは言うまでもない。例えば、携帯電話の最寄りの基地局を利用した現在位置の取得等を行ってもよい。また、現在位置取得部12が取得する現在位置は、例えば、緯度と経度を示す座標であってもよく、その他の座標であってもよい。また、現在位置取得部12は、第1の車載装置1の向き(方向)を含む現在位置を取得してもよい。その方向は、例えば、北を0度として、時計回りに測定された方位角によって示されてもよく、その他の方向を示す情報によって示されてもよい。第1の車載装置1がカーナビゲーション装置である場合には、その第1の車載装置1の向きは、例えば、進行方向、すなわち、第1の車載装置1が設置された車両の前方の向きであってもよい。現在位置取得部12は、第1の車載装置1の向きを取得するために、電子コンパスや地磁気センサーを備えていてもよい。現在位置取得部12が取得した現在位置は、図示しない記録媒体で記憶されてもよい。また、現在位置取得部12は、GPS等やジャイロ等を有していてもよく、あるいは、GPS等やジャイロ等から現在位置を受け取るものであってもよい。
点灯色取得部13は、信号機の点灯色を取得する。なお、その信号機は、車両の進行・停止を指示する交通信号機のことである。また、信号機の点灯色は、例えば、進行に応じた点灯色や、停止に応じた点灯色がある。なお、点灯色に、停止に応じた点灯色になる直前の点灯色があってもよい。本実施の形態では、進行に応じた点灯色を「青」とし、停止に応じた点灯色を「赤」とする。また、停止に応じた点灯色になる直前の点灯色を「黄」とすることもある。なお、点灯色を取得する方法については後述する。また、点灯色取得部13は、点灯色を取得した時点の時刻を、図示しない時計部から取得してもよい。その時刻には、年月日が含まれていてもよく、あるいは、含まれていなくてもよい。また、その時刻は、分秒を示すものであってもよく、あるいは、時分秒を示すものであってもよい。これらの時刻に関することは、後述する他の時刻についても同様であるとする。また、点灯色取得部13が取得した点灯色や時刻は、図示しない記録媒体で記憶されてもよい。
信号機識別子取得部14は、地図情報記憶部11で記憶されている地図情報を用いて、現在位置取得部12が取得した現在位置に応じた信号機を識別する信号機識別子を取得する。現在位置に応じた信号機とは、現在位置に近い信号機であり、点灯色取得部13が点灯色を取得する信号機である。その信号機は、例えば、第1の車両の進行方向前方に存在する信号機のうち、現在位置に最も近い位置にある信号機であってもよい。信号機識別子は、例えば、信号機ごとに割り当てられた文字や数字等の列、すなわち、記号列であってもよく、あるいは、信号機の存在する位置の座標等であってもよい。なお、その信号機識別子は、方向をも識別できるものであってもよく、あるいは、そうでなくてもよい。その方向は、信号機が示す点灯色に関する方向であり、例えば、その点灯色を示す車両の進行方向であってもよい。具体的には、東西方向の道路と、南北方向の道路とが交差する交差点にある信号機の信号機識別子は、東西南北の各方向に進行する車両に対する信号機ごとに異なっていてもよい。すなわち、ある交差点の信号機の信号機識別子は、その交差点に進入する向きごとに異なるものであってもよい。ここで、ある交差点において、ある向きの信号機の点灯色と、逆向きの信号機の点灯色とは、通常、同じである。したがって、それらの信号機を識別する信号機識別子は、同じであってもよい。また、信号機識別子取得部14が取得する信号機識別子は、点灯色取得部13が点灯色を取得する信号機を識別する信号機識別子である。後述するように、点灯色取得部13は、通常、第1の車載装置1が設置された車両の前方にある信号機の点灯色を取得する。したがって、信号機識別子取得部14も、第1の車載装置1が設置された車両の前方にある信号機の信号機識別子を取得してもよい。そのため、信号機識別子取得部14は、現在位置取得部12が取得した現在位置を用いて、地図情報の示す地図上における車両の位置を特定し、その特定した位置よりも進行方向前方に存在する1個目の信号機を特定し、その信号機を識別する信号機識別子を取得してもよい。具体的には、信号機識別子が記号列であり、地図情報にその記号列が含まれる場合には、信号機識別子取得部14は、特定した信号機に対応する記号列である信号機識別子を取得してもよい。一方、信号機識別子が座標である場合には、信号機識別子取得部14は、特定した信号機の位置を示す座標を取得してもよい。なお、ある交差点に存在する信号機の信号機識別子が車両の進行方向ごとに異なる場合には、信号機識別子取得部14は、その交差点を識別する識別子と、向きや方向を識別する識別子とを有する信号機識別子を取得してもよい。本実施の形態では、この場合について主に説明する。
送信部15は、信号機識別子取得部14が取得した信号機識別子と、その信号機識別子で識別される信号機の点灯色とを第2の車載装置2に送信する。すなわち、送信部15は、信号機識別子等を他の車載装置に送信する。その点灯色は、点灯色取得部13が取得したものである。通常、点灯色取得部13は、第1の車両の前方にある最も近い信号機の点灯色を取得し、信号機識別子取得部14も、第1の車両の前方にある最も近い信号機の信号機識別子を取得するため、点灯色取得部13は、信号機識別子取得部14が取得した信号機識別子で識別される信号機の点灯色を取得することになる。なお、送信部15は、それらに加えて、点灯色取得部13が点灯色を取得した時刻をも第2の車載装置2に送信してもよい。その時刻は、前述のように、点灯色取得部13が取得したものであってもよく、または、他の構成要素が図示しない時計部から取得したものであってもよい。また、送信部15は、送信対象である信号機識別子と、それで識別される信号機の点灯色と、その点灯色を取得した時刻とを対応付けて第2の車載装置2に送信することが好適である。信号機識別子等を対応付けて送信するとは、例えば、信号機識別子等を1個のパケットで送信することであってもよく、信号機識別子等を連続して送信することであってもよく、または、信号機識別子等を他の識別子等を用いて紐付けて送信することであってもよい。他の構成要素が複数の情報を対応付けて送信する場合にも、同様であるとする。
なお、送信部15は、信号機識別子等を第2の車載装置2に直接送信してもよく、あるいは、サーバ等を介して間接的に送信してもよい。すなわち、第1の車載装置1と第2の車載装置2とは、車車間通信を行ってもよく、あるいは、車路車間通信を行ってもよい。また、送信部15は、図示しない記録媒体で保持している第2の車載装置2のアドレスを送信先として送信を行ってもよく、送信までに他の構成要素や他のサーバ等から受け取った第2の車載装置2のアドレスを送信先として送信を行ってもよい。また、送信部15は、ユニキャスト方式により、特定の第2の車載装置2を送信先として送信を行ってもよく、マルチキャスト方式により所定のグループに属する第2の車載装置2を送信先として送信を行ってもよく、あるいは、ブロードキャスト方式により通信範囲内に存在するすべての第2の車載装置2を送信先として送信を行ってもよい。なお、送信部15による通信は、例えば、無線アドホックネットワークを用いて行われてもよい。また、送信部15による通信は、例えば、DSRC(Dedicated Short Range Communications)によって行われてもよい。また、送信部15による通信は、例えば、可視光通信によって行われてもよい。また、送信部15は、送信を行うための送信デバイス(例えば、モデムやネットワークカードなど)を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、送信部15は、ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは送信デバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
ここで、点灯色取得部13による点灯色の取得方法について説明する。点灯色取得部13は、例えば、(1)車両の進行状況に応じて点灯色を取得してもよく、(2)信号機の画像を用いて点灯色を取得してもよく、(3)信号機から送信された点灯色を取得してもよい。以下、その3つの点灯色の取得方法についてそれぞれ説明する。
(1)車両の進行状況に応じて点灯色を取得する場合
図3は、車両の進行状況に応じて点灯色を取得する点灯色取得部13の構成を示すブロック図である。その点灯色取得部13は、進行判断手段16と、信号機判断手段17と、取得手段18とを備える。
進行判断手段16は、第1の車載装置1の設置されている第1の車両が進行しているかどうか判断する。進行判断手段16は、例えば、第1の車両が第1のしきい値以上の速度である場合に、第1の車両が進行していると判断し、第1の車両が第2のしきい値以下の速度である場合に、第1の車両が停止していると判断してもよい。通常、第1のしきい値は、第2のしきい値以上の値である。また、第1のしきい値と第2のしきい値とは同じであってもよく、あるいは、異なっていてもよい。また、第2のしきい値は、0であってもよい。すなわち、第1の車両が完全に停止している場合にのみ、進行判断手段16は、第1の車両が停止していると判断してもよい。進行判断手段16は、例えば、現在位置取得部12が取得する現在位置の時間変化を用いて、第1の車両が進行しているかどうかを判断してもよく、第1の車両に設置されている図示しない速度計を用いて第1の車両が進行しているかどうかを判断してもよく、あるいは、その他の方法によって第1の車両が進行しているかどうかを判断してもよい。
信号機判断手段17は、現在位置取得部12が取得した現在位置が信号機に応じた領域に存在するかどうかを判断する。信号機判断手段17は、通常、地図情報記憶部11で記憶されている地図情報を用いてその判断を行う。信号機に応じた領域とは、通常、信号機の位置から、その位置よりもあらかじめ決められた距離だけ進行方向と逆向きに進んだ位置までの領域である。その距離は、その信号機の点灯色が青である場合には、その領域を車両が走行しており、その信号機の点灯色が赤である場合には、その領域で車両が停止しているように設定されることが好適である。その距離は、例えば、50メートルや100メートルであってもよい。なお、そのような判断を行うため、信号機判断手段17は、例えば、現在位置から、進行方向にあらかじめ決められた距離だけ進んだ位置までの範囲内に信号機が存在するかどうかを判断してもよい。そして、その範囲内に信号機が存在する場合には、現在位置が信号機に応じた領域に存在すると判断し、存在しない場合には、現在位置が信号機に応じた領域に存在しないと判断してもよい。
取得手段18は、現在位置が信号機に応じた領域に存在すると信号機判断手段17によって判断された場合において、車両が進行していると進行判断手段16によって判断されたときに、進行に応じた点灯色「青」を取得し、車両が停止していると進行判断手段16によって判断されたときに、停止に応じた点灯色「赤」を取得する。なお、現在位置が信号機に応じた領域に存在しないと信号機判断手段17によって判断された場合や、車両が進行しておらず、停止もしていないと進行判断手段16によって判断された場合には、取得手段18は、点灯色を取得しないものとする。ここで、車両が進行しておらず、停止していない場合とは、例えば、車両が徐行している場合である。その場合には、車両が停止に応じた点灯色によって徐行しているのか、渋滞等によって徐行しているのかを判断できないため、点灯色を取得しないものとしている。このようにして、点灯色取得部13は、第1の車両が走行しているかどうかに応じた点灯色を取得することができる。
(2)信号機の画像を用いて点灯色を取得する場合
図4は、信号機の画像を用いて点灯色を取得する点灯色取得部13の構成を示すブロック図である。その点灯色取得部13は、画像取得手段19と、取得手段20とを備える。
画像取得手段19は、信号機の画像を取得する。画像取得手段19は、例えば、第1の車両の進行方向前方の静止画や動画を撮影するデジタルカメラであってもよく、あるいは、そのようなカメラで撮影された画像を受け取るものであってもよい。なお、画像が静止画である場合であっても、第1の車両の進行に応じて信号機の点灯色を取得することができる程度の時間間隔で撮影される静止画であることが好適である。その時間間隔は、例えば、0.5秒や1秒であってもよい。なお、信号機の画像は、通常、第1の車両の進行方向の信号機の画像であるが、その進行方向と交わる方向の信号機の画像であってもよい。その取得された画像は、図示しない記録媒体で記憶されてもよい。
取得手段20は、画像取得手段19が取得した信号機の画像を用いて、信号機の点灯色を取得する。この取得手段20が取得する信号機の点灯色は、通常、第1の車両の進行方向前方の信号機の点灯色である。なお、その点灯色の取得方法としては、例えば、前述の特許文献1等で開示されている方法を用いることができる。例えば、取得手段20は、取得された信号機の画像において、信号灯の領域を特定し、その特定した信号灯の領域において点灯している信号灯に対応する点灯色を特定することによって点灯色を取得してもよい。なお、点灯している信号灯の色に応じて点灯色を特定する場合には、画像取得手段19が取得する信号機の画像は、カラー画像であることが好適である。一方、点灯している信号灯の位置に応じて点灯色を特定する場合には、画像取得手段19が取得する信号機の画像は、カラー画像であってもよく、白黒の画像であってもよい。また、第1の車両の進行方向と交わる方向の信号機の画像を画像取得手段19が取得する場合には、取得手段20は、その画像を用いて取得した点灯色と反対の点灯色である信号機の点灯色を取得してもよい。そのようにすることで第1の車両の進行方向前方の信号機の点灯色を取得できるからである。なお、ある点灯色と反対の点灯色とは、ある点灯色が青の場合には赤であり、ある点灯色が赤の場合には青であり、ある点灯色が黄の場合には赤である。
(3)信号機から送信された点灯色を取得する場合
信号機が、その信号機の点灯色を送信する機能を有する場合には、点灯色取得部13は、その送信された点灯色を受信することによって、点灯色を取得できる。なお、その点灯色は、その点灯色を表示している信号機を識別する信号機識別子と共に送信されてもよい。その場合には、点灯色取得部13は、所望の信号機の信号機識別子と共に送信される点灯色を取得してもよい。また、その点灯色は、電波ビーコンや、光ビーコン、路側通信などによって送信されてもよく、または、その他の通信方法によって送信されてもよい。
なお、ここでは、点灯色を取得する(1)〜(3)の場合について説明したが、点灯色取得部13が、それ以外の方法によって点灯色を取得してもよいことは言うまでもない。
図5は、本実施の形態による第2の車載装置2の構成を示すブロック図である。本実施の形態による第2の車載装置2は、受信部21と、蓄積部22と、記憶部23と、点灯色予測部24と、送信部25と、地図情報記憶部26と、現在位置取得部27と、地点受付部28と、経路探索部29と、出力部30とを備える。
受信部21は、第1の車載装置1から送信された信号機識別子及び点灯色を受信する。なお、第1の車載装置1から時刻も送信された場合には、受信部21は、その時刻をも受信する。また、受信部21は、他の第2の車載装置2から送信された信号機識別子や点灯色、時刻を受信してもよい。すなわち、受信部21は、他の車載装置から送信された信号機識別子等を受信する。また、受信部21は、その他の情報を受信してもよい。また、受信部21は、受信を行うための有線または無線の受信デバイス(例えば、モデムやネットワークカードなど)を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、受信部21は、ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは受信デバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
蓄積部22は、受信部21が受信した信号機識別子及び点灯色を対応付けて記憶部23に蓄積する。また、蓄積部22は、信号機識別子、点灯色、及び点灯色に応じた時刻を対応付けて記憶部23に蓄積してもよい。点灯色に応じた時刻は、受信部21が信号機識別子等と共に時刻をも受信した場合には、その時刻であってもよく、そうでない場合には、信号機識別子等が受信された時刻や蓄積される時刻であってもよい。後者の場合には、その時刻は、受信部21や蓄積部22が図示しない時計部から取得したものであってもよい。なお、本実施の形態では、蓄積部22が時刻をも蓄積する場合について主に説明する。また、複数の情報を対応付けて蓄積するとは、それらの情報が紐付けられるように蓄積することである。具体的には、蓄積部22は、それらの情報を一のレコード等に蓄積してもよく、それらの情報をポインタ等で対応付けて蓄積してもよい。また、蓄積部22が信号機識別子と点灯色とを対応付けて記憶部23に蓄積するとは、結果として、記憶部23で、それらの情報が対応付けられて記憶されるようにすることである。したがって、結果としてそのようになるのであれば、蓄積部22が信号機識別子等を蓄積する方法を問わない。例えば、記憶部23に信号機識別子があらかじめ記憶されている場合には、蓄積部22は、その信号機識別子に対応付けて点灯色のみを蓄積してもよい。
記憶部23では、蓄積部22によって蓄積された信号機識別子等が記憶される。なお、記憶部23で記憶されている信号機識別子等のうち、古いものについては順次、削除されてもよい。ただし、点灯色予測部24による点灯色の予測を行う場合には、その予測で用いる程度の時刻や点灯色等を残すようにしてもよい。具体的には、記憶部23では、最新の1時間程度の情報のみを残しておくようにしてもよい。記憶部23での記憶は、RAM等における一時的な記憶でもよく、あるいは、長期的な記憶でもよい。記憶部23は、所定の記録媒体(例えば、半導体メモリや磁気ディスクなど)によって実現されうる。
点灯色予測部24は、蓄積部22が記憶部23に蓄積した点灯色及び時刻を用いて、将来の点灯色を予測する。通常、信号機は規則的に点灯色を変えるため、点灯色予測部24は、その規則性を用いて予測を行うことができる。なお、この予測方法については後述する。
送信部25は、受信部21が受信した信号機識別子及び点灯色を他の第2の車載装置2に送信する。すなわち、送信部25は、信号機識別子等を他の車載装置に送信する。送信部25は、受信された信号機識別子等を対応付けて送信することが好適である。また、受信部21が時刻をも受信した場合には、送信部25は、信号機識別子、点灯色、及び時刻を対応付けて他の第2の車載装置2に送信することが好適である。受信された点灯色等を送信部25が送信することによって、第2の車載装置2間で、点灯色等が転々と伝送されることになる。その結果、第1の車載装置1で取得された点灯色等が、その第1の車載装置1とは直接通信できない第2の車載装置2でも取得されるようになる。すなわち、車載装置間においては、デイジーチェーン方式によって通信が行われることになる。
送信部25は、受信部21が受信した信号機識別子等をすべて送信してもよく、あるいは、受信部21が受信した信号機識別子等のうち、一部の信号機識別子等を送信してもよい。後者の場合について、いくつかの具体例を説明する。
(A)時刻を用いる方法
例えば、信号機識別子と、点灯色と、その点灯色に応じた時刻とが送受信される場合に、受信された信号機識別子等に含まれる時刻と現在の時刻との差があらかじめ決められたしきい値より大きくなると、送信部25は、その時刻を含む信号機識別子等を送信しなくてもよい。古い情報を送受信する必要はないからである。
(B)経由数を用いる方法
信号機識別子等の経由した第2の車載装置2の数である経由数が管理されている場合に、その経由数があらかじめ決められたしきい値を超えると、送信部25は、その信号機識別子等を送信しなくてもよい。信号機の情報は、その信号機の近くで用いられるべきであり、遠方にまで伝送される必要はないからである。その経由数の管理方法は問わない。例えば、信号機識別子等を送受信するパケットのヘッダに、第2の車載装置2を経由するごとに1だけデクリメントされる寿命が設定されており、その寿命がなくなったとき、すなわち、1や0になったときに、送信部25は、そのパケットを送信しなくてもよい。この場合には、第1の車載装置1が信号機識別子等を含むパケットを送信する際に、あらかじめ決められた値に応じた寿命をヘッダに設定しているものとする。また、例えば、信号機識別子等を送受信するパケットのヘッダに、第2の車載装置2を経由するごとに1だけインクリメントされるホップ数が設定されており、そのホップ数があらかじめ決められた値を超えたときに、送信部25は、そのパケットを送信しなくてもよい。
(C)信号機の位置を用いる方法
受信された信号機識別子で識別される信号機の位置と、第2の車載装置2の現在位置と距離が、あらかじめ決められたしきい値を超えている場合に、送信部25は、その信号機識別子等を送信しなくてもよい。このようにすることで、信号機から所定の範囲内でのみ、その信号機に関する点灯色等が伝送されるようにすることができる。なお、送信部25は、例えば、信号機識別子が信号機の位置である場合には、その信号機識別子を用いて信号機の位置を取得してもよく、信号機の位置を示す情報が信号機識別子等と一緒に通信される場合には、その情報を用いて信号機の位置を取得してもよく、地図情報を用いて、信号機識別子に対応する位置を取得してもよい。
(D)送信内容を用いる方法
例えば、送信部25は、すでに送信した信号機識別子等と同じ信号機識別子等が受信された場合には、その信号機識別子等を送信しなくてもよい。具体的には、蓄積部22が、信号機識別子等を蓄積する際に、すでに同じ情報が蓄積されていた場合には、送信部25は、その信号機識別子等を送信しなくてもよい。デイジーチェーン方式の通信におけるループ状の通信経路の生成を防止するためである。
なお、送信部25は、信号機識別子等を第2の車載装置2に直接送信してもよく、あるいは、サーバ等を介して間接的に送信してもよい。すなわち、第2の車載装置2同士は、車車間通信を行ってもよく、あるいは、車路車間通信を行ってもよい。また、送信部25は、図示しない記録媒体で保持している第2の車載装置2のアドレスを送信先として送信を行ってもよく、送信までに他の構成要素や他のサーバ等から受け取った第2の車載装置2のアドレスを送信先として送信を行ってもよい。また、送信部25は、ユニキャスト方式により、特定の第2の車載装置2を送信先として送信を行ってもよく、マルチキャスト方式により所定のグループに属する第2の車載装置2を送信先として送信を行ってもよく、あるいは、ブロードキャスト方式により通信範囲内に存在するすべての第2の車載装置2を送信先として送信を行ってもよい。なお、送信部25による通信は、例えば、無線アドホックネットワークを用いて行われてもよい。また、送信部25による通信は、例えば、DSRCによって行われてもよい。また、送信部25による通信は、例えば、可視光通信によって行われてもよい。また、送信部25は、送信を行うための送信デバイス(例えば、モデムやネットワークカードなど)を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、送信部25は、ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは送信デバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
地図情報記憶部26には、信号機の位置を含む地図に関する情報である地図情報が記憶される。なお、地図情報記憶部26は、第1の車載装置1が有する地図情報記憶部11と同様のものであり、その詳細な説明を省略する。なお、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報は、経路探索を行うことができるものであることが好適である。
現在位置取得部27は、第2の車載装置2の現在位置を取得する。なお、現在位置取得部27は、第1の車載装置1が有する現在位置取得部12と同様のものであり、その詳細な説明を省略する。
地点受付部28は、出発地及び目的地を受け付ける。この出発地等は、経路探索で用いられるものである。なお、地点受付部28は、ユーザが入力した出発地及び目的地を受け付けてもよく、ユーザが入力した目的地と、現在位置取得部27が取得した現在位置である出発地とを受け付けてもよい。なお、ユーザによって入力された地点は、例えば、選択された地点であってもよく、検索結果の地点であってもよく、その他の入力された地点であってもよい。
地点受付部28は、例えば、入力デバイス(例えば、キーボードやマウス、タッチパネルなど)から入力された目的地等を受け付けてもよく、有線もしくは無線の通信回線を介して送信された目的地等を受信してもよく、所定の記録媒体(例えば、光ディスクや磁気ディスク、半導体メモリなど)から読み出された目的地等を受け付けてもよく、他の構成要素から目的地等を受け付けてもよい。なお、地点受付部28は、受け付けを行うためのデバイス(例えば、モデムやネットワークカードなど)を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、地点受付部28は、ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは所定のデバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
経路探索部29は、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて、地点受付部28が受け付けた出発地から目的地までの経路を探索する。なお、経路探索部29は、信号機識別子及び点灯色と、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報とを用いて、停止に応じた点灯色の信号機を回避するように経路探索を行ってもよい。停止に応じた点灯色の信号機を回避するとは、その信号機の位置を完全に通過しないことであってもよく、または、その信号機の位置を通過する可能性を低くすること、すなわち、実際には通過する可能性もありうることであってもよい。そのようにして探索された経路は、赤信号で停止しない、または、停止する時間の短いものである。そのような経路を探索する方法は、例えば、次のようである。経路探索部29は、出発地から目的地までの経路を通常通りに探索する。そして、経路探索部29は、探索結果の経路において、1個目の信号機に到達する時刻を算出する。また、経路探索部29は、その1個目の信号機について、算出した時刻の点灯色を予測するように点灯色予測部24に指示する。そして、その指示に応じて予測された点灯色が青かどうか判断する。青であれば、まだ点灯色を判断していない出発地に最も近い信号機について、同様の処理を繰り返す。一方、赤であれば、その信号機の位置を通過しないように、あるいは、その信号機の位置を通過し難いように設定して、再度、経路探索を行う。そして、その再探索された経路において、また点灯色を判断していない出発地に最も近い信号機について、同様の処理を繰り返す。このようにして、経路の最後の信号機までの処理を行うことによって、赤信号を回避した経路探索を行うことができる。なお、この経路探索の方法は一例であって、他の方法によって赤信号を回避するように経路探索を行ってもよい。例えば、経路探索部29は、経路探索を行う際に、赤信号である交差点のスコアを調整することによって、その赤信号の交差点をできるだけ通過しないように経路探索を行ってもよい。
なお、経路探索部29は、経路探索によって、経路を示す経路情報を取得してもよい。その経路情報は、出発地から目的地までの経路を構成する多数の点を示す情報であってもよい。また、その経路情報は、出発地から目的地までの経路を示す画像を含んでいてもよく、出発地から目的地までの移動時間に関する情報を含んでいてもよい。また、その経路情報は、図示しない記録媒体で記憶されてもよい。また、経路探索部29は、例えば、地図情報を用いて、始点から終点までの経路のスコアが最小となるように経路を探索する。その経路探索において、例えば、ダイクストラ法を用いてもよく、A*アルゴリズムを用いてもよく、ベルマン−フォード法を用いてもよく、ワーシャル−フロイド法を用いてもよく、その他のアルゴリズムを用いてもよい。この経路探索方法はすでに公知であり、その詳細な説明を省略する。例えば、オンラインマップにおいて、始点の緯度・経度と、終点の緯度・経度を入力すると、その始点から終点までの経路が表示されるものがある(例えば、「http://maps.google.co.jp/maps」等を参照のこと)。
出力部30は、蓄積部22が蓄積した信号機識別子及び点灯色を用いて、その点灯色に関する出力を行う。その点灯色は、例えば、現在位置に応じた領域にある信号機の信号機識別子に対応する点灯色でもよく、あるいは、その他の点灯色であってもよい。現在位置に応じた領域にある信号機とは、例えば、現在位置から、進行方向に所定の距離だけ進んだ位置までの間に存在する信号機であってもよく、現在位置を中心とした所定の範囲内に存在する信号機であってもよい。点灯色に関する出力は、点灯色と何らかの関連のある出力であれば、その内容を問わない。その出力は、点灯色の直接的な出力であってもよく、あるいは、間接的な出力であってもよい。点灯色の直接的な出力とは、例えば、点灯色そのものを出力することである。一方、点灯色の間接的な出力とは、例えば、点灯色を用いて生成された情報を出力することである。例えば、出力部30は、点灯色を出力してもよく、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を読み出して表示し、その表示された地図上において、信号機識別子で識別される信号機の位置に、その信号機識別子に対応する点灯色を示す表示を行ってもよい。信号機識別子に対応する点灯色とは、その信号機識別子で識別される信号機の点灯色の意味である。点灯色を示す表示は、例えば、「赤」「青」等のテキスト表示であってもよく、点灯色に応じた信号機の図形の表示であってもよい。点灯色に応じた信号機の図形とは、その点灯色を点灯している信号機の図形のことである。このように、出力部30は、点灯色を第2の車載装置2のユーザに知らせるための出力を行ってもよい。その出力は、表示でもよく、音声出力でもよい。また、例えば、出力部30は、点灯色が「赤」である場合に、前方の信号機が赤である旨の警告を音声出力してもよい。また、出力部30は、点灯色予測部24が予測した点灯色に関する出力を行ってもよい。例えば、点灯色予測部24によって、点灯色の継続時間が予測された場合には、出力部30は、点灯色を出力すると共に、その継続時間をも出力してもよい。そのようにすることで、ユーザは、信号機の点灯色が赤から青に変わるタイミングや、その逆のタイミングを知ることができるようになる。そのため、例えば、渋滞時に交差点に進入した状態で赤信号になることなどを回避することができるようになる。なお、点灯色の継続時間とは、その点灯色が継続する時間、すなわち、その点灯色が別の点灯色に変わるまでの時間である。例えば、継続時間が「20秒」であれば、あと20秒は、現在の点灯色が継続することを知ることができる。なお、その継続時間は、将来の点灯色の継続時間であってもよい。また、例えば、第2の車両が停止しようと減速している場合に、もう少し(例えば、あと2,3秒程度等)で青信号になる旨の予測結果の出力がなされると、第2の車両は、ローリングスタートを行うことができ、燃費を向上させることができる。なお、ローリングスタートとは、減速した後に、完全に停止することなく、加速を行うことである。また、出力部30は、点灯色の継続時間によって、第2の車両が信号機の位置に到着する時点では、赤信号になっていることが分かる場合に、その信号機で適切に停止できるための速度を出力してもよい。第2の車両の運転者は、その出力された速度に応じて、第2の車両を減速させることができる。なお、その速度は、信号機までの距離が短いほど、より遅い速度となるように設定されてもよい。また、出力部30は、経路探索部29が探索した経路に関する出力を行う。その経路に関する出力は、例えば、地図情報を読み出して表示し、その地図上に経路を表示することであってもよい。また、その探索された経路は、赤信号を回避するように探索された経路であってもよい。その場合には、その経路の出力が、点灯色に関する出力であると考えられる。また、出力部30は、第2の車両の進行方向前方の信号機の点灯色が停止に応じたものであることが、蓄積部22によって蓄積された信号機識別子や点灯色によって示される場合に、第2の車両を停止させるための制御信号を出力してもよい。その制御信号は、例えば、第2の車両の走行を制御する図示しない制御部に出力されてもよい。その制御信号は、例えば、第2の車両のブレーキを作動させる制御信号であってもよく、第2の車両のアクセルをゆるめる制御信号であってもよく、第2の車両を停止させるためのその他の制御のための制御信号であってもよい。その制御信号を用いた制御において、現在位置と信号機までの距離が短いほど、より遅い速度となるように制御されてもよい。
ここで、この出力部30による出力は、例えば、表示デバイス(例えば、CRTや液晶ディスプレイなど)への表示でもよく、所定の機器への通信回線を介した送信でもよく、スピーカによる音声出力でもよく、記録媒体への蓄積でもよく、他の構成要素への引き渡しでもよい。なお、出力部30は、出力を行うデバイス(例えば、表示デバイスや通信デバイスなど)を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、出力部30は、ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは、それらのデバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
なお、記憶部23と、地図情報記憶部26とは、同一の記録媒体によって実現されてもよく、あるいは、別々の記録媒体によって実現されてもよい。前者の場合には、点灯色等を記憶している領域が記憶部23となり、地図情報を記憶している領域が地図情報記憶部26となる。
ここで、点灯色予測部24による将来の点灯色の予測方法について簡単に説明する。点灯色予測部24は、記憶部23で記憶されている、ある信号機の時刻及び点灯色の履歴を用いて、次のように処理を行う。
(処理1)点灯色の変化時刻の特定
点灯色予測部24は、ある信号機の時刻及び点灯色の履歴を用いて、点灯色の変化時刻を特定する。具体的には、時間的に隣接する点灯色が異なっており、かつ、その異なっている各点灯色にそれぞれ対応している時刻の差が所定の期間以内である場合に、その点灯色の変化した時点である変化時刻を特定する。その所定の期間は、短いほど変化時刻が正確になるが、変化が特定され難くなる。そのため、変化時刻を特定できると共に、変化時刻がある程度正確になるような所定の期間を設定することが好適である。その所定の期間は、例えば、3秒や5秒等であってもよい。また、点灯色予測部24は、その特定した変化に関する変化前の点灯色に対応する時刻である変化時刻を特定してもよく、または、その特定した変化に関する変化後の点灯色に対応する時刻である変化時刻を特定してもよい。例えば、
時刻 点灯色
10:15:20 青
10:15:24 赤
である場合に、点灯色予測部24は、青から赤への変化について、変化時刻「10:15:20」を特定してもよく、変化時刻「10:15:24」を特定してもよい。なお、変化前の時刻を変化時刻とするのか、あるいは、変化後の時刻を変化時刻とするのかは決まっていることが好適である。また、変化前の時刻と変化後の時刻との中間の時刻、上記例の場合には「10:15:22」を変化時刻としてもよい。本実施の形態では、この場合について主に説明する。なお、点灯色予測部24は、ある信号機について変化時刻を特定する場合に、記憶部23で記憶されているすべての時刻を用いて変化時刻の特定を行ってもよく、あるいは、最新の所定の期間の時刻を用いて変化時刻の特定を行ってもよい。後者の場合には、例えば、最新の1時間や30分間の時刻を用いて変化時刻の特定が行われてもよい。
(処理2)各点灯色の期間候補の取得
点灯色予測部24は、処理1で特定した変化時刻を用いて、ある変化時刻から次の変化時刻までの間に、それらの変化時刻に応じた点灯色の変化以外の他の点灯色の変化があるかどうか判断する。そして、他の点灯色の変化がない場合には、点灯色予測部24は、その変化時刻から次の変化時刻までの時間を、その時間に応じた点灯色の期間候補とする。その時間に応じた点灯色とは、時間的に前の変化時刻に対応する変化における変化後の点灯色、すなわち、時間的に後の変化時刻に対応する変化における変化前の点灯色である。点灯色予測部24は、時間的に隣接するすべての変化時刻について、この処理を行う。
(処理3)各点灯色の期間の特定
点灯色予測部24は、処理2で取得した各点灯色の期間候補を用いて、各点灯色の期間を特定する。点灯色予測部24は、例えば、各点灯色の期間候補の平均をそれぞれ算出することによって各点灯色の期間を算出してもよく、各点灯色の期間候補の中央値を特定することによって行ってもよく、その他の方法によって各点灯色の期間を特定してもよい。なお、ある点灯色の期間候補が、他の期間候補の2倍以上の長さである場合には、その期間候補を破棄して点灯色の期間を特定してもよい。例えば、夜間などにおいて交通量が少ない場合には、点灯色が赤→青→赤と変化したとしても、その青の期間の点灯色が取得されないこともありうる。そのような状況で取得された期間候補を用いて点灯色の期間を特定することは適切でないため、点灯色予測部24は、そのような期間候補を破棄してもよい。
(処理4)点灯色の予測
点灯色予測部24は、処理3で特定した各点灯色の期間を用いて、点灯色の予測を行う。ある予測時刻に対応する点灯色を予測する場合には、点灯色予測部24は、例えば、最新の変化時刻から、特定した点灯色の期間を予測時刻となるまで順次加算することによって、予測時刻に応じた点灯色を特定できる。また、現在の点灯色の継続時間を予測する場合には、点灯色予測部24は、例えば、最新の変化時刻に現在の点灯色の期間を加算した時刻から、現在の時刻を減算することによって、現在の点灯色の継続時間を特定できる。なお、点灯色予測部24は、処理3で特定した各点灯色の期間を用いて、その他の方法によって点灯色の予測を行ってもよいことは言うまでもない。
なお、情報通信システム100の第1及び第2の車載装置1,2において図示しない時計部から時刻を取得されることがあるが、その時計部は、各装置において、同一の時刻となるように同期されていることが好適である。そのため、例えば、その時計部は、電波時計であってもよく、NTP(Network Time Protocol)サーバ等を用いて同期されてもよい。
次に、第1の車載装置1の動作について図6のフローチャートを用いて説明する。
(ステップS101)現在位置取得部12は、新たな現在位置を取得したかどうか判断する。そして、新たな現在位置を取得した場合には、ステップS102に進み、そうでない場合には、新たな現在位置を取得するまでステップS101の処理を繰り返す。現在位置取得部12は、例えば、新たな現在位置を取得したと判断した場合に、その現在位置を図示しない記録媒体において一時的に記憶しておき、最新の現在位置がその一時的に記憶している現在位置と異なる場合に、新たな現在位置を取得したと判断して、その新たな現在位置を図示しない記録媒体に上書きで蓄積してもよい。
(ステップS102)信号機識別子取得部14は、地図情報記憶部11で記憶されている地図情報と、現在位置取得部12が取得した現在位置とを用いて、その現在位置に応じた信号機の信号機識別子を取得する。
(ステップS103)点灯色取得部13は、点灯色を取得する処理を行う。なお、この処理によって点灯色が取得されることもあるが、取得されないこともある。この処理の詳細については、図7Aや図7Bのフローチャートを用いて後述する。
(ステップS104)点灯色取得部13は、点灯色を取得できたかどうか判断する。そして、点灯色を取得できた場合には、ステップS105に進み、取得できなかった場合には、ステップS101に戻る。なお、点灯色を取得できた場合には、点灯色取得部13は、その時点の時刻をも取得するものとする。
(ステップS105)送信部15は、信号機識別子取得部14が取得した最新の信号機識別子と、点灯色取得部13が取得した最新の点灯色と、その取得時の時刻とを第2の車載装置2に送信する。そして、ステップS101に戻る。
なお、図6のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終了する。また、ステップS102において信号機識別子を取得できなかった場合、すなわち、現在位置に応じた信号機が存在しない場合には、ステップS101に戻ってもよい。
図7Aは、図6のフローチャートにおける点灯色の取得の処理(ステップS103)、特に車両の進行状況に応じて点灯色を取得する処理の詳細を示すフローチャートである。
(ステップS201)信号機判断手段17は、現在位置取得部12が取得した現在位置が、信号機に応じた領域に存在するかどうか判断する。そして、その領域に存在する場合には、ステップS202に進み、そうでない場合には、図6のフローチャートに戻る。なお、その信号機は、通常、信号機識別子取得部14が取得した信号機識別子で識別される信号機である。
(ステップS202)進行判断手段16は、第1の車両が進行しているかどうか判断する。そして、進行している場合には、ステップS203に進み、そうでない場合には、ステップS204に進む。
(ステップS203)取得手段18は、進行に応じた点灯色を取得する。そして、図6のフローチャートに戻る。
(ステップS204)進行判断手段16は、第1の車両が停止しているかどうか判断する。そして、停止している場合には、ステップS205に進み、そうでない場合には、図6のフローチャートに戻る。
(ステップS205)取得手段18は、停止に応じた点灯色を取得する。そして、図6のフローチャートに戻る。
図7Bは、図6のフローチャートにおける点灯色の取得の処理(ステップS103)、特に信号機の画像を用いて点灯色を取得する処理の詳細を示すフローチャートである。
(ステップS206)画像取得手段19は、画像を取得する。
(ステップS207)取得手段20は、画像取得手段19が取得した画像を用いて、信号機の点灯色を取得する。なお、画像取得手段19が取得した画像に信号機が含まれていない場合には、点灯色の取得は行われないことになる。そして、図6のフローチャートに戻る。
なお、信号機から送信された点灯色を取得する場合には、点灯色取得部13は、信号機識別子取得部14が取得した信号機識別子で識別される信号機から送信された点灯色を受信することによって、その信号機の点灯色を取得してもよい。
次に、第2の車載装置2の動作について図8のフローチャートを用いて説明する。
(ステップS301)受信部21は、点灯色等を受信したかどうか判断する。そして、受信した場合には、ステップS302に進み、そうでない場合には、ステップS305に進む。
(ステップS302)蓄積部22は、受信部21が受信した点灯色等を対応付けて記憶部23に蓄積する。
(ステップS303)送信部25は、ステップS301で受信された点灯色等を送信するかどうか判断する。そして、送信する場合には、ステップS304に進み、そうでない場合には、ステップS301に戻る。なお、送信部25は、前述のように、受信された時刻と現在時刻との差がしきい値以上である場合に送信しないと判断してもよく、受信された点灯色等がしきい値以上の数の装置を経由している場合に送信しないと判断してもよく、受信された点灯色等が過去にも受信されたものである場合に送信しないと判断してもよく、あるいは、その他の理由で送信しないと判断してもよい。
(ステップS304)送信部25は、ステップS301で受信された点灯色等を他の第2の車載装置2に送信する。そして、ステップS301に戻る。
(ステップS305)現在位置取得部27は、新たな現在位置を取得したかどうか判断する。そして、新たな現在位置を取得した場合には、ステップS306に進み、そうでない場合には、ステップS308に進む。現在位置取得部27は、例えば、新たな現在位置を取得したと判断した場合に、その現在位置を図示しない記録媒体において一時的に記憶しておき、最新の現在位置がその一時的に記憶している現在位置と異なる場合に、新たな現在位置を取得したと判断して、その新たな現在位置を図示しない記録媒体に上書きで蓄積してもよい。
(ステップS306)出力部30は、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて、現在位置取得部27が取得した現在位置に応じた信号機が存在するかどうか判断する。そして、信号機が存在する場合には、ステップS307に進み、そうでない場合には、ステップS301に戻る。なお、出力部30は、第2の車両の進行方向前方に信号機が存在する場合に、現在位置に応じた信号機が存在すると判断してもよい。また、出力部30は、現在位置から所定の範囲内(例えば、半径500メートル以内等)に信号機がない場合には、現在位置に応じた信号機が存在しないと判断してもよい。また、出力部30は、進行方向前方に代えて、経路探索部29が探索した経路の前方に信号機が存在するかどうか判断してもよい。
(ステップS307)出力部30は、ステップS306で存在すると判断した信号機を識別する信号機識別子に対応する最新の点灯色を記憶部23から読み出し、その点灯色に関する出力を行う。この出力は、例えば、信号機の点灯色を示す情報を出力することであってもよく、その点灯色が停止に応じたものである場合に、第2の車両を停止させるための制御信号を出力することであってもよい。そして、ステップS301に戻る。
(ステップS308)地点受付部28は、出発地と目的地とを受け付けたかどうか判断する。そして、出発地等を受け付けた場合には、ステップS309に進み、そうでない場合には、ステップS301に戻る。その出発地の受け付けは、前述のように、現在位置取得部27からの受け付けであってもよい。
(ステップS309)経路探索部29は、地点受付部28が受け付けた出発地から目的地までの経路を、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて探索する。なお、ステップS312からステップS309に戻ってきた場合には、経路探索部29は、特定の信号機の位置を通過しないように設定して、または、特定の信号機の位置を通過し難いようにスコアを調整して経路探索を行う。
(ステップS310)経路探索部29は、探索した経路上に、点灯色を予測していない信号機が存在するかどうか判断する。そして、点灯色を予測していない信号機が存在する場合には、経路探索部29は、探索した経路上にある信号機であって、まだ点灯色を予測していない信号機のうち、出発地に最も近い信号機を識別する信号機識別子と、その信号機の位置に到着する時刻とを特定してステップS311に進み、そうでない場合には、ステップS313に進む。なお、経路探索が2回以上行われた場合には、以前の経路で点灯色を予測した信号機については、点灯色をすでに予測したと判断するものとする。すなわち、再探索で新たに設定された領域についてのみ、この判断が行われてもよい。
(ステップS311)点灯色予測部24は、ステップS310で経路探索部29が特定した信号機識別子で識別される信号機について、ステップS310で経路探索部29が特定した時刻の点灯色を予測する。
(ステップS312)経路探索部29は、予測された点灯色が進行に応じた点灯色であるかどうか判断する。そして、進行に応じた点灯色である場合には、再探索は不要であるためステップS310に戻り、停止に応じた点灯色である場合には、再探索が必要であるためステップS309に戻る。なお、ステップS309に戻った際には、ステップS311で点灯色を予測した信号機の位置を通過しないように設定して、または、その信号機の位置を通過し難いようにスコアを調整して経路探索を行うものとする。
(ステップS313)出力部30は、経路探索部29が探索した経路を出力する。この経路は、停止に応じた点灯色を回避するように探索されたものである。また、この出力は、例えば、地図上への経路の表示であってもよい。そして、ステップS301に戻る。
なお、図8のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終了する。また、ステップS313の探索経路の出力後に、その経路を用いたナビゲーションが行われてもよく、あるいは、そうでなくてもよい。また、第2の車両が探索された経路に応じて移動している場合には、ステップS306において、出力部30は、現在位置から目的地までの経路上に信号機が存在するかどうか判断してもよい。そして、存在する場合には、出力部30は、ステップS307において、現在位置から目的地までの経路上に存在する信号機の点灯色を記憶部23から読み出して出力してもよい。
次に、本実施の形態による情報通信システム100の動作について、具体例を用いて説明する。なお、この具体例では、第1の車載装置1が車両の進行状況に応じて点灯色を取得する場合について説明する。また、進行判断手段16は、第1の車両の速度が20km/h以上の場合に、進行していると判断し、0km/hの場合に、停止していると判断するものとする。また、信号機判断手段17は、現在位置が信号機から80m以内である場合に、その現在位置が信号機に応じた領域に存在すると判断するものとする。また、この具体例では、現在位置を取得する際に、現在位置と共に進行方向をも取得するものとする。その進行方向は、北を0度とし、時計回りに増加する方位角であるとする。
この具体例において、第1の車両が図9で示される位置にいたとする。なお、図9において、三角形が、第1の車両の現在位置を示す図形である。また、図9において、図の上方が北であるとしている。その位置において、第1の車載装置1の現在位置取得部12が新たな現在位置(X101,Y101)と、進行方向「0度」とを取得したとする(ステップS101)。その取得した現在位置等は、信号機識別子取得部14と、点灯色取得部13とに渡される。
信号機識別子取得部14は、現在位置等を受け取ると、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて、その現在位置から進行方向に道路を進んだ先の信号機のある交差点を特定する。その交差点を識別する識別子は、SIG201であるとする。また、その交差点における進行方向は「北」であったとする。すると、信号機識別子取得部14は、交差点の識別子「SIG201」と、北を示す「N」とを用いて、信号機識別子「SIG201_N」を取得し、送信部15に渡す(ステップS102)。
また、点灯色取得部13は、現在位置等を受け取ると、点灯色の取得の処理を行う(ステップS103)。具体的には、点灯色取得部13の信号機判断手段17は、地図情報記憶部11で記憶されている地図情報を用いて、現在位置取得部12から受け取った現在位置から、進行方向に80m進んだ位置までの間に信号機があるかどうか判断する(ステップS201)。この場合には、図9で示されるように信号機が存在するため、信号機判断手段17は、現在位置が信号機に応じた領域に存在すると判断し、進行に関する判断を行う旨の指示を進行判断手段16に渡す。その指示を受け取ると、進行判断手段16は、その時点の第1の車両の速度を、図示しない速度測定部から取得する。その速度は0km/hであったとする。すると、進行判断手段16は、その時点の速度が20km/h未満であるため、進行していないと判断する(ステップS202)。また、その速度は0km/hであるため、停止していると判断し、車両が停止している旨を取得手段18に渡す(ステップS204)。取得手段18は、進行判断手段16から車両が停止している旨を受け取ると、停止の点灯色を示す「R」を取得すると共に、その時点の時刻「10:16:33」を図示しない時計部から取得する(ステップS203)。なお、その時刻は、10時16分33秒を示している。また、点灯色取得部13は、点灯色「R」を取得できたため、点灯色の取得に成功したと判断し(ステップS104)、その点灯色「R」と、時刻「10:16:33」とを送信部15に渡す。点灯色等を受け取ると、送信部15は、それまでに受け取っていた信号機識別子「SIG201_N」と、点灯色「R」と、時刻「10:16:33」とをペイロードに有するパケットを、ブロードキャストで周辺の第2の車載装置2に送信する(ステップS105)。
第1の車両の後方を第2の車両が走行していたとする。すると、第1の車載装置1から送信された点灯色等をペイロードに有するパケットは、その第2の車両に設けられている第2の車載装置2の受信部21で受信される(ステップS301)。そして、そのパケットは、送信部25に渡されると共に、そのパケットのペイロードに含まれる点灯色等は、蓄積部22に渡される。蓄積部22は、点灯色等を受け取ると、その点灯色等が記憶部23で記憶されているかどうか判断する。この場合は、記憶されていなかったとする。すると、蓄積部22は、記憶部23で記憶されていない点灯色等が受信された旨を送信部25に渡すと共に、その点灯色等を対応付けて記憶部23に蓄積する(ステップS302)。図10は、そのようにして記憶部23に蓄積された点灯色等を示す図である。図10において、信号機識別子と、時刻と、点灯色とが対応付けられている。なお、「SIG201_N」と「SIG201_E」とは、同じ交差点に存在する向きの異なる信号機をそれぞれ識別する信号機識別子である。信号機識別子「SIG201_N」は、北向きに進行する車両用の信号機に対応し、信号機識別子「SIG201_E」は、東向きに進行する車両用の信号機に対応する。また、点灯色「R」は、停止に応じた点灯色「赤」であり、点灯色「G」は、進行に応じた点灯色「青」である。なお、図10では、同じ信号機識別子を有するレコードがひとまとまりになるようにしているが、そうでなくてもよいことは言うまでもない。このようにして、第1の車載装置1からの点灯色等の送信と、その点灯色等の蓄積とが繰り返して行われることになる。通常、第1の車載装置1は、1台ではなく、複数台存在している。また、第2の車載装置2は、第1の車載装置1からだけでなく、他の第2の車載装置2からも信号機識別子等を受信することができる。したがって、第2の車載装置2は、各交差点の信号機の点灯色を収集することができる。
また、記憶されていない点灯色等が受信された旨を蓄積部22から受け取ると、送信部25は、信号機識別子等を送信すると判断し(ステップS303)、受信部21から受け取った信号機識別子等を他の第2の車載装置2に送信する(ステップS304)。このようにして、信号機識別子等が第2の車載装置2間で伝送されていくことになる。
また、第1の車両の後方に位置する第2の車両の有する第2の車載装置2の現在位置取得部27が、新たな現在位置(X201,Y201)と、進行方向「0度」とを取得し、出力部30に渡したとする(ステップS305)。出力部30は、現在位置等を受け取ると、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて、その現在位置から進行方向に道路を進んだ先に信号機があるかどうか判断する。この場合には、第1の車載装置1が取得した信号機識別子で識別される信号機が存在するため、出力部30は、信号機が存在すると判断し、その信号機識別子「SIG201_N」を信号機識別子取得部14と同様にして取得する(ステップS306)。そして、出力部30は、その取得した信号機識別子「SIG201_N」を検索キーとして記憶部23を検索し、ヒットしたレコードのうち、最新の時刻に対応する点灯色を読み出す。この場合には、その点灯色は「R」であったとする。すると、出力部30は、表示している地図における信号機識別子「SIG201_N」で識別される信号機の点灯色を「赤」にした図形を表示する(ステップS307)。その結果、図11で示される表示が行われる。なお、図11において、三角形が第2の車両の現在位置であり、その前方の信号機が信号機識別子「SIG201_N」で識別される信号機である。そして、その信号機の右側の信号灯に赤が表示されているものとする。この表示を見た第2の車両の運転者等は、前方の信号機が赤であることを知ることができ、例えば、減速する等の対応を行うことができる。その結果、安全運転を行うことができるようになる。
次に、第2の車両が図11で示される位置に存在する時に、ユーザが第2の車載装置2を操作して目的地を入力し、現在位置から目的地までの経路を探索する旨の指示を入力したとする。すると、地点受付部28は、現在位置取得部27が取得した最新の現在位置である出発地(X301,Y301)と、ユーザが入力した目的地(X401,Y401)とを受け付け(ステップS308)、経路探索部29に渡す。経路探索部29は、出発地等を受け取ると、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて、経路探索を行う(ステップS309)。その結果、図12の破線で示される経路が探索されたとする。すると、経路探索部29は、その経路上に送信要求を送信していない信号機があると判断し(ステップS310)、出発地に最も近い信号機の信号機識別子「SIG201_N」と、その信号機の位置に到着する予測時刻とを特定する。その予測時刻は、「10:16:51」であったとする。その予測時刻と信号機識別子とは、点灯色予測部24に渡される。点灯色予測部24は、その信号機識別子等を受け取ると、その信号機識別子「SIG201_N」を検索キーとして記憶部23を検索し、ヒットしたレコードのうち、最新の1時間に応じた時刻を有するすべてのレコードを読み出す。そして、点灯色予測部24は、まず、点灯色の変化時刻を特定する。図10で示される時刻の場合、例えば、変化時刻「10:15:33」、「10:16:00」、「10:16:30.5」等が特定される。次に、点灯色予測部24は、青の期間候補「30.5」等と、赤の期間候補「27」等とを取得する。なお、その期間候補の単位は秒である。その後、点灯色予測部24は、取得した期間候補を用いて、青の期間、赤の期間をそれぞれ特定する。この具体例では、青の期間が「30」秒となり、赤の期間が「29」秒となったとする。すると、点灯色予測部24は、最新の変化時刻「10:16:30.5」に赤の期間「29」秒を加算した「10:16:59.5」までが赤の期間であるとする。したがって、予測時刻「10:16:51」は赤の期間になるため、点灯色予測部24は、その予測時刻に対応する点灯色「R」を取得し、経路探索部29に渡す(ステップS311)。予測された点灯色「R」を受け取ると、経路探索部29は、予測された点灯色が停止に応じた点灯色「R」であるため、再探索が必要であると判断し(ステップS312)、その信号機識別子「SIG201_N」の信号機を回避するように再度、経路探索を行う(ステップS309)。その結果、図13で示される破線の経路が探索されたとする。すると、経路探索部29は、まだ点灯色の予測を行っていない出発地に最も近い信号機について、再度、点灯色予測部24に点灯色の予測をさせる(ステップS310〜S312)。このような処理が繰り返されることにより、赤信号を回避した経路が探索され、図13で示されるように表示される(ステップS313)。その結果、第2の車両の運転者は、赤信号を回避した目的地までのルートを知ることができ、より早く目的地に到達することができうる。なお、この具体例において再度、経路の探索を行う場合にも、信号機識別子「SIG201_N」で識別される信号機を回避するように経路の探索を行うものとする。
以上のように、本実施の形態による情報通信システム100によれば、第2の車載装置2は、取得された点灯色等を、第1の車載装置1から、または、他の第2の車載装置2経由で受信することができる。したがって、例えば、第2の車両の運転手は、進行方向前方にある信号機の点灯色をあらかじめ取得することができ、安全運転を行うことができるようになり、取得された点灯色を有効活用できる。また、第2の車両の進行方向前方の信号機の点灯色が赤信号である場合には、第2の車両を停止させるための制御を行うこともでき、安全運転に役立つことになる。また、その点灯色を用いて経路探索を行うことによって、例えば、赤信号を回避した経路を探索することも可能となる。
なお、赤信号を回避するように経路を探索する方法は上述した以外の方法であってもよい。例えば、次の実施の形態2で説明するように、出発地から目的地までの種々の経路候補に応じた移動時間を信号機の点灯色を考慮して算出し、その算出した移動時間のうち、最も短い移動時間に応じた経路候補を最終的な経路としてもよい。
また、本実施の形態では、第2の車載装置2が点灯色予測部24を備える場合について説明したが、点灯色の予測を行わない場合には、第2の車載装置2は、点灯色予測部24を備えていなくてもよい。
また、本実施の形態では、点灯色に応じた時刻も第2の車載装置2で管理される場合について説明したが、そうでなくてもよい。第2の車載装置2では、信号機識別子と、その信号機識別子で識別される信号機の点灯色とが管理されるだけであってもよい。その場合には、蓄積部22は、最新に受信された点灯色を特定できるように、信号機識別子と点灯色とを記憶部23に蓄積してもよい。すなわち、蓄積部22は、例えば、最新の点灯色を上書きで蓄積してもよく、最新の点灯色がフラグ等で特定可能となるように蓄積してもよい。そして、出力部30等は、その最新の点灯色に関する出力を行ってもよい。
また、本実施の形態において、送信部25が点灯色等の情報を他の第2の車載装置2に送信する際に、点灯色予測部24が点灯色を予測できる場合、すなわち、予測に用いることができる程度の点灯色の履歴が記憶部23で記憶されている場合には、点灯色の予測結果を含めて送信してもよい。なお、点灯色の予測結果は、例えば、現在の点灯色と、その点灯色が終了する時刻とであってもよく、さらに、将来の点灯色と、その点灯色に応じた期間を示す情報とが含まれていてもよい。ただし、予測結果に将来の点灯色が含まれる場合であっても、その範囲は、あまり大きくないことが好適である。予測する時点と現在時刻との差が大きくなるほど、予測の精度が落ちると考えられるからである。例えば、点灯色予測部24は、5分や10分先ぐらいまでの予測を行ってもよい。そのように、予測結果も含めて送信することで、他の第2の車載装置2は、将来の点灯色をも知ることができるようになる。また、そのように、点灯色の予測結果を含む情報が第2の車載装置2間で転々と伝送される場合には、送信部25は、現在時刻が予測の範囲を越えた場合に、その情報を送信しないようにしてもよい。例えば、10時16分30秒から、10分先までの予測が行われ、10時26分30秒までの点灯色が予測結果に含まれる場合には、送信部25は、現在時刻が10時26分30秒を超えると、その予測結果を含む点灯色等の情報を送信しないようにしてもよい。
(実施の形態2)
本発明の実施の形態2による第2の車載装置2について、図面を参照しながら説明する。本実施の形態による第2の車載装置2は、受信した点灯色等を用いて、距離や時間の予測を行うものである。なお、情報通信システム100における第2の車載装置2以外の構成及び動作は、実施の形態1と同様であり、その説明を省略する。
図14は、本実施の形態による第2の車載装置2の構成を示すブロック図である。本実施の形態による第2の車載装置2は、受信部21と、蓄積部22と、記憶部23と、点灯色予測部24と、送信部25と、地図情報記憶部26と、現在位置取得部27と、地点受付部28と、経路探索部29と、距離取得部31と、移動時間算出部32と、料金取得部33と、出力部34とを備える。なお、距離取得部31、移動時間算出部32、料金取得部33、及び出力部34以外の構成及び動作は、実施の形態1と同様であり、その詳細な説明を省略する。ここで、本実施の形態による経路探索部29は、実施の形態1による経路探索部29と異なり、停止に応じた点灯色を回避する経路探索を行わなくてもよい。すなわち、経路探索部29は、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて、地点受付部28が付け付けた出発地から目的地までの経路探索を行うものであってもよい。また、本実施の形態では、第2の車載装置2が設定される第2の車両がタクシーであるとしている。
距離取得部31は、経路探索部29が探索した経路に応じた距離を取得する。距離取得部31は、例えば、経路探索部29が探索した経路を示す情報を用いて、出発地から目的地までの距離を算出してもよく、または、経路探索部29が経路探索時に経路に応じた距離を取得している場合には、経路探索部29からその距離を取得してもよい。なお、経路に応じた距離の取得方法は、オンライン地図等ですでに公知であり、その説明を省略する。
移動時間算出部32は、経路探索部29が探索した経路に存在する信号機に応じた点灯色を用いて、経路に応じた移動時間を算出する。すなわち、移動時間算出部32は、停止に応じた点灯色によって第2の車両が停止する時間をも考慮した移動時間を算出するものとする。その移動時間の算出で用いられる点灯色は、点灯色予測部24によって予測された点灯色である。なお、移動時間算出部32は、信号機の位置や地点間の移動時間を知るために地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を参照してもよく、または、経路探索部29が探索した経路に信号機や移動時間等の情報も含まれている場合には、その信号機等の情報を用いてもよい。また、移動時間算出部32は、信号機間の移動時間を算出する際に、渋滞情報などを用いて、移動時間を算出してもよい。その渋滞情報などは、例えば、VICS(登録商標)(Vehicle Information and Communication System)等によって提供されたものであってもよく、インターネット等によって提供されたものであってもよく、または、その他の方法によって提供されたものであってもよい。なお、その移動時間の算出方法については、フローチャートを用いて後述する。
料金取得部33は、距離取得部31が取得した距離に応じたタクシー料金を取得する。また、料金取得部33は、移動時間算出部32が算出した移動時間に応じたタクシー料金も取得する。通常、距離に応じたタクシー料金は、距離が長くなるほど高くなる料金である。また、通常、移動時間に応じたタクシー料金も、移動時間が長くなるほど高くなる料金である。料金取得部33は、距離や移動時間を引数とする増加関数を用いて距離に応じたタクシー料金や、移動時間に応じたタクシー料金を算出してもよく、距離や移動時間と、タクシー料金とを対応付ける情報、例えば、テーブル等を用いて距離や移動時間に応じたタクシー料金を取得してもよい。
出力部34は、料金取得部33が取得した、距離に応じたタクシー料金及び移動時間に応じたタクシー料金を出力する。また、出力部34は、実施の形態1による出力部30と同様に、受信部21が受信した点灯色等に関するそれ以外の出力を行ってもよい。ここで、この出力は、例えば、表示デバイス(例えば、CRTや液晶ディスプレイなど)への表示でもよく、所定の機器への通信回線を介した送信でもよく、スピーカによる音声出力でもよく、記録媒体への蓄積でもよく、他の構成要素への引き渡しでもよい。なお、出力部34は、出力を行うデバイス(例えば、表示デバイスや通信デバイスなど)を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、出力部34は、ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは、それらのデバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
次に、本実施の形態による第2の車載装置2の動作について、図15のフローチャートを用いて説明する。なお、図15のフローチャートにおいて、ステップS301〜S307は、実施の形態1における図8のフローチャートと同様であり、その説明を省略する。
(ステップS401)地点受付部28は、出発地と目的地とを受け付けたかどうか判断する。そして、出発地等を受け付けた場合には、ステップS402に進み、そうでない場合には、ステップS301に戻る。
(ステップS402)経路探索部29は、地点受付部28が受け付けた出発地から目的地までの経路を、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて探索する。なお、探索された経路は、図示しない記録媒体で記憶されてもよい。
(ステップS403)距離取得部31は、探索された経路に応じた距離を取得する。なお、取得された距離は、図示しない記録媒体で記憶されてもよい。
(ステップS404)移動時間算出部32は、探索された経路上に、点灯色を予測していない信号機が存在するかどうか判断する。そして、点灯色を予測していない信号機が存在する場合には、移動時間算出部32は、探索された経路上にある信号機であって、まだ点灯色を予測していない信号機のうち、出発地に最も近い信号機を識別する信号機識別子を特定する。そして、ステップS405に進む。一方、点灯色を予測していない信号機が存在しない場合には、ステップS408に進む。
(ステップS405)移動時間算出部32は、それまでに移動時間を算出していない経路の範囲のうち、出発地に最も近い位置からステップS404で信号機識別子を特定した信号機の位置までの移動時間を算出し、その移動時間をそれまでに算出している移動時間に加算する。
(ステップS406)点灯色予測部24は、ステップS404で特定された信号機識別子で識別される信号機について、現在時刻にステップS405で算出された移動時間を加算した予測時刻の点灯色と、その点灯色の継続時間とを予測する。なお、その予測時刻は、ステップS404で特定された信号機識別子で識別される信号機の位置に第2の車両が到着する時刻である。また、予測された点灯色や継続時間は、図示しない記録媒体で記憶されてもよい。また、予測した点灯色が青である場合には、点灯色予測部24は、継続時間を予測しなくてもよい。
(ステップS407)移動時間算出部32は、予測された点灯色が赤である場合には、予測された点灯色の継続時間を、移動時間に加算する。一方、移動時間算出部32は、予測された点灯色が青である場合には、移動時間の加算を行わない。なお、点灯色が青である場合には、移動時間に0が加算されると考えてもよい。そして、ステップS404に戻る。
(ステップS408)移動時間算出部32は、それまでに移動時間を算出していない経路の範囲のすべて、すなわち、目的地までの移動時間を算出し、その移動時間をそれまでに算出している移動時間に加算する。この加算の後の移動時間がすべての経路の移動時間、すなわち、最終的な移動時間である。
(ステップS409)料金取得部33は、ステップS403で取得された距離に応じたタクシー料金と、ステップS408で算出された移動時間に応じたタクシー料金とを取得する。
(ステップS410)出力部34は、ステップS409で取得された距離に応じたタクシー料金と、移動時間に応じたタクシー料金とを出力する。そして、ステップS301に戻る。
なお、図15のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終了する。また、ステップS410では、両料金のうち、高い方の料金のみを出力してもよい。
次に、本実施の形態による情報通信システム100の動作について、具体例を用いて説明する。なお、この具体例では、前述のように、点灯色予測部24が、予測時間に対応する点灯色と、その点灯色の継続時間とを予測するものとする。
タクシーである第2の車両が図12の三角形で示される位置で客を乗せたとする。すると、そのタクシーの運転手は、第2の車載装置2を操作して、客から聞いた目的地を入力する。そして、地点受付部28は、現在位置取得部27が取得した最新の現在位置である出発地と、運転手が入力した目的地とを受け付け(ステップS401)、経路探索部29に渡す。経路探索部29は、出発地等を受け取ると、地図情報記憶部26で記憶されている地図情報を用いて、経路探索を行う(ステップS402)。その結果、図12の破線で示される経路が探索されたとする。経路探索部29は、探索した経路を距離取得部31と移動時間算出部32とに渡す。経路を受け取ると、距離取得部31は、その経路の出発地から目的地までの距離を取得し、料金取得部33に渡す(ステップS403)。また、移動時間算出部32は、経路を受け取ると、その経路上に送信要求を送信していない信号機があると判断し(ステップS404)、出発地に最も近い信号機の信号機識別子「SIG201_N」を特定し、現在位置からその信号機の位置までの移動時間を算出する。移動時間は15秒であったとする。すると、移動時間算出部32は、全移動時間に、その移動時間15秒を代入する(ステップS405)。その結果、信号機識別子「SIG201_N」で識別される信号機までの全移動時間は15秒となる。また、その時点の現在時刻が10時16分36秒であったとする。すると、移動時間算出部32は、現在時刻に全移動時間を加算した予測時刻「10:16:51」と、信号機識別子「SIG201_N」とを点灯色予測部24に渡す。予測時刻等を受け取ると、点灯色予測部24は、点灯色を予測する。なお、この予測の処理は、実施の形態1の具体例と同様であり、その詳細な説明を省略する。この具体例では、前述のように、継続時間、すなわち、赤の期間の終点である「10:16:59.5」から予測時刻「10:16:51」を減算した8.5秒も点灯色予測部24によって取得されるものとする。そして、予測された点灯色「R」、及び継続時間「8.5」が移動時間算出部32に渡される(ステップS406)。予測された点灯色等を受け取ると、移動時間算出部32は、予測された点灯色がRであるため、全移動時間に、継続時間を加算する(ステップS407)。その結果、全移動時間は、23.5秒となる。その後、移動時間算出部32は、経路上に次の信号機があると判断し(ステップS404)、信号機識別子「SIG201_N」で識別される信号機から、次の信号機までの移動時間を算出して、全移動時間に加算する(ステップS405)。このような処理が繰り返されることによって、経路上の最後の信号機までの全移動時間が算出されることになる(ステップS404〜S407)。なお、経路上の最後の信号機までの全移動時間が算出されると、移動時間算出部32は、その最後の信号機の位置から目的地までの移動時間を算出して全移動時間に加算する(ステップS408)。その加算後の全移動時間が、出発地から目的地までの最終的な移動時間となる。そして、その最終的な移動時間は、料金取得部33に渡される。移動時間を受け取ると、料金取得部33は、それまでに受け取っていた距離に応じたタクシー料金と、移動時間に応じたタクシー料金とを取得し、それらを出力部34に渡す(ステップS409)。出力部34は、料金取得部33から受け取った各タクシー料金を表示する(ステップS410)。この具体例では、例えば、次のような表示がなされる。
距離に応じた料金:1200円
時間に応じた料金:1000円
したがって、この場合には、渋滞等がなければ、距離に応じた料金である1200円が最終的なタクシー料金になることを乗客は知ることができる。
なお、この具体例では、出力部34が距離に応じたタクシー料金と、時間に応じたタクシー料金との両方を表示する場合について説明したが、そうでなくてもよい。両料金のうち、高い方のみを料金の予測結果として表示してもよい。
また、距離に応じたタクシー料金や、移動時間に応じたタクシー料金は、タクシーである第2の車両の移動に応じて再度、取得され、更新されてもよい。例えば、経路探索部29が探索した経路以外を第2の車両が通行した場合には、それに応じて距離に応じた料金が変わりうる。また、予測に失敗した赤信号や、想定外の渋滞等によって、移動時間の予測がずれることがありうる。そのため、出発地から目的地までの間であっても、それまでの実移動距離、実移動時間と、そこから目的地までの予測移動距離、予測移動時間とを用いて、出発地から目的地までの距離や移動時間を取得することによって、より正確な距離や時間を取得することができるようになる。したがって、距離取得部31は、出発地から目的地までの間であっても、出発地から現在位置までの実移動距離と、現在位置から目的地までの経路探索結果に応じた予測移動距離とを用いて、出発地から目的地までの経路に応じた距離を更新してもよい。また、移動時間算出部32は、出発地から目的地までの間であっても、出発地から現在位置までの実移動時間と、現在位置から目的地までの経路探索結果に応じた予測移動時間とを用いて、出発地から目的地までの経路に応じた移動時間を更新してもよい。また、料金取得部33は、そのようにして更新された距離や移動時間を用いて、新たなタクシー料金を取得してもよい。そして、出力部34は、そのようにして新たに取得されたタクシー料金を出力することによって、タクシー料金の更新を行ってもよい。
以上のように、本実施の形態による情報通信システム100によれば、第2の車両がタクシーである場合に、距離に応じた料金と、時間に応じた料金との両方を出力することができる。したがって、例えば、タクシーの乗客は、より正確な予測料金を知ることができるようになる。また、例えば、距離に応じた料金と、時間に応じた料金との両方が表示される場合において、タクシーが目的地の近くにおいて赤信号で止まっており、時間に応じた料金の方が、距離に応じた料金よりも高く予測されている場合には、乗客は、その場所で降車することによって、タクシー料金を節約することもできうる。
なお、本実施の形態では、第2の車両がタクシーであり、第2の車載装置2がタクシー料金を取得する場合について説明したが、そうでなくてもよい。第2の車両は、タクシーでなくてもよい。その場合に、第2の車載装置2は、料金取得部33を備えていなくてもよく、出力部34は、移動時間算出部32が算出した移動時間に関する出力を行ってもよく、距離取得部31が取得した距離に関する出力を行ってもよい。また、出力部34が、距離と移動時間とのいずれか一方のみに関する出力を行う場合には、第2の車載装置2は、距離取得部31または移動時間算出部32の一方を備えていなくてもよい。
また、上記各実施の形態において、第2の車載装置2が、受信した点灯色等を他の第2の車載装置2に送信する送信部25を備える場合について説明したが、そうでなくてもよい。すなわち、第2の車載装置2は、送信部25を備えておらず、点灯色等を取得する第1の車載装置1からのみ点灯色等を受信するものであってもよい。
また、上記各実施の形態において、第1の車載装置1と第2の車載装置2とが異なる構成である場合について説明したが、そうでなくてもよい。第1の車載装置1と第2の車載装置2とは、点灯色等を取得して送信する構成と、点灯色等を受信し、それを転送すると共に、その点灯色等に関する出力を行う構成との両方を備えていてもよい。両装置の構成を備える車載装置は、第1の車載装置1の構成と第2の車載装置2の構成とを結合したものとなりうるが、地図情報記憶部11,26や、現在位置取得部12,27などのように、両装置に共通している構成については、1個の構成を用いるようにしてもよい。
また、上記各実施の形態において、各処理または各機能は、単一の装置または単一のシステムによって集中処理されることによって実現されてもよく、あるいは、複数の装置または複数のシステムによって分散処理されることによって実現されてもよい。
また、上記各実施の形態において、各構成要素間で行われる情報の受け渡しは、例えば、その情報の受け渡しを行う2個の構成要素が物理的に異なるものである場合には、一方の構成要素による情報の出力と、他方の構成要素による情報の受け付けとによって行われてもよく、あるいは、その情報の受け渡しを行う2個の構成要素が物理的に同じものである場合には、一方の構成要素に対応する処理のフェーズから、他方の構成要素に対応する処理のフェーズに移ることによって行われてもよい。
また、上記各実施の形態において、各構成要素が実行する処理に関係する情報、例えば、各構成要素が受け付けたり、取得したり、選択したり、生成したり、送信したり、受信したりした情報や、各構成要素が処理で用いるしきい値や数式、アドレス等の情報等は、上記説明で明記していなくても、図示しない記録媒体において、一時的に、あるいは長期にわたって保持されていてもよい。また、その図示しない記録媒体への情報の蓄積を、各構成要素、あるいは、図示しない蓄積部が行ってもよい。また、その図示しない記録媒体からの情報の読み出しを、各構成要素、あるいは、図示しない読み出し部が行ってもよい。
また、上記各実施の形態において、各構成要素等で用いられる情報、例えば、各構成要素が処理で用いるしきい値やアドレス、各種の設定値等の情報がユーザによって変更されてもよい場合には、上記説明で明記していなくても、ユーザが適宜、それらの情報を変更できるようにしてもよく、あるいは、そうでなくてもよい。それらの情報をユーザが変更可能な場合には、その変更は、例えば、ユーザからの変更指示を受け付ける図示しない受付部と、その変更指示に応じて情報を変更する図示しない変更部とによって実現されてもよい。その図示しない受付部による変更指示の受け付けは、例えば、入力デバイスからの受け付けでもよく、通信回線を介して送信された情報の受信でもよく、所定の記録媒体から読み出された情報の受け付けでもよい。
また、上記各実施の形態において、第1の車載装置1、第2の車載装置2に含まれる2以上の構成要素が通信デバイスや入力デバイス等を有する場合に、2以上の構成要素が物理的に単一のデバイスを有してもよく、あるいは、別々のデバイスを有してもよい。
また、上記各実施の形態において、各構成要素は専用のハードウェアにより構成されてもよく、あるいは、ソフトウェアにより実現可能な構成要素については、プログラムを実行することによって実現されてもよい。例えば、ハードディスクや半導体メモリ等の記録媒体に記録されたソフトウェア・プログラムをCPU等のプログラム実行部が読み出して実行することによって、各構成要素が実現され得る。その実行時に、プログラム実行部は、記憶部や記録媒体にアクセスしながらプログラムを実行してもよい。なお、上記各実施の形態における第1の車載装置1を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラムは、信号機の位置を含む地図に関する情報である地図情報が記憶される地図情報記憶部にアクセス可能なコンピュータを、現在位置を取得する現在位置取得部、地図情報を用いて、現在位置取得部が取得した現在位置に応じた信号機を識別する信号機識別子を取得する信号機識別子取得部、信号機の点灯色を取得する点灯色取得部、信号機識別子取得部が取得した信号機識別子と、信号機識別子で識別される信号機の点灯色とを送信する送信部として機能させるためのプログラムである。
また、上記各実施の形態における第2の車載装置2を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、信号機を識別する信号機識別子、及び信号機識別子で識別される信号機の点灯色を受信する受信部、受信部が受信した信号機識別子及び点灯色を対応付けて蓄積する蓄積部、蓄積部が蓄積した信号機識別子及び点灯色を用いて、点灯色に関する出力を行う出力部として機能させるためのプログラムである。
なお、上記プログラムにおいて、上記プログラムが実現する機能には、ハードウェアでしか実現できない機能は含まれない。例えば、情報を取得する取得部や、情報を受信する受信部、情報を送信する送信部、情報を出力する出力部などにおけるモデムやインターフェースカードなどのハードウェアでしか実現できない機能は、上記プログラムが実現する機能には少なくとも含まれない。
また、このプログラムは、サーバなどからダウンロードされることによって実行されてもよく、所定の記録媒体(例えば、CD−ROMなどの光ディスクや磁気ディスク、半導体メモリなど)に記録されたプログラムが読み出されることによって実行されてもよい。また、このプログラムは、プログラムプロダクトを構成するプログラムとして用いられてもよい。
また、このプログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であってもよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
図16は、上記プログラムを実行して、上記各実施の形態による第1の車載装置1、第2の車載装置2を実現するコンピュータの外観の一例を示す模式図である。上記各実施の形態は、コンピュータハードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムによって実現されうる。
図16において、コンピュータシステム900は、CD−ROMドライブ905、FD(Floppy(登録商標) Disk)ドライブ906を含むコンピュータ901と、キーボード902と、マウス903と、モニタ904とを備える。
図17は、コンピュータシステム900の内部構成を示す図である。図17において、コンピュータ901は、CD−ROMドライブ905、FDドライブ906に加えて、MPU(Micro Processing Unit)911と、ブートアッププログラム等のプログラムを記憶するためのROM912と、MPU911に接続され、アプリケーションプログラムの命令を一時的に記憶すると共に、一時記憶空間を提供するRAM913と、アプリケーションプログラム、システムプログラム、及びデータを記憶するハードディスク914と、MPU911、ROM912等を相互に接続するバス915とを備える。なお、コンピュータ901は、LANやWAN等への接続を提供する図示しないネットワークカードを含んでいてもよい。
コンピュータシステム900に、上記各実施の形態による第1の車載装置1、第2の車載装置2の機能を実行させるプログラムは、CD−ROM921、またはFD922に記憶されて、CD−ROMドライブ905、またはFDドライブ906に挿入され、ハードディスク914に転送されてもよい。これに代えて、そのプログラムは、図示しないネットワークを介してコンピュータ901に送信され、ハードディスク914に記憶されてもよい。プログラムは実行の際にRAM913にロードされる。なお、プログラムは、CD−ROM921やFD922、またはネットワークから直接、ロードされてもよい。
プログラムは、コンピュータ901に、上記各実施の形態による第1の車載装置1、第2の車載装置2の機能を実行させるオペレーティングシステム(OS)、またはサードパーティプログラム等を必ずしも含んでいなくてもよい。プログラムは、制御された態様で適切な機能やモジュールを呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいてもよい。コンピュータシステム900がどのように動作するのかについては周知であり、詳細な説明は省略する。
また、本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。