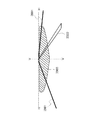JP5855258B2 - 車両用前照灯装置 - Google Patents
車両用前照灯装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5855258B2 JP5855258B2 JP2014534184A JP2014534184A JP5855258B2 JP 5855258 B2 JP5855258 B2 JP 5855258B2 JP 2014534184 A JP2014534184 A JP 2014534184A JP 2014534184 A JP2014534184 A JP 2014534184A JP 5855258 B2 JP5855258 B2 JP 5855258B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light
- mirror
- axis
- rotation
- incident
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 158
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 128
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 66
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 7
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 19
- 230000006870 function Effects 0.000 description 15
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 10
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 10
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 10
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 10
- 230000009471 action Effects 0.000 description 9
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 9
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 9
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 5
- 210000000887 face Anatomy 0.000 description 5
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 201000009310 astigmatism Diseases 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 238000005549 size reduction Methods 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- 230000009194 climbing Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000005401 electroluminescence Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 1
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/20—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
- F21S41/25—Projection lenses
- F21S41/26—Elongated lenses
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62J—CYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
- B62J6/00—Arrangement of optical signalling or lighting devices on cycles; Mounting or supporting thereof; Circuits therefor
- B62J6/02—Headlights
- B62J6/022—Headlights specially adapted for motorcycles or the like
- B62J6/023—Headlights specially adapted for motorcycles or the like responsive to the lean angle of the cycle, e.g. changing intensity or switching sub-lights when cornering
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62J—CYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
- B62J6/00—Arrangement of optical signalling or lighting devices on cycles; Mounting or supporting thereof; Circuits therefor
- B62J6/02—Headlights
- B62J6/022—Headlights specially adapted for motorcycles or the like
- B62J6/026—Headlights specially adapted for motorcycles or the like characterised by the structure, e.g. casings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/10—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
- F21S41/14—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
- F21S41/141—Light emitting diodes [LED]
- F21S41/143—Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being parallel to the optical axis of the illuminating device
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/20—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
- F21S41/25—Projection lenses
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/20—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
- F21S41/25—Projection lenses
- F21S41/275—Lens surfaces, e.g. coatings or surface structures
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/30—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by reflectors
- F21S41/32—Optical layout thereof
- F21S41/36—Combinations of two or more separate reflectors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/60—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution
- F21S41/63—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on refractors, filters or transparent cover plates
- F21S41/635—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on refractors, filters or transparent cover plates by moving refractors, filters or transparent cover plates
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/60—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution
- F21S41/67—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on reflectors
- F21S41/675—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on reflectors by moving reflectors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/30—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by reflectors
- F21S41/32—Optical layout thereof
- F21S41/36—Combinations of two or more separate reflectors
- F21S41/365—Combinations of two or more separate reflectors successively reflecting the light
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Planar Illumination Modules (AREA)
Description
図1は、この発明を実施するための実施の形態1に係る車両用前照灯装置100の構成を概略的に示すものである。ここで、図1(A)は、車両用前照灯装置100を側面から見た図である。図1(B)は、車両用前照灯装置100を上から見た図である。図1では、車両用前照灯装置100の構成要素を破線で囲んで示している。
実施の形態1に係る車両用前照灯装置100は、配光パターン形成部30の前にコリメートレンズ20を設けて、平行光を配光パターン形成部30に入射させていた。また、ダブプリズム40とプロジェクションレンズ60とを車体のバンク角kに応じて回転させていた。実施の形態2に係る車両用前照灯装置110は、コリメートレンズ20の代わりに正のパワーを有するコンデンサレンズ200を設けている。また、車両用前照灯装置110は、プロジェクションレンズ60を設けない構成をしている。
実施の形態1に係る車両用前照灯装置100は、配光パターン形成部30の前にコリメートレンズ20を設けて、平行光を配光パターン形成部30に入射させていた。また、ダブプリズム40とプロジェクションレンズ60とを車体のバンク角kに応じて回転させていた。実施の形態3に係る車両用前照灯装置120は、配光パターン形成部30の代わりに変形ダブプリズム41を採用している。また、車両用前照灯装置120は、プロジェクションレンズ60を設けない構成をしている。
実施の形態1では、ダブプリズム40とプロジェクションレンズ60とを車体のバンク角kに応じて回転させ、所望の配光を得ていた。実施の形態4では、ダブプリズム40の代わりにローテーションミラー80を採用する。実施の形態1で示した構成要素と同じ構成要素には、同一の符号を付し、その説明を省略する。実施の形態1と構成要素は、光源11、コリメートレンズ20、配光パターン形成部30、プロジェクションレンズ60、回転機構50、制御回路70及び車体傾斜検出部75である。なお、回転機構50の歯車502は、ローテーションミラー80の回転軸805に取り付けられている。
実施の形態5では、実施の形態2のダブプリズム40の代わりに実施の形態4で示したローテーションミラー80を設ける構成を持つ。実施の形態2で示した構成要素と同じ構成要素には、同一の符号を付し、その説明を省略する。実施の形態2と構成要素は、光源11、コンデンサレンズ200、配光パターン形成部30、回転機構50、制御回路70及び車体傾斜検出部75である。なお、回転機構50の歯車502は、ローテーションミラー80の回転軸805に取り付けられている。
実施の形態6では、実施の形態3の変形ダブプリズム41の代わりに変形ローテーションミラー81を採用する。実施の形態3で示した構成要素と同じ構成要素には、同一の符号を付し、その説明を省略する。実施の形態3と構成要素は、光源11、コリメートレンズ20、回転機構50、制御回路70及び車体傾斜検出部75である。なお、回転機構50の歯車502は、変形ローテーションミラー81の回転軸815に取り付けられている。
Claims (14)
- 光を放射する光源と、
入射面と反射面と出射面とを有し、前記入射面に入射された前記光の進行方向を前記入射面で変更して前記反射面に導き、前記反射面に導かれた前記光を前記反射面で反射して前記出射面に導き、前記出射面に導かれた前記光の進行方向を前記出射面で変更して出射する光学部品と、
前記入射面及び前記出射面を通り、前記入射面に入射する直前の前記光の中心光線に平行な直線を、回転軸として前記光学部品を回転可能に支持する回転機構と
を備え、
前記入射面は、前記反射面に対して傾斜した面であり、
前記出射面は、前記反射面に対して傾斜したトロイダル面であり、
前記入射面と前記出射面とは、互いに対向する位置に配置され、前記入射面と前記出射面との間の間隔は、前記反射面から離れるにつれて短くなる
車両用前照灯装置。 - 前記回転機構は、前記車両用前照灯装置が備えられた車体のバンク角に応じて前記光学部品を回転させる
請求項1に記載の車両用前照灯装置。 - 前記回転機構は、前記車体のバンク方向と逆方向に前記光学部品を回転させる請求項2に記載の車両用前照灯装置。
- 前記回転機構は、前記光学部品を前記バンク角の半分の回転量で回転させる請求項2又は3に記載の車両用前照灯装置。
- 前記回転軸は、前記反射面に平行な平面と前記入射面との交線に垂直で、前記反射面に平行な直線である請求項1から4のいずれか1項に記載の車両用前照灯装置。
- 前記光学部品は、ダブプリズムであり、
前記入射面は、前記ダブプリズムの台形形状の1つの脚を含む面であり、
前記出射面は、前記ダブプリズムの台形形状の他の脚を含む面であり、
前記反射面は、前記入射面及び前記出射面と鋭角をなす面である請求項1から5のいずれか1項に記載の車両用前照灯装置。 - 光を放射する光源と、
入射面と反射面と出射面とを有し、前記入射面に入射された前記光の進行方向を前記入射面で変更して前記反射面に導き、前記反射面に導かれた前記光を前記反射面で反射して前記出射面に導き、前記出射面に導かれた前記光の進行方向を前記出射面で変更して出射する光学部品と、
前記入射面及び前記出射面を通り、前記入射面に入射する直前の前記光の中心光線に平行な直線を回転軸として前記光学部品を回転可能に支持する回転機構と
を備え、
前記入射面は、前記反射面に対して傾斜した第1のミラー面であり、
前記出射面は、前記反射面に対して傾斜したトロイダル面である第2のミラー面であり、
前記反射面は、第3のミラー面であり、
前記光学部品は、前記第1のミラー面を有する第1のミラー、前記第2のミラー面を有する第2のミラー及び前記第3のミラー面を有する第3のミラーを備え、前記回転軸を中心に回転可能なローテーションミラーであり、
前記第1のミラー及び前記第2のミラーは、前記第1のミラー面の反対側の面である第1の裏面と前記第2のミラー面の反対側の面である第2の裏面とが互いに対向するように配置され、前記第1の裏面と前記第2の裏面との間の間隔は、前記第3のミラー面から離れるにつれて長くなる
車両用前照灯装置。 - 前記出射面から出射される光束を前記反射面に平行な平面で切断した平面上の発散角が、前記出射面から出射される前記光束を前記反射面に垂直で前記光束の中心光線を含む平面で切断した平面上の発散角よりも小さい請求項1から7のいずれか1項に記載の車両用前照灯装置。
- 前記反射面に垂直で光束の中心光線を含む平面で切断した平面上における前記出射面の負のパワーが前記反射面から遠ざかるほど小さくなる請求項1から8のいずれか1項に記載の車両用前照灯装置。
- 前記光源から出射された前記光を配光パターンを有するパターン光に形成し、前記パターン光を前記入射面に向けて出射する配光パターン形成部をさらに備える請求項1から9のいずれか1項に記載の車両用前照灯装置。
- 前記光源から出射された前記光を平行光に変換して前記配光パターン形成部に向けて出射するコリメートレンズをさらに備える請求項10に記載の車両用前照灯装置。
- 前記光源と前記配光パターン形成部との間に、コンデンサレンズをさらに備え、
前記コンデンサレンズを透過した光束の前記車両用前照灯装置が備えられた車体の垂直方向における発散角が前記車体の水平方向における発散角よりも小さい請求項10に記載の車両用前照灯装置。 - 前記光学部品から出射された前記光を拡大して出射するプロジェクションレンズをさらに備え、
前記回転機構は、前記光源の発光面の中心と前記プロジェクションレンズの中心とを結ぶ直線で示される光軸を前記回転軸として前記プロジェクションレンズを回転可能に支持する請求項1から12のいずれか1項に記載の車両用前照灯装置。 - 前記光学部品から出射された前記光を拡大して出射するプロジェクションレンズをさらに備え、
前記回転機構は、前記光源の発光面の中心と前記プロジェクションレンズの中心とを結ぶ直線で示される光軸を前記回転軸として前記プロジェクションレンズを回転可能に支持し、前記プロジェクションレンズを前記車両用前照灯装置が備えられた車体のバンク方向と逆方向に回転させる請求項1から12のいずれか1項に記載の車両用前照灯装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014534184A JP5855258B2 (ja) | 2012-09-07 | 2013-09-03 | 車両用前照灯装置 |
Applications Claiming Priority (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012197486 | 2012-09-07 | ||
| JP2012197486 | 2012-09-07 | ||
| JP2013114395 | 2013-05-30 | ||
| JP2013114395 | 2013-05-30 | ||
| JP2014534184A JP5855258B2 (ja) | 2012-09-07 | 2013-09-03 | 車両用前照灯装置 |
| PCT/JP2013/005186 WO2014038177A1 (ja) | 2012-09-07 | 2013-09-03 | 車両用前照灯装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP5855258B2 true JP5855258B2 (ja) | 2016-02-09 |
| JPWO2014038177A1 JPWO2014038177A1 (ja) | 2016-08-08 |
Family
ID=50236806
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2014534184A Active JP5855258B2 (ja) | 2012-09-07 | 2013-09-03 | 車両用前照灯装置 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9689549B2 (ja) |
| EP (1) | EP2894086B1 (ja) |
| JP (1) | JP5855258B2 (ja) |
| CN (1) | CN104602997B (ja) |
| WO (1) | WO2014038177A1 (ja) |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2907732B1 (en) | 2012-10-11 | 2018-01-31 | Mitsubishi Electric Corporation | Vehicle headlight device |
| JP6160206B2 (ja) * | 2013-04-23 | 2017-07-12 | 三菱電機株式会社 | 光軸調整装置 |
| JP5858185B2 (ja) * | 2014-06-13 | 2016-02-10 | ウシオ電機株式会社 | 光投射装置および車載用前照灯 |
| WO2017122629A1 (ja) | 2016-01-13 | 2017-07-20 | 三菱電機株式会社 | 前照灯モジュール及び前照灯装置 |
| US10539287B2 (en) * | 2016-01-13 | 2020-01-21 | Mitsubishi Electric Corporation | Headlight module and headlight device |
| FR3056685B1 (fr) * | 2016-09-28 | 2021-01-15 | Valeo Vision | Support monobloc pour dispositif lumineux avec matrice de micro-miroirs |
| CN108692267A (zh) * | 2017-03-03 | 2018-10-23 | 长城汽车股份有限公司 | 前照灯的调节机构 |
| WO2019039051A1 (ja) * | 2017-08-24 | 2019-02-28 | 株式会社小糸製作所 | 車両用灯具 |
| JP7002255B2 (ja) * | 2017-09-08 | 2022-02-04 | スタンレー電気株式会社 | 車両用灯具 |
| WO2019067550A1 (en) * | 2017-09-26 | 2019-04-04 | Mark Fuller | SOLAR TUBE |
| CN112166366B (zh) * | 2018-06-04 | 2022-12-06 | 三菱电机株式会社 | 光照射装置 |
| US11493365B2 (en) * | 2018-08-28 | 2022-11-08 | Mitsubishi Electric Corporation | Light irradiation device |
| WO2020216206A1 (zh) * | 2019-04-25 | 2020-10-29 | 苏州欧普照明有限公司 | 一种配光组件和照明装置 |
| US10823358B1 (en) * | 2019-12-19 | 2020-11-03 | Valeo Vision | Device and method of directing a light via rotating prisms |
| EP3971470B1 (de) * | 2020-09-16 | 2024-03-06 | ZKW Group GmbH | Hochauflösender fahrzeugscheinwerfer |
| CN113091013B (zh) * | 2021-03-16 | 2022-11-01 | 苏州海栎森视觉有限公司 | 一种通过脉冲调制控制的adb透镜组 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06261242A (ja) * | 1993-03-03 | 1994-09-16 | Mitsubishi Electric Corp | 旋回撮像装置 |
| JPH09277974A (ja) * | 1996-04-15 | 1997-10-28 | Hideo Hayashi | 照射範囲を一定に保つ二輪車用前照灯 |
| JP2001347977A (ja) * | 2000-06-06 | 2001-12-18 | Kawasaki Heavy Ind Ltd | 自動二輪車用ヘッドランプ装置 |
| JP2003086009A (ja) * | 2001-09-07 | 2003-03-20 | Stanley Electric Co Ltd | 車両用前照灯 |
| JP2005228502A (ja) * | 2004-02-10 | 2005-08-25 | Koito Mfg Co Ltd | 車両用灯具ユニット |
| JP2008151642A (ja) * | 2006-12-18 | 2008-07-03 | Toyota Motor Corp | 測色装置 |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6251101A (ja) | 1985-08-02 | 1987-03-05 | スタンレー電気株式会社 | 二輪車用前照灯装置 |
| JPH0762962B2 (ja) | 1986-12-20 | 1995-07-05 | 株式会社小糸製作所 | 車輌用前照灯 |
| JPS63312280A (ja) | 1987-06-12 | 1988-12-20 | スタンレー電気株式会社 | 二輪車用ヘッドランプ |
| JPH01173095U (ja) * | 1988-05-27 | 1989-12-07 | ||
| JP4078151B2 (ja) | 2001-08-24 | 2008-04-23 | スタンレー電気株式会社 | 車両用前照灯 |
| EP1288069B1 (en) | 2001-08-24 | 2009-12-16 | Stanley Electric Co., Ltd. | Vehicle headlight |
| JP4054594B2 (ja) | 2002-04-04 | 2008-02-27 | 日東光学株式会社 | 光源装置及びプロジェクタ |
| AT500893B1 (de) * | 2004-10-14 | 2006-11-15 | Zizala Lichtsysteme Gmbh | Fahrzeugscheinwerfer |
| DE102005014754A1 (de) * | 2005-03-31 | 2006-10-05 | Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH | KFZ-Scheinwerfer |
| JP4523509B2 (ja) | 2005-07-29 | 2010-08-11 | 株式会社小糸製作所 | 灯具の照射方向制御装置 |
| DE102005037764B4 (de) | 2005-08-10 | 2008-07-03 | Carl Zeiss Jena Gmbh | Anordnung zur homogenen Beleuchtung eines Feldes |
| JP2007333525A (ja) | 2006-06-14 | 2007-12-27 | Samsung Yokohama Research Institute Co Ltd | 距離測定装置 |
| US7674022B2 (en) * | 2006-11-09 | 2010-03-09 | Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha | Motorcycle headlight device |
| DE102008019125A1 (de) * | 2008-04-16 | 2009-10-22 | Volkswagen Ag | Fahrzeugleuchte |
| JP2010122485A (ja) | 2008-11-20 | 2010-06-03 | Seiko Epson Corp | 投射型表示装置 |
| JP2010164855A (ja) | 2009-01-16 | 2010-07-29 | Olympus Corp | ロッドインテグレータ、及びそれを備えた照明系及び投影装置 |
| DE202009011500U1 (de) * | 2009-08-20 | 2010-12-30 | Arnold & Richter Cine Technik Gmbh & Co. Betriebs Kg | Optisches System für eine LED-Leuchte |
| JP5535663B2 (ja) * | 2010-01-14 | 2014-07-02 | 株式会社小糸製作所 | 車両用ヘッドランプ |
| FR2963922B1 (fr) | 2010-08-18 | 2014-08-29 | Quality Electronics Design S A | Phare frontal pour vehicule a deux roues |
-
2013
- 2013-09-03 JP JP2014534184A patent/JP5855258B2/ja active Active
- 2013-09-03 US US14/419,820 patent/US9689549B2/en active Active
- 2013-09-03 CN CN201380046382.5A patent/CN104602997B/zh active Active
- 2013-09-03 WO PCT/JP2013/005186 patent/WO2014038177A1/ja active Application Filing
- 2013-09-03 EP EP13835162.2A patent/EP2894086B1/en active Active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06261242A (ja) * | 1993-03-03 | 1994-09-16 | Mitsubishi Electric Corp | 旋回撮像装置 |
| JPH09277974A (ja) * | 1996-04-15 | 1997-10-28 | Hideo Hayashi | 照射範囲を一定に保つ二輪車用前照灯 |
| JP2001347977A (ja) * | 2000-06-06 | 2001-12-18 | Kawasaki Heavy Ind Ltd | 自動二輪車用ヘッドランプ装置 |
| JP2003086009A (ja) * | 2001-09-07 | 2003-03-20 | Stanley Electric Co Ltd | 車両用前照灯 |
| JP2005228502A (ja) * | 2004-02-10 | 2005-08-25 | Koito Mfg Co Ltd | 車両用灯具ユニット |
| JP2008151642A (ja) * | 2006-12-18 | 2008-07-03 | Toyota Motor Corp | 測色装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US9689549B2 (en) | 2017-06-27 |
| CN104602997B (zh) | 2017-11-10 |
| US20150204504A1 (en) | 2015-07-23 |
| EP2894086A1 (en) | 2015-07-15 |
| EP2894086B1 (en) | 2017-12-20 |
| JPWO2014038177A1 (ja) | 2016-08-08 |
| EP2894086A4 (en) | 2016-12-07 |
| CN104602997A (zh) | 2015-05-06 |
| WO2014038177A1 (ja) | 2014-03-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5855258B2 (ja) | 車両用前照灯装置 | |
| US10458611B2 (en) | Headlight module and headlight device | |
| JP6918191B2 (ja) | 前照灯モジュール及び車両用前照灯装置 | |
| JP5902350B2 (ja) | 車両用前照灯モジュール、車両用前照灯ユニット及び車両用前照灯装置 | |
| JP6161732B2 (ja) | 前照灯装置 | |
| JP5920480B2 (ja) | 車両用前照灯装置 | |
| CN108603644B (zh) | 前照灯模块和前照灯装置 | |
| US10495277B2 (en) | Headlight module with two light guides receiving light from two light sources | |
| JP5437599B2 (ja) | 自動車用ヘッドライトのための照明モジュール | |
| JP2014191996A (ja) | 車両用灯具ユニット | |
| JP6079059B2 (ja) | 前照灯装置 | |
| CN118346939B (zh) | 一种超窄光学透镜及车灯 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20151110 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20151208 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5855258 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |