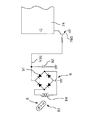JP4232071B2 - 車両用交流発電機の制御装置 - Google Patents
車両用交流発電機の制御装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP4232071B2 JP4232071B2 JP2001148244A JP2001148244A JP4232071B2 JP 4232071 B2 JP4232071 B2 JP 4232071B2 JP 2001148244 A JP2001148244 A JP 2001148244A JP 2001148244 A JP2001148244 A JP 2001148244A JP 4232071 B2 JP4232071 B2 JP 4232071B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- circuit
- power supply
- voltage
- field
- supply circuit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Description
【発明の属する技術分野】
本発明は車両用交流発電機の電圧制御装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
特開昭55ー127849号公報や特開平6ー284598号公報は、回転界磁極型オルタネータの回転時に、鉄心に残留して電機子巻線に鎖交する磁束が界磁極の回転により変調されて電機子巻線に誘起する交流電圧(残留磁化電機子巻線誘起電圧ともいう)を検出して、オルタネータの回転すなわちエンジン始動を検出している。
【0003】
特開平3ー215200号公報やEP664887号公報は、回転界磁極型オルタネータを構成する回転磁極に残留する磁束が多相電機子巻線に鎖交して誘起する多相交流電圧のうちの2相の電圧間の電位差を検出することにより、発電検出を行うことを開示している。これらの発電検出技術を用いれば、IG配線を省略できるとともに、IGスイッチオンにもかかわらずエンジン始動しない場合にはオルタネータを励磁することはないという利点が生じる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この種の残留磁化電機子巻線誘起電圧による回転検出によるIG線の廃止は、上記残留磁化電機子巻線誘起電圧の検出のために常時電力を消費し、かつ、回転停止時でもレギュレータに電源電力を給電する必要があるので、電力消費の低減が課題となっていた。
【0005】
また、電機子巻線は整流器を通じてバッテリに接続されているため、この整流器に水分や塩分が付着するなどして電流リークが生じると、上記残留磁化電機子巻線誘起電圧による回転検出が困難となる。
【0006】
本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、簡素な構成で良好に回転検出可能な車両用交流発電機の制御装置を提供することをその目的としている。
【0007】
【課題を解決する手段】
請求項1の車両用交流発電機の制御装置は、複数の界磁極を備えた界磁鉄心を有する回転子と、前記界磁極磁化用の界磁電流が通電される界磁巻線と、前記回転子が発生する回転磁界により交流電圧を誘起する電機子巻線が巻装された電機子鉄心を有する電機子とを備える回転磁極型交流発電機に装備されて、前記界磁電流の断続により前記交流発電機の出力電圧を所定値に制御する車両用交流発電機の制御装置において、
前記界磁電流を断続するスイッチ手段と、前記出力電圧に応じて前記スイッチ手段を制御する制御回路と、前記制御回路に電源を供給する主電源回路と、前記主電源回路を動作状態又は非動作状態に制御する副電源回路とを備え、前記副電源回路は、前記回転子の回転時に前記電機子鉄心の残留磁束が前記界磁巻線と鎖交して前記界磁巻線に誘起される残留磁化界磁巻線誘起電圧からなる回転起因電気信号に基づいて、前記残留磁化界磁巻線誘起電圧が所定のしきい値と交差する時点から所定の期間だけ前記主電源回路を一時的に動作状態にして前記制御装置を駆動させることを特徴としている。
【0008】
すなわち、本構成によれば、制御回路に電源電力を給電する主電源回路を回転子の回転が増大した場合にだけアクティブとするので、車両の非稼働時における消費電流を従来の発電検出式車両用交流発電機の制御装置より大幅に低減することができる。もちろん、本構成においても、車両の回転増大を検出しで主電源回路を起動させる副電源回路は電力を消費するが、この副電源回路が大電力を必要とする制御回路自体に電源電力を給電するのではないので、電力消費を低減できるわけである。
【0009】
上記した本発明によれば、前記回転起因電気信号は、前記回転子の回転時に前記電機子鉄心の残留磁束が前記界磁巻線と鎖交して前記界磁巻線に誘起される残留磁化界磁巻線誘起電圧からなり、前記副電源回路は、前記残留磁化界磁巻線誘起電圧が所定のしきい値と交差する時点から所定の期間だけ前記主電源回路を一時的に動作状態とする。
【0010】
上記した本発明によれば、回転検出動作の信頼性を向上することができる。なお、主電源回路が立ち上がり、界磁巻線に界磁電流が通電された後は、電機子巻線の発電電圧やそれを整流した出力電圧により発電状態すなわち回転状態を良好にモニタすることができる。
【0011】
更に説明すれば、電機子巻線は通常6個の整流器及び外部ラインを通じて外部のバッテリに接続され、これら整流器は外部から取り込んだ冷却空気により冷却されるため、整流器の表面が汚損されやすく、リークが生じやすい。これに対して、界磁巻線は密集して巻装されており電機子巻線よりも電気絶縁の劣化の危険が小さい。更に、界磁巻線は電機子巻線よりも格段に残留磁束と鎖交するターン数が多く、誘起電圧の増大に有利である。
【0012】
請求項2記載の構成によれば、前記副電源回路は、前記車両用交流発電機のバッテリ端子電位と前記主電源回路への電源電圧入力端子との間を開閉する電源スイッチを有し、前記主電源回路を一時的に動作状態とするための二値信号により前記電源スイッチを開閉制御することを特徴とする。これにより、主電源回路への電源電力供給の制御を確実に実施できる。
【0013】
請求項3記載の構成によれば、前記副電源回路は、前記交流発電機の前記出力電圧が所定値以上になった場合に前記主電源回路を優先的に前記動作状態とするので、発電機の回転数が所定値以上になった場合には安定して主電源回路を動作させることができる。
【0023】
好適な態様において、前記副電源回路は、前記所定期間にのみ出力されるHi信号を複数段のシフトレジスタに入力し、該シフトレジスタの各段の出力の論理和で得られる前記所定期間より長い第2の一定期間にのみHiが出力される信号の立ち上がりもしくは立ち下がりをトリガとするので、CR回路のコンデンサ容量を小さくでき実装容易にできるとともに、フリップフロップの不定状態を回避できより安定な電源回路を供給できる。
【0024】
【発明の実施の形態】
本発明の好適な態様を以下の実施例を参照して説明する。
【0025】
【第1実施例】
図1は第1実施例の車両用交流発電機の回路構成を示すブロック図である。
【0026】
1は車両用交流発電機(オルタネータ)、2は車載バッテリ、3は三相電機子巻線、4は電機子巻線3の各相出力端に接続される全波整流回路、6は界磁極を有する界磁鉄心(図示せず)に巻装される界磁巻線、7は界磁電流を調整してオルタネータ1の出力電圧を所定範囲内に制御する電圧制御装置である。
【0027】
71は界磁巻線と直列に接続されて界磁電流を断続するトランジスタ、72はトランジスタ71がオフの際に界磁電流を環流させるフライホイルダイオード(環流ダイオード)、73は全波整流回路4の出力電圧をモニタし、出力電圧が所定の範囲内に収まるようにパワートランジスタ71を駆動させる信号を発生する制御回路、74は電圧制御回路73を動作状態に保つべく電源電力を給電する電源回路(本発明で言う主電源回路)、75は回転子の回転を検出して電源回路を駆動するための信号を発する電源駆動回路(本発明で言う副電源回路)である。
【0028】
電源回路74自体は、制御回路73に電源電圧を給電する従来同様の回路であり、たとえば定電圧回路で構成してもよく、電源回路のIG端子に入力される電源電圧をそのまま制御回路73に電源電圧として印加してもよい。制御回路73は、バッテリ電圧と所定の調整電圧を比較して比較結果によりトランジスタ71を断続制御するコンパレータを含む。電源回路74及び制御回路73は従来同様であるので、詳細な説明を省略する。
【0029】
電源駆動回路75の一例を図2に示す。
【0030】
751は界磁巻線の高位側の電位を所定の定電圧(ここでは接地電位)と比較する第1のコンパレータ、752は、図示しない定電圧回路から給電される電源電圧Vccを分圧する抵抗群で各々の抵抗値は等しく設定される。なお、この定電圧回路を省略してバッテリ電圧を直接印加してもよい。753は電源電圧Vccの2/3分圧と後述のCR積分回路757の出力とを比較する第2のコンパレータ、754は第1のコンパレータ751の出力電圧と電源電圧Vccの1/3分圧とを比較する第3のコンパレータ、755は第2のコンパレータ753出力をリセット入力、第3のコンパレータ754の出力をセット入力とするRSフリップフロップ、757はコンデンサC1と抵抗R2とを直列接続してなる前述のCR積分回路、759はフリップフロップ755の反Q出力をベース抵抗Rbを通じて受けてコンデンサC1の電荷を放電させるトランジスタである。
【0031】
764は、図示しない抵抗分圧回路から出力されるオルタネータ1の直流出力電圧の分圧Vsと所定の基準電圧とを比較するコンパレータ、765はフリップフロップ755のQ出力とコンパレータ764の出力との論理和をとるORゲート、760はORゲート765の出力で駆動され、電源回路(主電源回路)74のIG端子に供給する電源電力を断続するアナログスイッチである。
【0032】
Cbはコンパレータ751の一対の入力端間に接続される高周波バイパスコンデンサであり、接地電位へ重畳する高周波ノイズ電圧をバイパスしてコンパレータ751が誤動作するのを防止する。なお、車両用交流発電機の回転開始により残留磁化により生じる残留磁化界磁巻線誘起電圧は交流電圧ではあるが、低周波数のためこの高周波バイパスコンデンサによる減衰効果は小さい。
【0033】
図3を用いて電源駆動回路(本発明で言う副電源回路)75の動作を以下に説明する。
【0034】
オルタネータ1の各鉄心には前回の発電によって磁化が残留している。回転子が回転することで界磁コイル6には、界磁鉄心の残留磁化と電機子鉄心の残留磁化との合成残留磁化(この場合は特に電機子鉄心残留磁化)により形成される残留磁束が界磁極に対して周期変動し、これにより界磁巻線に鎖交する上記残留磁束が周期変動することにより交流電圧が誘起される。
【0035】
更に説明すれば、回転開始直後の電機子鉄心の残留磁化の空間分布を考えると、前回の回転子の爪状の界磁極の停止時の位置により電機子鉄心の内周面において周方向にN極とS極とをその合計が界磁極総数と一致するだけ周方向交互に生じている。その結果、界磁極が回転すると、この電機子鉄心の残留磁化により形成されて界磁巻線6と鎖交する磁束が周期変化し、界磁巻線6には交流電圧が発生する。このとき、スイッチ71はオフしているものとする。この交流電圧の振幅はたとえば約0.2〜0.4V、周波数は回転磁極数を2P1個とするとN〔rpm〕にてP1・N/60〔Hz〕となる。
【0036】
コンパレータ751は、この交流電圧と定電圧(ここでは接地電位)とを比較して、デュ−ティ比50%、周波数P1・N/60の矩形波パルス電圧inを出力する。この矩形波パルス電圧inは第3のコンパレータ754に入力されて分圧Vcc/3と比較され、フリップフロップ755のセット入力になる。もちろん、基準電圧を接地以外に設定することにより任意デュ−ティの矩形波パルスを作ることができる。
【0037】
第2コンパレータ753には後段のCR回路757(第1のタイマ)の出力が入力され、分圧2・Vcc/3と比較される。つまり、CR回路757の出力が分圧2・Vcc/3に達した時点で第2コンパレータ753はHi出力を出し、フリップフロップ755をリセットする。
【0038】
第2コンパレータ753の出力がLo、つまりCR回路の出力が2・Vcc/3以下の期間ではフリップフロップ755のQ出力はHi、反Q出力はLoになり、トランジスタ759がオフとなってコンデンサC1が充電される。コンデンサC1が充電されて電位Vcが2・Vcc/3に達するとフリップフロップ755がリセットされてトランジスタ759がオンし、コンデンサC1が放電される。結局、フリップフロップ755は、コンデンサ757が充電されている期間、つまりほぼCR回路757の時定数に等しいだけの一定期間だけHiを出力する。フリップフロップ755の出力がHiである場合、電源回路74のIG端子に電力を供給するスイッチ760はオン状態に維持され、電源回路74が動作可能になる。
【0039】
回転数が低い場合には、フリップフロップ755のセット入力の周期よりCR回路757のCR時定数の方が短いので、フリップフロップ755がリセットされる時点つまりコンデンサC1の電位Q2が2・Vcc/3となる時点ではセット入力はLoになっており、次に、セット入力がHiになるまで、フリップフロップ755はLo出力を維持し、電源駆動回路75の出力Out1はLoを維持する。
【0040】
回転数が所定値を超えるとフリップフロップ755のセット入力の周期の方がCR時定数より短くなるので、フリップフロップ755のリセット時点つまりコンデンサC1の電位が2・Vcc/3になる時点ではセット入力もHiになっており、フリップフロップ755はHi出力を維持し、電源駆動回路75の出力Out1はHiを維持する。つまり、回転数が高くなるにつれて界磁巻線6に誘起される電圧の周波数が高くなって出力Out1のオフ期間が次第に短縮され、やがては連続的にオンになる。つまりは連続的に電源回路74を動作状態に維持できる。すなわち、低回転域では間欠動作であり、ある回転数以上で連続動作に移行する。
【0041】
たとえば12極(6極対)の回転磁極を備えるオルタネータにおいて、R2=100kΩ、C1=0.1μFに設定すると約1000〔rpm〕にて連続的に動作可能である。一般に2・P1極のオルタネータをN1〔rpm〕で連続に動作させたい場合、CR回路757の時定数を60/(P1・N1)〔sec〕に設定すればよい。
【0042】
すなわち、上記実施例では、残留磁化界磁巻線誘起電圧の周期(周波数関連信号電圧、回転起因電気信号)とCR回路(第1のタイマ)757の時定数との比較により、電源電力を給電するかどうかを判定するので、回転数が所定値以上となった場合に制御回路73に電源電力を安定に連続給電することができる。
【0043】
なお、RSフリップフロップ755を用いた場合、セット、リセット入力がともにHiとなる場合にフリップフロップ出力が不定となる。そこで、抵抗分圧回路761によりオルタネータ1の出力電圧を検出し、コンパレータ764でバッテリの開放端子電圧よりも高い基準電圧たとえば13.0Vに対応する基準電圧値Vrefと比較し、オルタネータ1の出力電圧がこの基準電圧値Vrefよりも高い場合にHiを出力し。この信号Out2と出力Out1との論理和信号にてスイッチ760のゲートを駆動すれば動作を一層の安定化することができる。
【0044】
また、オルタネータ1の出力電圧(直流出力電圧)とバッテリの開放端子電圧よりも高い基準電圧との比較結果を論理和ゲートを通すことで更に以下の如き効果も奏することができる。
【0045】
車両の運行が終了して車載エンジンを停止させるプロセスを考える。通常、バッテリは略満充電状態に維持されているので、その端子電圧、即ちコンパレータ764の入力電圧はほぼ14.5Vに対応する値になっており、コンパレータ764の出力はHiである。運転者がエンジンを停止させるとオルタネータ1も直ちに停止するものの、オルタネータ1の電圧制御装置の主電源はコンパレータ764のHi信号を受けてまだアクティブ状態にある。従って、適当なデュ−ティ比でオルタネータ1の界磁巻線6に励磁電流を通電し続ける。やがて車載バッテリの端子電圧は充電分極の消失などにより無負荷電圧略12.8Vにまで落ち込み、コンパレータ764の出力を反転させて電源回路74を非動作状態にする。一般の車載バッテリは化学反応を利用しているので、エンジンが停止し、オルタネータ1の発電が停止してから電圧制御装置の電源回路74が非動作状態になり、界磁巻線6に流れる励磁電流が完全に消滅するまで10数秒〜数10秒要する。
【0046】
したがって、この実施例では、界磁巻線6の減衰励磁電流が回転停止時に電機子鉄心を消磁するという現象を、バッテリ電圧すなわちオルタネータ1の直流出力電圧に基づく制御回路への電源電力給電停止の遅延により実現しているので、次回のエンジン始動時にも、オルタネータ1の電圧制御装置を確実にスタンバイ状態に復帰させることができる。もちろん、直流出力電圧の大きさの変化ではなく、その周波数変化や電機子巻線の発電電圧又は周波数の変化により制御回路への電源電力給電停止の遅延を実現してもよい。
【0047】
なお、上記実施例では、CR回路の時定数を利用したタイマすなわち遅延回路を用いて時限信号を出力するアナログ信号処理を説明したが、各種ディジタルカウンタを利用したディジタル信号処理でも同等の機能を実現できることは言うまでもない。
【0048】
【第2実施例】
第2実施例を図4を参照して説明する。
【0049】
この実施例は、上述した実施例1において、コンパレータ751の入力電圧を残留磁化界磁巻線誘起電圧から永久磁石型電磁誘導式回転センサ8に変換した点をその特徴としている。
【0050】
この回転センサ8は、回転子に装備された永久磁石からなる第2の界磁極82と、この第2の界磁極82の回転により交流電圧を発生する第2電機子84とからなる。第2電機子84は、図示しない電機子鉄心(第2電機子鉄心)に1つの電機子巻線(第2電機子巻線)を巻装して構成されている。動作原理は実施例1と同じであるが、電機子鉄心の残留磁化ではなく永久磁石からなる第2の界磁極82の回転を検出するので高い信号電圧を発生することができる。
【0051】
(構造)
回転センサ8の一例を図5〜7を参照して説明する。
【0052】
60は図示しないハウジングに回転自在に支持される回転子、61は界磁鉄心、62はシャフト、63、64はスリップリングである。スリップリング63,64は図5では界磁鉄心61ないに隠れている界磁巻線6の両端に個別に接続されている。
【0053】
この実施例の特徴は、図示しないハウジングに固定された回転センサ8が、スリップリング給電用のブラシ装置と一体に形成されている点にある。回転センサ8の構造を更に詳しく説明する。
【0054】
回転センサ8は、貫通孔80を有する樹脂製のホルダ81を有し、回転子60のシャフト62は、貫通孔80に同軸に貫通している。図6は回転センサ8のX方向断面図、図7はそのY方向断面図である。
【0055】
82は円筒形状の永久磁石からなる第2の磁極であって、スリップリング63,64とともにスリップリング支持用の樹脂筒65に一体に成形されてシャフト62に嵌着、固定されている。第2の磁極82の外周面には周方向一定ピッチでN極とS極とが極性交互に着磁されている。
【0056】
83は、ホルダ81に径方向に延在する凹部であり、凹部83の内部には、軟磁性の鉄心85に巻回転されたピックアップコイル84が収容されている。鉄心85は湾曲されており、その両端はギャップを介して第2の磁極82の外周面に対面している。この場合、軟鉄心85の両端は第2の磁極82の磁極ピッチ離れて第2の磁極82の外周面に対面することが好ましい。66、67は、ホルダ81に径方向摺動自在に保持されるブラシであり、68,69はブラシ66,67をスリップリング63,64に押しつけるコイルスプリングである。
【0057】
この実施例によれば、第2の磁極82をスリップリング支持用の樹脂筒65に一体成形し、更に、電磁誘導式の回転センサ8のピックアップコイル84をブラシホルダを兼ねるホルダ81に固定しているので、構造が簡素となり、既存のオルタネータに設計変更を抑止しつつ容易に装着することができる。
【0058】
この実施例では、たとえ界磁巻線6などが泥や塩水などにより絶縁劣化しても、確実に回転検出を実現することができる。凹部83をポッティング材などで封止しておくとより一層、耐環境性を向上することができる。なお、この永久磁石式回転センサ8は、ブラシホルダとは独立に設置することができ、ピックアップコイルの代わりにホール素子などの半導体磁気センサを採用してもよいことはもちろんである、
(変形態様1)
この実施例の変形態様を図8に示す。
【0059】
この変形態様では、副電源回路75を整流回路9に変更した点が異なっている。この整流回路9は、ピックアップコイル84から出力される交流電圧を全波整流するダイオードブリッジ回路91と、このダイオードブリッジ回路91から出力される全波整流電圧を平滑する平滑コンデンサ92とからなり、その出力電圧Vdcは直接又は図示しないバッファ回路を通じてスイッチ760に制御入力として供給される。すなわち、
この直流電圧Vdcを所定回転数N1〔rpm〕にてスイッチ760をオン可能に設計しておけば、オルタネータがN1〔rpm〕に達したら自動的にレギュレータが稼働状態になり直ちに発電開始する。したがって、この変形態様では、回路構成が簡素となり、副電源回路がバッテリ電力を消費することがない。
【0060】
(変形態様2)
この実施例の変形態様を図9に示す。
【0061】
この変形態様は、図4に示す回転センサ8をもつ副電源回路75の信号inに更に、実施例1同様の残留磁化界磁巻線誘起電圧を用いた信号Sを付加した点をその特徴としている。
【0062】
更に詳しく説明すれば、7510は図2に示すコンパレータ751に相当するコンパレータであり、界磁巻線8の残留磁化界磁巻線誘起電圧を二値信号に変換する。コンパレータ7510から出力される二値信号は、所定段数の分周回路762で分周された後、オア回路763でコンパレータ751の出力信号inとの論理和信号が形成され、この論理和信号がコンパレータ754のー入力端に出力される。
【0063】
この変形態様によれば、残留磁化界磁巻線誘起電圧と回転センサ8の出力電圧の両方を回転検出に用いるので、信頼性を向上することができる。なお、分周回路762は、回転センサ8の出力交流電圧の周波数と界磁巻線6の出力交流電圧(残留磁化界磁巻線誘起電圧)の周波数とを一致させるためのものであるが、第2の磁極82の着磁磁極数を界磁鉄心の爪極形界磁極数と一致させれば、分周回路762を省略することができる。
【0064】
【第3実施例】
第3実施例を図10を参照して以下に説明する。
【0065】
この実施例は、図2に示す副電源回路75において、フリップフロップ755のQ出力Voutをクロック信号CLの周波数でシフトされるシフトレジスタ765に入力し、このシフトレジスタ765の各段の出力をオア回路767に入力し、このオア回路767の出力をオア回路765に入力する点をその特徴としている。
【0066】
この実施例では、CR回路757のコンデンサC1の容量を図2に示すコンデンサC1の容量の約1/10に設定する。その結果、CR回路757から出力される出力Q2のHiレベル継続時間は第1実施例の1/10に短縮される。
【0067】
しかし、この実施例では、シフトレジスタ765を10段に設定しているため、シフトレジスタ765の各段の出力信号の論理和信号Out3は、シフトレジスタ765のクロック信号CL周波数φを1/CR近傍に設定しておくとほぼ第1実施例の信号Out1と同じ期間だけオア回路765にHiレベルとなる信号Out3を出力することができ、コンデンサ容量を格段に小さくできるとともに、第1実施例で述べたRSフリップフロップの不定状態を容易に回避できる。すなわち、シフトレジスタ765の段数に反比例してCR回路757のコンデンサC1として第1実施例のコンデンサC1の1/nの容量のものを採用することができる。これは、シフトレジスタ765に入力されたHi電位レベルがシフトレジスタ765の各段をシフトしていく間中、ずっとオア回路767の出力Out3がHiレベルとなるからである。オア回路767と765とを一個のオア回路に置換することも当然可能である。
【0068】
なお、出力信号Out1がHiとなった場合はHiを出力し、その後、入力される出力信号Out1のパルス数をカウンタでカウントし、カウンタのカウント値が所定値に達したらこれまでのカウント時間に等しいだけLoを出力するデジタル回路を用いてもよく、同等の回路機能を種々のハードウエア又はソフトウエアで実現することができる。図10の各部の電位変化を図11のタイミングチャートに示す。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1実施例の車両用交流発電機の回路構成を示すブロック図である。
【図2】図1の副電源回路の一例を示す回路図である。
【図3】図2の副電源回路の各部電位変化を示すタイミングチャートである。
【図4】図1の副電源回路の他例を示す回路図である。
【図5】図4の回転センサの一例を示す分解斜視図である。
【図6】図5の回転センサの要部拡大軸方向断面図である。
【図7】図5の回転センサの要部拡大軸方向断面図である。
【図8】図1の副電源回路の他例を示す回路図である。
【図9】図1の副電源回路の他例を示す回路図である。
【図10】図1の副電源回路の他例を示す回路図である。
【図11】図10の副電源回路の各部電位変化を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
1 車両用発電機
3 電機子巻線
6 界磁巻線
7 電圧制御装置
71 トランジスタ(スイッチ手段)
73 電圧制御回路(制御回路)
74 電源回路(主電源回路)
75 電源駆動回路(副電源回路)
Claims (3)
- 複数の界磁極を備えた界磁鉄心を有する回転子と、前記界磁極磁化用の界磁電流が通電される界磁巻線と、前記回転子が発生する回転磁界により交流電圧を誘起する電機子巻線が巻装された電機子鉄心を有する電機子とを備える回転磁極型交流発電機に装備されて、前記界磁電流の断続により前記交流発電機の出力電圧を所定値に制御する車両用交流発電機の制御装置において、
前記界磁電流を断続するスイッチ手段と、
前記出力電圧に応じて前記スイッチ手段を制御する制御回路と、
前記制御回路に電源を供給する主電源回路と、
前記主電源回路を動作状態又は非動作状態に制御する副電源回路と、
を備え、
前記副電源回路は、前記回転子の回転時に前記電機子鉄心の残留磁束が前記界磁巻線と鎖交して前記界磁巻線に誘起される残留磁化界磁巻線誘起電圧からなる回転起因電気信号に基づいて、前記残留磁化界磁巻線誘起電圧が所定のしきい値と交差する時点から所定の期間だけ前記主電源回路を一時的に動作状態にして前記制御装置を駆動させることを特徴とする車両用交流発電機の制御装置。 - 前記副電源回路は、
前記車両用交流発電機のバッテリ端子電位と前記主電源回路への電源電圧入力端子との間を開閉する電源スイッチを有し、
前記主電源回路を一時的に動作状態とするための二値信号により前記電源スイッチを開閉制御することを特徴とする請求項1記載の車両用交流発電機の制御装置。 - 前記副電源回路は、
前記交流発電機の前記出力電圧が所定値以上になった場合に前記主電源回路を優先的に前記動作状態とすることを特徴とする請求項1又は2記載の車両用交流発電機の制御装置。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2001148244A JP4232071B2 (ja) | 2000-07-12 | 2001-05-17 | 車両用交流発電機の制御装置 |
| US09/885,163 US6707276B2 (en) | 2000-06-26 | 2001-06-21 | Voltage regulator of AC generator having circuit for detecting voltage induced in field coil |
| DE10130712A DE10130712A1 (de) | 2000-06-26 | 2001-06-26 | Spannungsregler für einen Fahrzeugwechselstromgenerator |
| FR0108424A FR2812140A1 (fr) | 2000-06-26 | 2001-06-26 | Regulateur de tension d'un generateur a courant alternatif pour vehicule |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2000211706 | 2000-07-12 | ||
| JP2000-211706 | 2000-07-12 | ||
| JP2001148244A JP4232071B2 (ja) | 2000-07-12 | 2001-05-17 | 車両用交流発電機の制御装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2002095295A JP2002095295A (ja) | 2002-03-29 |
| JP4232071B2 true JP4232071B2 (ja) | 2009-03-04 |
Family
ID=26595901
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2001148244A Expired - Fee Related JP4232071B2 (ja) | 2000-06-26 | 2001-05-17 | 車両用交流発電機の制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP4232071B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100450706B1 (ko) * | 2002-01-11 | 2004-10-01 | 미래산업 주식회사 | 부품공급장치 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06284598A (ja) * | 1993-03-29 | 1994-10-07 | Sawafuji Electric Co Ltd | 車両用充電発電装置 |
| JP3091768B2 (ja) * | 1993-06-14 | 2000-09-25 | エコエアー コーポレーション | 電圧調整器付きハイブリッド交流発電機 |
| JP3299380B2 (ja) * | 1994-04-27 | 2002-07-08 | 三菱電機株式会社 | 車両用交流発電機の制御装置 |
| DE19611908A1 (de) * | 1996-03-26 | 1997-10-02 | Bosch Gmbh Robert | Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer geregelten Spannung |
| JP3736011B2 (ja) * | 1997-03-21 | 2006-01-18 | 株式会社デンソー | 車両用発電制御装置 |
| JP4192439B2 (ja) * | 2000-06-19 | 2008-12-10 | 株式会社デンソー | 車両用交流発電機の制御装置 |
-
2001
- 2001-05-17 JP JP2001148244A patent/JP4232071B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2002095295A (ja) | 2002-03-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100271475B1 (ko) | Ac발전장치 및 그 제어방법 | |
| JP3865157B2 (ja) | 車両用交流発電機 | |
| JP3775189B2 (ja) | 内燃機関用スタータジェネレータ | |
| US6420855B2 (en) | Vehicular ac generator having voltage control unit | |
| JP3664379B2 (ja) | 車両用交流発電機の電圧制御装置 | |
| US6664767B2 (en) | Voltage regulator of vehicle AC generator having variable bypass circuit resistance | |
| JP3736011B2 (ja) | 車両用発電制御装置 | |
| US6707276B2 (en) | Voltage regulator of AC generator having circuit for detecting voltage induced in field coil | |
| JP4200672B2 (ja) | 車両用発電制御装置 | |
| JP4006941B2 (ja) | 車両用発電制御装置 | |
| JP4232071B2 (ja) | 車両用交流発電機の制御装置 | |
| JPH0951697A (ja) | 車両用発電装置 | |
| JP4192427B2 (ja) | 車両用発電制御装置 | |
| JP3666240B2 (ja) | インバータ装置 | |
| JP4265115B2 (ja) | 車両用交流発電機の電圧制御装置 | |
| KR100707517B1 (ko) | 자동차용 동기발전기-스타터와 같은 전기 기기의 로터필드 코일 전력의 제어를 위한 방법 및 장치 | |
| JP2001069797A (ja) | 始動発電機の電流調整装置 | |
| JP3015098B2 (ja) | オルタネータ | |
| CN111448751B (zh) | 用于运行用于机动车中的电存储器的充电调节器的方法 | |
| JP4135052B2 (ja) | 車両用交流発電機 | |
| KR0124034B1 (ko) | 차량용 교류발전기 | |
| KR200316730Y1 (ko) | 차량용교류발전기의전압조정기 | |
| JPS59139847A (ja) | 回転子巻線を有する直流ブラシレスモ−タ | |
| JP2003033095A (ja) | 車両用交流発電機の電圧制御装置 | |
| JPH09191695A (ja) | 電動発電機 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070709 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080610 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080718 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080909 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20081023 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20081113 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20081126 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (prs date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111219 Year of fee payment: 3 |
|
| R150 | Certificate of patent (=grant) or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (prs date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121219 Year of fee payment: 4 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (prs date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131219 Year of fee payment: 5 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |